『小野 篁(おのの たかむら)』とは何者?
昼は朝廷・夜は地獄を行き来した“只者ではない”偉人の生き様
🐉もし、あなたが
「地獄と現世を行ったり来たりして働いていた人がいる」と聞いたら、信じますか?
——それが、今回ご紹介するいまから約1200年くらい前に活躍した、
平安時代の不思議な天才、
小野篁(おののたかむら)です。
昼は天皇のそばで法律や政治の仕事をこなし、夜は地獄で閻魔大王のお手伝いをしていた……。
そんな不思議な伝説を持ちながらも、
頭の良さと行動力でどんどん出世していった人物なのです。
でも、ただすごいだけではありません。
命令に納得できなければ「それは違う!」とはっきり意見を言い、罰を受けても決してくじけなかった。
だからこそ、彼の物語は「信じたことを貫く強さ」「何度でもやり直せる勇気」を、私たちに教えてくれるのです。
🌊 すぐわかるエピソード
「昼の上司は天皇、夜の上司は閻魔大王」
そんなウソのような本当のような話が、千年以上も語りつがれている人物、それが小野篁です。
例えば、あなたが学校に通って、帰ってきたら夜は“幽霊の世界”で仕事をする……そんな生活を想像してみてください。
とても大変そうですよね。でも、小野篁はそれほどいくつもの世界をまたにかけて活やくしていたと伝えられているのです。
なぜそんな伝説が残ったのか?
それは、彼の生き方がまるで“人間を超えた存在”のように見えたからです。
実際に、彼は学問・政治・詩・書道と何でもこなす「スーパー万能人」。
一度は島流しという大きなピンチに陥っても、見事にカムバック!
そして、そんな彼が夜に出入りしていたと言われる井戸が、今も京都にあるのです。
伝説はきっと、彼の努力や信念を伝える“もう一つの形”だったのかもしれません。
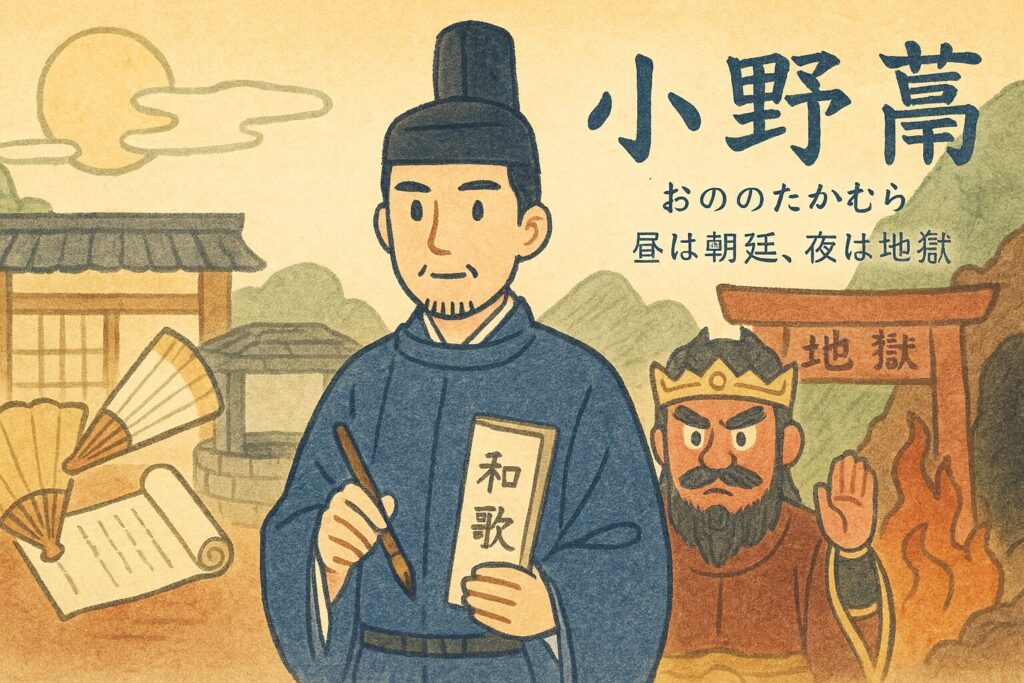
小野篁とは?
小野篁(おのの たかむら)は、
平安時代前期(802〜853年)に活躍した
公卿(こうぎょう)であり、
文人(ぶんじん)でもありました。
公卿(こうぎょう)と呼ばれる高位の貴族で、朝廷の重要な政治決定に関わる立場でした。
文人(ぶんじん)としても知られ、漢詩・和歌・書・学問など、芸術や教養の分野でも高い才能を発揮しました。
つまり彼は、「政治」と「文化」の両面で時代を支えた、まさに“二刀流”の人物だったのです。
生没年:延暦21年(802年)〜仁寿2年12月22日(853年2月3日)
出身地:正確な出生地については諸説ありますが、現在では一般的に、山城国(現在の京都府南部)出身とされています。
出身・家系:父は漢詩や文章に秀でた小野岑守(みねもり)。その才能を受け継ぎ、小野篁も漢詩や和歌、書道において高い評価を得ています
官歴・ジャンル:参議(さんぎ)などの高い位を歴任し、儒学・漢詩・和歌・書道で活躍。百人一首にも歌が選ばれています。
異名:「野相公」「野宰相」、その反骨精神から「野狂(やきょう)」とも呼ばれました。
小野篁は、
優れた文才を受け継ぐ名門「小野氏」の出身です。
父は小野岑守(おのの みねもり)といって、
朝廷の役人であり、漢詩にも秀でた教養人。篁の学問の基礎は、この父から受け継がれたものでした。
祖先に当たるとされている、小野妹子(おのの いもこ)は、飛鳥時代に遣隋使として中国に派遣されたことで有名な人物です。
つまり篁は、「外交」「政治」「文学」に優れた血筋を持ち、まさに“才気の系譜”を受け継いだ存在だったのです。
伝説が語る
“昼夜を行き来する両立の達人”
小野篁には、まるでマンガのような伝説があります
■ 地獄へ通った井戸(京都・六道珍皇寺)
『今昔物語集』『江談抄』『元亨釈書』などの中世説話集に記録されており、地獄と現世を行き来していたと伝えられています。
京都・東山区にある六道珍皇寺には、実際に「冥途通いの井戸」(地獄への入口)と「黄泉がえりの井戸」(戻る出口)が現存しています。
■ 閻魔大王の補佐役となった逸話
『今昔物語集』では、例えば藤原良相(ふじわら よしみ)が死後、冥界で裁きを受ける際に「彼の弁護をしたのは小野篁でした」とされ、良相が蘇ったと記録。
『江談抄』でも、権力者・藤原高藤(たかふじ)の救済や、篁が閻魔大王の隣にいたという伝承が残されています。

■ なぜこのような伝説が生まれたのか?
小野篁は官僚として厳しく裁きを下す役目を担っていたため、地獄の裁判官・閻魔王と重ねられた説が生まれたと考えられます。
また、彼の反骨精神や超人的な仕事ぶりが、「地獄まで働く」という誇張された称賛となり、千年以上もの間語り継がれてきたのです。
小野篁の生涯と主な功績
若年期:武を愛し学問を志す転機
若き日の小野篁は、身長約190cmの長身を活かし、馬術や弓術に夢中でした。しかし、父・小野岑守は漢詩に優れ、篁は学問より遊びに傾いていたことを嵯峨天皇から強く叱責されます。その言葉に篁は“猛反省”。18歳すぎには三年ほどで難関の「文章生試」に合格し、以後は文武両道を体現し始めました。
政治家として:反骨と流罪、そして復権
篁は大内記や東宮学士、さらには遣唐副使に任じられるなど要職を歴任します。しかし838年、遣唐使の航海中、正使・藤原常嗣が船を交換する不誠実さに反発し、病を理由に乗船を辞退。風刺詩『西道謠』を詠んだため嵯峨上皇の怒りを買い、隠岐への流罪に処されました。流刑中にも『謫行吟』という美しい詩をのこし、2年後に赦免。仁明天皇にも重宝され、公卿・参議に復帰しました。
文化的功績:文芸と和歌の才
漢詩・和歌・書道に長け、百人一首にも歌が選ばれるなど文学的評価も高いです。特に「わたの原八十島かけて…」の和歌は流刑の悲しみをうたった名作。また、『令義解』という律令解説書の序文も執筆しています。
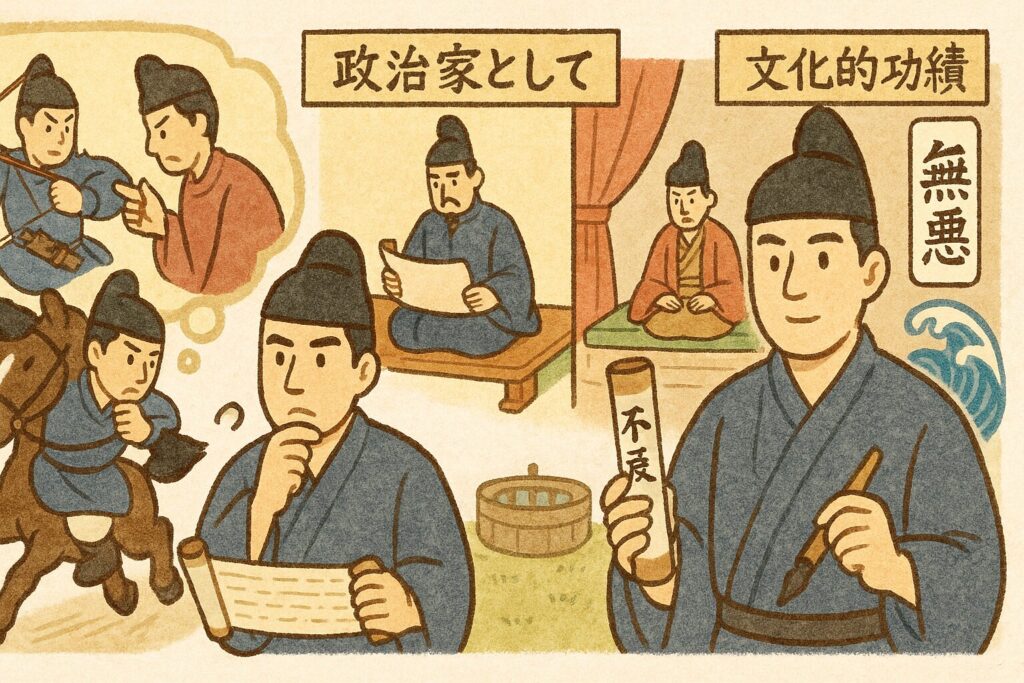
名言・思想から学ぶ
鋭い知性とユーモアの使い手
あるとき、「無悪善(むあくぜん)」と書かれた札が宮中に掲示され、完成な漢字を示すか謎かけのようでした。天皇に読めと命じられた篁は「峨(が)あらずなら善し」つまり「悪い嵯峨(天皇)がいなければ良い」と読み返し、机上ではない本音をユーモアを交えて伝えます。さらに、片仮名「子」を12個並べる難問にも、「猫の子仔猫、獅子の子仔獅子」と即答し、天皇を笑わせました。
思慮深さと勇気が根底
これらのエピソードから、篁は言葉で敬意と本音を両立させ、難題にも理性で挑む姿勢を持っていたことがうかがえます。上司への配慮を欠かさずに、かつ自分の思考をしっかり伝える、そのバランス感覚は現代にも大いに役立ちます。
小野篁への問いかけと返答
■ 第一の謎:「無悪善(むあくぜん)」
【問題】
「無悪善」という漢字三文字が書かれた札。
普通に読めば「悪がなければ善である」という道徳的な意味にも取れますが、これは嵯峨天皇が臣下たちに「機転ある読み」を求めた謎かけでした。
【篁の回答】
「“峨”がなければ“善”である」と読み、
つまり「“嵯峨(さが)”がなければ善い」というシャレに仕立て上げたのです。
【思想・意図】
篁は、命令や上意に対しても真っ向から意見を言う反骨精神の持ち主でした。
しかしこのとき、彼はあえてユーモアという“やわらかい刃”で本音を伝えたのです。
それは、「ただ従うだけではなく、自分の意見をどう伝えるか」に重きを置いた高度な知性の現れでした。
【もし本人の言葉で語るなら】
「“無悪善”と書かれていた。……ならば、“峨”を取ってしまえば“善”になるではないか。
すなわち、嵯峨(天皇)がいなければよろしい――
……と、言葉の綾で申したまで。
されど陛下、時に臣下の目も必要かと存じます。」
「“悪(=が)”が無ければ、“善”になります」と読んだ。
ここでの「が」は「嵯峨(さが)」の中の「が」とも受け取れるため、
「嵯峨がなければ、善くなる」とも読めてしまう。
つまりこれは、
🌀「天皇がいなければ、世の中はよくなる」とも聞こえてしまうシャレ(=風刺)だったのです。
この言葉遊びは**“嵯峨天皇=悪”と断定しているのではなく、**
あくまで小野篁がユーモアで「本音」を遠まわしに言ったという風刺表現。
■ 第二の謎:「子子子子子子子子子子子子」
【問題】
片仮名の「子」が12個、ずらりと並べられたこの暗号文。
何を意味するのか、宮中の誰もが首をかしげました。
【篁の回答】
「ねこのここねこ、ししのこじし」と即答。
(=「猫の子(仔猫)、獅子の子(仔獅子)」)
【思想・意図】
これは単なる言葉遊びではありません。
篁は言葉のリズムと意味、音の二重性を瞬時に見抜き、“遊びの中に知”を込めた回答を出しました。
場の空気を和ませつつ、「思考は柔軟であれ」という自身の哲学を実践した形です。
【本人の口調で言えば】
「“子”が並んでいる? ふむ……これは“ねこのここねこ、ししのこじし”よ。
単なる“子”に見えても、その中にいくつもの命が眠っておる。
目を凝らせば、意味はどこにでも転がっているのだ。」
「『子』という字は、読む人しだいで『こ』にも『し』にもなる。
だから私は、こう読んだのだ――
『ねこの子はこねこ、ししの子はこじし』とね。」
「子子子子」と書いてあるけど、読み方を変えて、意味がわかるように言いかえると、
「ねこのこねこ」「ししのこじし」になるよ。
だから、『ね』とか『の』は、意味をちゃんと伝えるために自分で足して読んでるだよ。
「これは“読み”のちから。書いてない言葉も、こころの中で見つけてやるのが、学問の面白さよ。」
このように、小野篁の答えには
ただの賢さではない、信念と優しさ、そして遊び心が込められていたのです。
彼の知性は、相手を打ち負かすのではなく、「ふっと笑わせて考えさせる」力でした。

🐎 文武両道への覚悟——若き日の決断
陸奥(むつ)の国で馬に乗り、弓を射まくっていた青年・小野篁。ところが帰京後、その武の才能ばかりが目立ち、嵯峨天皇から問いかけられます。「漢詩に秀でた父を持ちながら、なぜ学問に励まぬ?」その一言が篁の心に響き、一夜にして“猛反省”。馬場から書斎へ場所を変え、自らの進む道を決め直したのです。
🌊 海の風と反骨心——遣唐使拒否の真相
838年、小野篁は遣唐副使に任命されます。ところが航海中、船が交換され、“理不尽”を感じた篁は病を理由に乗船拒否。帰国後、『西道謠』という詩で朝廷制度そのものを風刺しました。その勇気と正直さにより嵯峨上皇は激怒。隠岐へ流されるという大きな代償を払うことになります。
しかし流刑中にも美しい詩を作り、2年後には公卿として復権。逆境を乗り切るその姿は、今も胸を打ちます。
✍️ 言葉で信念を伝える——名言と知略
ある日、「無悪善」と書かれた札が宮中に貼られる事件が起こります。天皇は篁に解読を求めますが、篁は「“峨”がなければよかろう」と読んでしまいました。このときの机上のユーモアと、相手の欄を崩さず真実を伝える姿勢に、人々は驚嘆しました。その鋭さと配慮の両立は、現代のコミュニケーションにも通じるものがあります。
❓問いかけ:あなたなら、どう動きますか?
自分の意見と上司の意向の間で葛藤したとき、あなたはどう伝えますか?
馬に乗る日課と勉強、どちらを優先しますか?自分なりのバランスの取り方を教えてください。
🧭 考察として
型にとらわれない二刀流力
小野篁ほど私たちに「自分らしく」「信念を貫き」「多才であれ」と教えてくれる人は、他にいないでしょう。彼は、昼間は政治に携わり、夜は地獄で閻魔大王の補佐をしていた──そんな伝説を持つ“反骨&多才二刀流の達人”でした。島流しの流刑に耐えながらも、2年後には公職に返り咲くその復活力。まさに「只者ではないからこそ、奇跡の復活も果たせた」のです。
今日の私たちも、仕事に家庭に社会に「○○もやらねば、△△もがんばらなくちゃ」と、つい自分を追い込みがちです。しかし、篁の姿はこう語りかけます。
「焦らず、無理せず、自分にしかできないことを中心に据えよ」と。
彼のように「多方面で活躍しながらも、自分の信念を曲げず、復活し続ける強さ」は、現代人にとっても大切なメッセージです。
小野篁という偉人からは
🧠“只者ではない力”があれば苦境からでも復活できる、
ということを教えてくれているのではないでしょうか。
小野篁の魅力は、ズバリ「型にはまらない反骨&多才二刀流力」にあります。
昼間は国家を支える公職に携わり、夜には地獄を治める伝説の裁判官
──これほど大胆かつ繊細な二つの顔を持つ人物は、平安時代でも稀でした。
彼が流刑から復権したのも、
この“只者ではない”存在感と信念ゆえ。
これは私たちにも問いかけています。
「自分は、平凡な毎日を過ごしていないか? せめて一つ、自分にしかできない何かに取り組んでいるか?」と。

📘 更に学びたい人へ
📚 書籍のご紹介
『宇治拾遺物語』
『今昔物語集』
『古今和歌集』
特徴とおすすめ理由
『宇治拾遺物語』
著者・訳者:町田康(現代語訳)
出版社:河出書房新社(2019年刊)
特徴とおすすめ理由:中世の説話のユーモアと教訓がいきいきと蘇っており、小野篁の人となりを感じるエピソードも多数収録。わかりやすい現代語訳で初心者にも読みやすいです。
『今昔物語集』(新潮日本古典集成など)
編者(伝承):源隆国ら、
出版社:新潮社ほか
特徴とおすすめ理由:小野篁の地獄伝説が収められたオリジナル説話集。現代語訳版や注釈付きで、伝説の真偽や時代背景を深く知りたい人に最適です。
『古今和歌集』(藤原定家筆写本ほか)
編者:紀貫之ほか
出版社:多くの出版社・電子版あり
特徴とおすすめ理由:平安時代の代表的和歌集。小野篁の歌も収録されており、彼の文学的感性に直接触れられる貴重な資料です。
🏯 現地で伝説を追体験
『京都・六道珍皇寺』
場所:京都市東山区松原通大和大路東入ル(六道町)
おすすめポイント:境内に伝わる「冥途通いの井戸」や「黄泉がえりの井戸」は、通常非公開ですが、年に数回行われる特別公開時に拝観可能。
冥界と現世をつなぐとされる雰囲気を実際に体感でき、「地獄伝説」を肌で感じる貴重な場所です。
アクセス:京都駅から市バス206系統で「東山安井」下車、徒歩数分。
拝観情報:年に数回、ウェブ等で特別公開日が告知されます。格子窓越しに井戸をのぞく体験や、閻魔大王・小野篁像の公開もある貴重な機会です。
📚 想像を膨らませる書籍案内
「古典に興味はあるけれど、難しそう…」という方には、町田康さんの軽快な語り口が魅力の『宇治拾遺物語(河出文庫)』がおすすめです。古い説話がまるで絵本のように読みやすく、小野篁のエピソードも親しみやすく味わえます。
本格志向なら、伝説そのものを体験できる『今昔物語集(新潮日本古典集成)』へ。地獄での事件は現代語訳付きで、資料としても充実。さらに、篁の感情に寄り添うなら『古今和歌集』で彼の和歌を原文で味わうのが最適です。
🏯 京都で体感!六道珍皇寺の魅力
京都観光の穴場としても人気の六道珍皇寺。年に数回だけ公開される「冥途通いの井戸」は、本当に地獄へ通じていそうな不思議な雰囲気。格子窓ごしに静かに覗くと、まるで小野篁が夜な夜な通っていたかのよう。そのひんやりとした空気が、伝説にリアリティを与えてくれます。
拝観日には、閻魔大王や篁の像も公開され、地図で辿る“平安時代の京都”を五感で感じられます。歩いたあと、あなたもきっと「本当にあったんだ」と思うはずです。
結びとして
小野篁という人物の生涯をたどることで、私たちは「信念を貫く強さ」や「型にはまらない生き方の価値」を学ぶことができました。
昼は朝廷に仕え、夜は地獄を行き来するという伝説すら生まれた彼の姿は、現代を生きる私たちにも「多様な生き方を恐れない心」と「再起する力」の大切さを教えてくれます。
補足注意
本記事は、筆者が個人で調べられる範囲で、
信頼できる文献や資料をもとに調査した内容に基づいて構成しておりますが、
歴史的事実には諸説が存在し、今後の研究によって新たな解釈が加わる可能性もあります。
どうかこの記事が、皆さまの「もっと知りたい」という気持ちの入り口になれば幸いです。
もしこの物語に心を動かされたなら、どうかここで終わらせずに——
小野篁という只者ではなかった人物の本当の姿を、さらに深い文献や資料の中で探しに行ってみてください。
きっと、あなた自身の中にも“まだ知らない自分”が見つかるはずです。
どうかあなたの人生にも、小野篁のように“昼も夜も輝く”知恵と信念が灯りますように。

最後までお読みいただき、
本当にありがとうございました。







コメント