ーーー如月ウロ 探偵
“ドロボウ”により“存在感”を盗まれてしまった新米刑事の有馬ハル。自分の存在感を盗んだ犯人を他者に伝えようとするも、その手段は自分の存在が物と化すしかないと考え、銃器保管室に入室した有馬ハル。意を決した有馬の前に、座っていたのは如月ウロでした。
驚く有馬に対して、この場所何故如月がいたのかの説明を事細かく話すのではなく、比喩で言ったその言い回しが伊達者だと感じられた言葉でした。
今までの行動や出来事から、有馬という人物像が思考し行動するであろう事を推測していけば導き出される結果である、と。
正しい推測をしていけば、結果として求めていた正解が現れる。
いとも簡単なように語る姿や、さも当たり前だと言わんばかりの言葉に揺るぎない自信が感じられます。
簡単な答え合わせだともいうように如月は話し、その推理を聴けば有馬の向かう場所にたどり着く、という結果に納得は出来ても、その推理をするために必要な情報の取捨選択や筋道を思い描くことは困難であると感じざるを得ません。
さらには有馬が誰にも気づいてもらえずに独りの孤独な世界に失望している状態であり、その世界から抜け出せる可能性を示してくれた、手を差し伸べてくれたという場面が相まり、心に響いた感銘を受けた言葉になりました。
その場面へのまでの話は、新米刑事の有馬ハルが失踪した人物が死体となり突然家の中に現れたという謎の事件を受け持つことから始まります。
そこにはなぞの遺書も壁に書かれており、その文字も死体とともに突然現れたと報告を受けます。
ベテラン刑事はこの事件は“ドロボウ”絡みだと納得する様子ですが、有馬は何を言っているのかが検討もつきません。
困惑している有馬は特別任務としてある人物のところに捜査協力依頼に行くように命じられます。
向かった先の部屋に入ると、床一面に置かれた巨大で真っ白なジグソーパズルを組み立てる人物の姿があります、その人物こそが捜査依頼をする如月ウロでした。
一通り話を聴いたウロは“ドロボウ”の事を端的に説明し、捜査を始めます。
被害者の家族に聞き込みし、如月はある言葉に気が付きます、“壁の落書き”刑事たちが遺書だと言っていたラクガキ、被害者家族は遺体を見つけた後に、いつの間にか書いてあったと証言します。
そのラクガキと証言が参考になったと、如月は聞き込みを終えます。
その後の調査で有馬は、被害者には注射痕が有ったことをが分かります、しかもその痕は献血の痕だとわかります。
真相を求め献血センターへと向かう有馬でしたが、そこではどのような取り調べをすればよいのか途方に暮れ、帰路につきます。
しかし、その道中で有馬は奇妙な出来事に遭遇します。
コンビニに入店しようにも、自動ドアが開かない、レジに品物を持っていっても店員は会計を始めようともしない。他のお客さんからは、有馬がいないかのように扱われてしまう。
すでに有馬は“ドロボウ”に盗まれてしまった後だったのでした。
盗品は存在感というガイネンでした。

存在感をなくした者達は、誰からも気付かれない存在となり、 死体という物になることで、やっと気付かれる存在になるということでした。
気付かれないことに、気が付いた有馬、刑事としてこの事件の真相を犯人を他者に伝えるために、自らの存在を気付かれる状態にすべく行動を起こします。
被害を最小限におさえ、かつ最短で物となった自身が発見されるであろう状況を作り出す為に、必要な行動を考えた有馬。そのように有馬が考え行動するであろうと推理した如月。
その結果二人が出会った場所は、銃器保管室でした。
銃器保管室に入室した有馬に、
如月の言った言葉は
…パズルの素晴らしいところは
周りを正しく埋めれば欠けた部分が見える点だ
漫画 概念ドロボウ 第1巻 第1幕 タンテイトデカ より引用
でした。

有馬の求めた疑問を正確に答える言葉では無かったかも知れませんが、誰にも気が付かれないという絶望の中でこれほど救われた、と思える瞬間はなかったのでは無いでしょうか。
そのような場面で、ダラダラと経緯を話されるよりも、如月のような簡潔な言葉を聴くことが、心から頼もしいと感じられるのではないでしょうか?
勿論その後に如月は、きちんとどの様な思考を持ってこの場所にたどり着いたのかを有馬に説明してくれますが。
ただの説明ではなく、自分の思考をパズルに例えて説明する、しかもその説明する場面が、救いを必要とする者の前だった、という事が相乗効果となり絶好の、心に響く感銘を受けた言葉となりました。
理路整然と出来事を整理し、結果に至り着く。そこからの決め台詞。
どちらの要素も一筋縄では行えないだと感じられました。
この様な如月と有馬のやり取りを
直接読みたい場合は
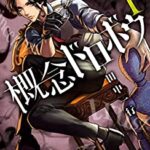
概念ドロボウ 田中一行 アフタヌーンKC 講談社
第1巻 第1幕 タンテイトデカ
を、是非読んでみてください。
皆様にはどの様な新しい響きがあるのか楽しみです。
存在として気付かれない、その事が意識を必要とする生物だけではなく、自動ドアというセンサー等で物理で気に存在を感知する機会にまで影響を与えてしまう、存在感を盗むドロボウ、恐るべしですね。
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました。




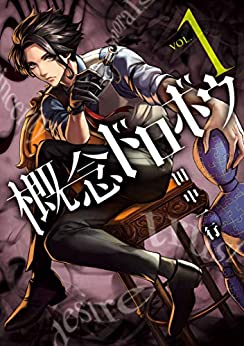
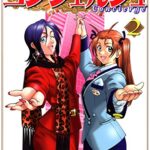
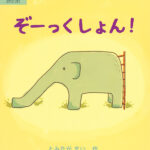
コメント