ーーー瀬戸慎吾 14歳
ダーツプレイヤーである烏丸徨はダーツバーで、とある人物と一緒に来店しています。
その人物のみがダーツに興じており烏丸は座ったまま、求められればアドバイスを返す程度。
しびれを切らして、聞きたいことは何かと問います、冗談でダーツのコツとかか?と問うと、ダーツ賭博の元締めでもある絹守 一馬(きぬもり かずま)は、ダーツなんてくだらない、20点にあたらないしと冗談とも取れる返しをし、烏丸を焦らせます。
そこで本題に入る絹守、とあるカードを差し出します、キャッシュカードのような見た目のカード、表には大きく“A”印字されているカード。何の変哲もないこのカードを見せられた烏丸は、先程の穏やかな雰囲気はどこへやら、真剣かつ冷酷そうな表情で、無駄口は叩かず質問に答えてくれ、誰に渡された?名前を教えろと問います。
そのカードから回想は始まります、10年前の山奥に建てられた施設にある一室、朝の挨拶とともにアナウンスがが長々と語られます、そのアナウンスを目覚ましに14歳の烏丸は目覚めます、“A”と印字されたカードを片手に。4年間毎朝毎朝と言う烏丸が正しいのならば、現在の烏丸は24歳であり、この施設に連れてこられたのか自主的に来たのかは定かではありませんが、この時点での烏丸は10歳、だとすれば小学4年もしくは小学5年でこの施設に来ており中学生辺りの年代までをこの施設で過ごしたということになります。
自主的か強制的かである程度は変わるかもしれませんが、そのような若い頃から一人暮らしを強いられ、暮らし続けながらも、今に至るような斜に構えた性格でいられるのもある意味凄いことなのかもしれませんね、もしくはこのような施設でゴールデンエイジと呼ばれる時期を過ごしたのであのような性格になってしまったのでしょうか、それともまったく関係ない?
ともあれこのような辺鄙な施設で4年も過ごすなんて、自分ならばよっぽどの熱意か強制でもなければ断りたい気持ちでいっぱいです。
それでも朝が来れば、ジャージに着替えて部屋を出る、向かった先はロビーそこでは大量のダーツマシンが並んでおり、それよりも更に大量な人達が淡々とダーツを行っています。
満員だったので、空いているダーツマシンを探している烏丸に声をかけてきたのが、同じく14歳の桂木鈴音でした。軽口をたたき合えるような仲の二人暫く話していると、そこに現れたのは“B”のカードを見せながら涙するこれまた14歳の瀬戸慎吾でした。
14歳の三人組これは、施設側はあえて14歳辺りのゴールデンエイジの時期の子供を施設に暮らさせていると考えるのが理にかなっているのかもしれません。
ゴールデンエイジ呼ばれる年頃の男女ならば一心不乱にダーツに取り組めばとんでもな腕前になるということを狙って集めたと考えても不思議ではありません。それほどまでに奇妙な程ダーツも実力で全ての優劣が定められてしまう制度、教官の態度は勿論のこと、着るものや、食事、住居のランクまでもが、“A“”B”“C”と明確なランク分けがされているほどでした。
そんな施設で“A”を取り続ける二人それを眺める瀬戸、どこで差がついたのかと考えます、勿論今回のダーツも5ゲーム行い平均1440点で勿論ランクAに留まる二人それを眺めた周囲の人達、奴らは凄い、天才だ別ものだと、褒め、たたえ、天才だ別ものだと囃し立てます、諦めを含みつつ。
それを聞いていた瀬戸は
『…“天才”ねぇ… ……
…同じ時間おなじことをやって 差がついているんだ
オレ達がダメダメなだけじゃないの…?』
漫画 エンバンメイズ 第1巻 ROUND 04 誕生~early days~〈前編〉 より引用
と思考します。
二人を認めながらも、自己を自虐的に評価する瀬戸、時間の使い方が上手だったのか、もとからの素質なのか?
上手な人をみて天才だと考えてしまえば、自分とは持っているものが違う、才能が違うのだ、だからこのような結果になるのは仕方がないと考えるのがてっとりばやくかつ区合理的なのかもしれません、自己の成長を止めてしまうことに目をつぶって、しまえば。
思考を止め、出来るのは天才だから、出来ない自分は才能がない、凡人だから出来なくても当たり前なので、自分は悪くないと考え思い込めばどれ程楽なことなのだろうか。
たとえ天才と呼ばれる者の、努力や苦労が凄まじくても。
才能がないと諦め立ち尽くす者の努力の量、上達するために必要な方法またその種目を考察する努力が少なかった足りなかったとしても。
才能その言葉で片付けてしまえば、楽であり傷つくことを回避できる。
そんな周囲の言葉を察したかのように発せられた、瀬尾の言葉。
少しひねくれながらも
逃げ出さず、諦めず、相手を認めそして自分の行動にも向き合ってこそ、出てきた言葉ではないか、自分も出来ないことを才能という言葉で簡単に置き換えているのではないか、本当に才能の差でしか判断できないほどにその事に向き合ったのか、努力し続けたのだろうかと自己に問いかけなければ、自分もそして結果を出している者にも失礼なのではないかと、考えるきっけとなった心に響いた感銘を受けたでした。
まあ、それでも圧倒的に差のある事象というのは、本当に稀なようで、どこにでもどの業種にでもいるのも事実なのではないでしょうか、事実だと思いたいとも考えます。
皆様がこのような思考になった瀬戸に対してどう思うのか
直接考察してみたい場合は
エンバンメイズ 田中一行 good!AFTERNOON KC 講談社
第1巻 ROUND 04 誕生ーearly daysー〈前編〉
を是非読んでみたください、皆様にはどのような新しい響きがあるのか楽しみです。




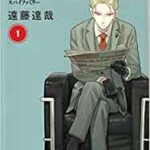

コメント