『待つのが祭り』とは?旅行前夜やイベントを待つ時間が一番楽しい理由を解説
旅行の前夜、
遠足のカバンを詰めている時間のほうがワクワクする。
当日はもちろん楽しいけれど、
気づけば一日はあっという間に過ぎてしまう。
――そんな“不思議な体験”に、
昔から名前がついていることをご存じですか?
このようなことはありませんか?
新しいスマホを注文したあと、届くまでの数日間がやたらと楽しい。
大好きなアーティストのライブ前、曲を聴きながら待っている時間が一番ドキドキする。
レストランで料理を待つとき、想像だけでお腹も心も満たされる気がする。
運動会や文化祭の準備期間、当日より前のワクワク感が強く残っている。
こうした“待っている時間の不思議な楽しさ”は、
誰もが一度は感じたことがあるはずです。
読むメリット
この記事を読むと――
毎日のストレスをちょっと減らし、
待ち時間をポジティブに楽しむコツが分かります。
昔から言い伝えられてきたことわざの意味を知り、
日本語の奥深さにも触れられます。
心理学の研究に基づいた
「なぜワクワクするのか?」の理由を理解できます。
疑問が生まれた物語
日曜日の夜。
月曜からの修学旅行を控えた小学生のユウくん。
持ち物をひとつひとつチェックしながら、
「明日のホテルの朝ごはんは何かな」
「友だちと同じ部屋だったらいいな」
「バスの座席はどこになるんだろう」
想像するだけで胸が高鳴って、
ニコニコが止まりません。
そして当日。
観光もごはんも最高に楽しいけれど――
一日は矢のように過ぎていきます。
帰りのバスでふと思うのです。
「昨日までの準備していた時間、
あれが一番楽しかったかも」。
心の声ブロック
なんで?
準備してるだけなのに、どうしてあんなにワクワクするんだろう。
映画だって、始まる前の予告編のほうが楽しいときがあるのはなぜ?
風船がふくらむように、
期待が大きくなるほど心もふくらんでいく。

――この“ふくらむ時間”の正体、
もっと知りたくなってきませんか?
次への誘い
この不思議な感覚には、
昔の人がぴったりの名前をつけています。
余韻に残るその言葉を、
心理学やことわざの由来とあわせて探っていきましょう。
さあ、さらに学んでいきましょう。
すぐに分かる結論
お答えします。
この不思議な感覚には、
昔からことわざで名前がつけられています。
それが――
「待つのが祭り」
という言葉です。
「待つのが祭り」とは、物事は“待っているあいだ”が一番楽しいという意味のことわざです。
同じ意味で使われる定番の表現に「待つ間が花」や「見ぬが花」**があります。
意味をひとことで
お祭りそのものよりも、
「お祭りを待っている時間」が
いちばんワクワクして楽しい。
そうした体験を表すのが
「待つのが祭り」ということわざです。。
次への誘い
言葉の響きどおり、
待っている時間がまるで祭りのように心を躍らせます。
――では、どうして人は待っている間に
こんなにワクワクしてしまうのでしょうか?
👉 まるでお祭り前夜のように、
待っている時間そのものが心を躍らせる――
この感覚の正体を知れば、
“待ち時間”がもっと豊かに変わります。
それでは、ことわざの由来や心理学の視点から、
「待つのが祭り」の奥深さを一緒に探っていきましょう。
『待つのが祭り』とは?
――待っている時間がいちばん楽しい不思議
定義
「待つのが祭り」とは、
本番そのものより“待っている間”がいちばん楽しい
という意味のことわざです。
たとえば、
「待つ間が花(まつまがはな)」
「見ぬが花(みぬがはな)」
「祭りより前の日」
といった似た表現もあります。
どれも「待っている時間の楽しさ」を表す言葉です。
表記と由来
口語では「待つのが祭り」とよく言われますが、
辞書には「待つ間が花」という形で載っています。
「花」という言葉には
“一番よい時・盛り”という意味があります。
だからこそ、
「待っている間こそ花」と
昔の人は表現したのです。
この感覚は江戸時代の本にも出ていて、
庶民の生活の中から自然に広まっていったもの。
誰か特定の人が作ったわけではありません。
なぜ注目されるのか?
心理学の研究が裏づける『待つのが祭り』
旅行やライブの予定を考えるだけで、
つい笑顔になってしまう。
この“不思議な感覚”は、
心理学の研究によって裏づけられています。
アメリカの研究(Kumar ほか, 2014)
アメリカの心理学者 クマール、キリングスワース、ギロヴィッチ は
2014年に有名な研究を発表しました。
論文タイトルは――
“Waiting for Merlot: Anticipatory Consumption of Experiential and Material Purchases”
(ウェイティング・フォー・メルロー:アンティシパトリー・コンサンプション・オブ・エクスペリエンシャル・アンド・マテリアル・パーチェスズ)
日本語にすると、
「メルローを待ちながら ― 体験購入と物品購入における待ち時間の違い」。
研究の目的
「体験を買うとき」と「モノを買うとき」で、
待ち時間の気分や幸福感に違いはあるのか?
これを確かめるのが研究の目的でした。
方法と結果
研究1:アンケート調査
大学生に近々予定している「体験」と「モノ」を思い出してもらい、
そのときの気分を測定。
👉 体験を待つ方がワクワク感が強い。
研究2:日常の追跡調査
スマホ通知を使って「今、何を待っているか」を記録。
👉 体験を待っているときの方が幸福度が高い。
研究3:ニュース記事の分析
行列に並ぶ人たちの記事を比較。
👉 体験チケットを待つ人の方が楽しそうに描かれていた。
研究4:追加検証
収入や趣味などの影響を取り除いても結果は安定。
結論はシンプルです。
👉 体験を待つ時間は、モノを待つ時間より楽しい。
セイヴァリング(savoring)という力
心理学では、
ポジティブな感情を意識して味わう力を
セイヴァリング(セイヴァリング)と呼びます。
未来を味わう(anticipation/アンティシペーション)
今を味わう
過去を思い出して味わう
この3つがあり、
「待つのが祭り」はまさに
未来を味わう楽しみの典型例なのです。
記憶のクセもひと役
人には2つの特徴があります。
ロージー・レトロスペクション
(rosy retrospection)=過去を実際より良く思い出すクセ
ピーク・エンド則
(peak–end rule)=体験は“山場と終わり”で評価されやすい
これらが重なることで、
「待っていた時間が一番楽しかった」と
感じやすくなります。
脳の働きから見ても
人の脳には、
「これから得られるごほうび」を先取りして楽しむ仕組みがあります。
特に大切なのが、
辺縁系(へんえんけい) と 前頭前野(ぜんとうぜんや) です。
辺縁系(へんえんけい)とは?
脳の奥深くにあり、
感情や欲求、記憶の働きに関わる部分です。
「楽しそう!」「うれしい!」といった感情を生み出すのもこの領域。
ごほうびを予測したとき、ドーパミンという神経伝達物質が働き、
「待つ楽しみ」を感じさせてくれます。
前頭前野(ぜんとうぜんや)とは?
脳の前方にある領域で、
計画、判断、注意、衝動のコントロールを担います。
たとえば「明日の旅行の準備をしよう」
「待っている時間を楽しもう」と考えるのは前頭前野の働きです。
理性と計画性をつかさどることで、
ワクワク感を安全に“長持ちさせる”役割を果たします。
2つの連携
辺縁系が「ワクワク!」という感情を生み出し、
前頭前野がそれを整理して「どう楽しむか」を考える。
この2つがバランスよく働くことで、
ワクワクを“少しずつ小分け”にして味わうことができるのです。
👉 だからこそ、予定を少しずつ思い描いたり、
友人と共有したりすることで「待つ時間」をもっと豊かにできるのです
まとめ
つまり――
「待つのが祭り」はことわざだけでなく、心理学的にも正しい
待ち時間をどう味わうかが、幸福感を大きく左右する
次は、この知恵を日常生活でどう生かすかを見ていきましょう。
👉 「待ち時間を楽しみに変えるコツ」をご紹介します。
実生活への応用例
――今日からできる、“待つ時間を楽しさに変えるコツ”
ミニ予定をカレンダーに散らす
旅行や誕生日など大きなイベントだけでなく、
週1回の「ご褒美ランチ」や「銭湯」「映画ナイト」など、
小さな予定をカレンダーに入れてみましょう。
研究でも、モノを待つより体験を待つ方が、
ずっとワクワクしやすいことが分かっています。
準備そのものをイベント化する
旅行前の持ち物チェックを家族でゲームにしたり、
旅先のプレイリストを作ったり。
「準備=面倒」ではなく、
「準備=お祭り前夜」ととらえると、
毎日の満足度がぐんと高まります。
これは心理学でいう セイヴァリング(savoring/セイヴァリング)。
ポジティブな気持ちを意識して味わう力です。
誰かと共有して二度おいしい
「ここ行きたい!」「これ食べたい!」を、
友だちや家族と送り合ってみましょう。
良い出来事を共有することで、
期待感は倍になり、絆も深まります。
心理学ではこの効果を
キャピタライゼーション(capitalization)と呼びます。
終わりに小さな“余韻”を残す
体験の最後に写真を見返したり、
一言メモを残したりするだけで、
満足度はさらに高まります。
これは ピーク・エンド則(peak–end rule/ピーク・エンド)。
人は「山場」と「終わり」の印象で、
体験全体を評価しやすいのです。
💡 たとえるなら、風船はふくらむ過程が一番ドキドキ。
体験も同じで、「ふくらませ方」を工夫すれば、
日常がもっと軽やかに変わります。
注意点や誤解されがちな点
――正しく理解すれば、もっと心地よい“待ち時間”に
「現実がつまらない」という意味ではない
「待つのが祭り」は、
待っている時間の楽しさを表すことわざです。
決して「当日がつまらない」という否定ではありません。
辞書でも「待つ間が一番楽しいことが多い」と説明されています。
期待をふくらませすぎない
期待が大きすぎると、
「思ったほどじゃなかった」と落ち込むこともあります。
対処のコツは3つ。
小さな予定を複数つくる(ひとつに賭けない)
情報は小出しにして楽しむ
最後に小さな儀式で満足を閉じる
これで期待と現実のギャップをやわらげられます。
共有が逆効果になることもある
誰かに楽しみを話すとき、
相手が素っ気ない反応をすると気持ちはしぼんでしまいます。
だから、反応が前向きな人や場面を選んで、
「楽しみを共有する」ようにしましょう。
似た言葉との混同に注意
「待つのが祭り」と似た響きのことわざに
「後の祭り」があります。
これは「手遅れ」という全く別の意味。
混同しないように気をつけてください。
注意点のまとめ
「待つのが祭り」を上手に活かすコツは、
小さな予定をつくる
準備も楽しむ
誰かと共有する
最後に余韻を残す
この4つです。
うまく取り入れれば、
毎日の待ち時間が“前夜祭”に変わり、
人生がもっと彩り豊かになります。
👉 次は、「おまけコラム」として
ことわざの関連表現や、
ちょっと違った視点からの楽しみ方を紹介していきましょう。
おまけコラム
――言葉の世界をもう一歩
「待つのが祭り」と似たことわざは、実はたくさんあります。
待つ間が花(まつまがはな)
待っているあいだがいちばん楽しい、という表現。辞書にも定番で載っています。ニュアンスとしては「待つのが祭り」とほぼ同義。
祭りより前の日
地域のことばとして伝わる表現で、「当日より前日のワクワク感」を強調しています。日本各地の民俗行事の感覚に根ざしています。
成らぬうちが楽しみ
「物事は完成する前がいちばん楽しい」という意味。待つ時間だけでなく、未完成の状態をポジティブにとらえています。
見ぬが花(みぬがはな)
実際に見るより、想像しているときが美しいという意味。待つ時間のワクワク感よりも、想像力の美しさに重きがあります。
言葉の違いと地域の感じ方
「待つのが祭り」「待つ間が花」は、生活に根ざした口語的な言い回し。特にお祭り文化のある地域で自然に広まったと考えられます。
「見ぬが花」は、古典文学にも登場するやや雅な表現。芸術や美意識に近い世界観を表します。
「成らぬうちが楽しみ」は、職人文化や農耕生活とも重なり、結果より過程を楽しむ感覚がにじんでいます。
つまり「待つのが祭り」は、もっとも庶民的で生活感のある表現。
一方で「見ぬが花」などは、文化や美学の視点から表した言葉といえます。
まとめ・考察
「待つのが祭り」とは――
待っている時間がいちばん楽しいということわざです。
心理学でも、
体験を待つ時間の快さ(Kumar ほか, 2014)
セイヴァリング(味わう力)
ピーク・エンド則
といった研究によって裏づけられています。
考察
人は未来に物語を編む動物です。
「待つ時間」を先取りして味わう力は、文化やことわざに刻まれ、時代を超えて語り継がれてきました。
予定表は、家庭のなかの“神輿(みこし)”です。
担ぐ前から「今日はどんなふうに楽しもう?」と家族や仲間でワクワクを回覧すれば、日常がちょっとしたお祭りに変わります。
あなたへの問いかけ
このような体験談、ありませんか?
「“祭り前”を意識して暮らしたら、毎週が少し楽になった」――
そんな小さな実践の積み重ねが、日常の幸福度を底上げしてくれます。
👉 あなたなら、この感覚をどう活かしますか?
更に学びたい人へ
おすすめ書籍のご案内
心理学や「待つのが祭り」の感覚をより深く学びたい方に向けての書籍を“初学者向け”と“全体おすすめ”でご紹介します。
初学者向け:『図解 心理学用語大全』
著者 / 監修:田中 正人(著)/齊藤 勇(監修)
— 田中氏はビジュアル重視の編集者兼著者、齊藤氏は対人・社会心理学の専門家で心理学普及に尽力した福祉・心理学の大家です。
出版社:誠文堂新光社—
約100人の心理学者と150以上の用語を図解で解説し、心の仕組みが“つながって見える”ユニークな構成です。
おすすめ理由:ビジュアル中心でわかりやすく、60分で心理学の基礎を整理できます。
日常語で使われる心理用語の理解をスッと吸収できる入門書です。
全体におすすめ:『嫌われる勇気』
著者:岸見 一郎・古賀 史健
— 岸見氏はアドラー心理学の第一人者で、多くの著作圏を持つ哲学者。古賀氏はベストセラー作家として知られます。
出版社:ダイヤモンド社
本の特徴とおすすめ理由:哲学者と青年の対話形式で、アドラー心理学の核心を日常会話のように理解できます。
「悩みは対人関係にある」というアドラーのメッセージが、悩みを抱える人に勇気と希望を与えます。
両書とも「待つのが祭り」に関連する概念を深める上で、とても役立ちます。
まずは『図解 心理学用語大全』で、心の仕組みを視覚的に整理し、
次に『嫌われる勇気』で、心のあり方を実践的・哲学的に学ぶ流れが自然です。
疑問の解決した物語
バスの窓にもたれながら、ユウくんはふと先生の言葉を思い出しました。
「楽しいのは本番だけじゃないんだよ。
待っている時間そのものが祭りなんだ」
――そうか。
昨日のワクワクは、昔から「待つのが祭り」という言葉で語られていたんだ。
ユウくんの胸の中に、すとんと答えが落ちます。
持ち物を準備していた時間。
「どんな部屋になるかな」と友だちと話した時間。
その全部が、修学旅行という祭りを彩る
大切なひとコマだったのです。
笑顔で外を眺めながら、ユウくんは心の中でつぶやきました。
「また次のお祭りを楽しみに待とう」
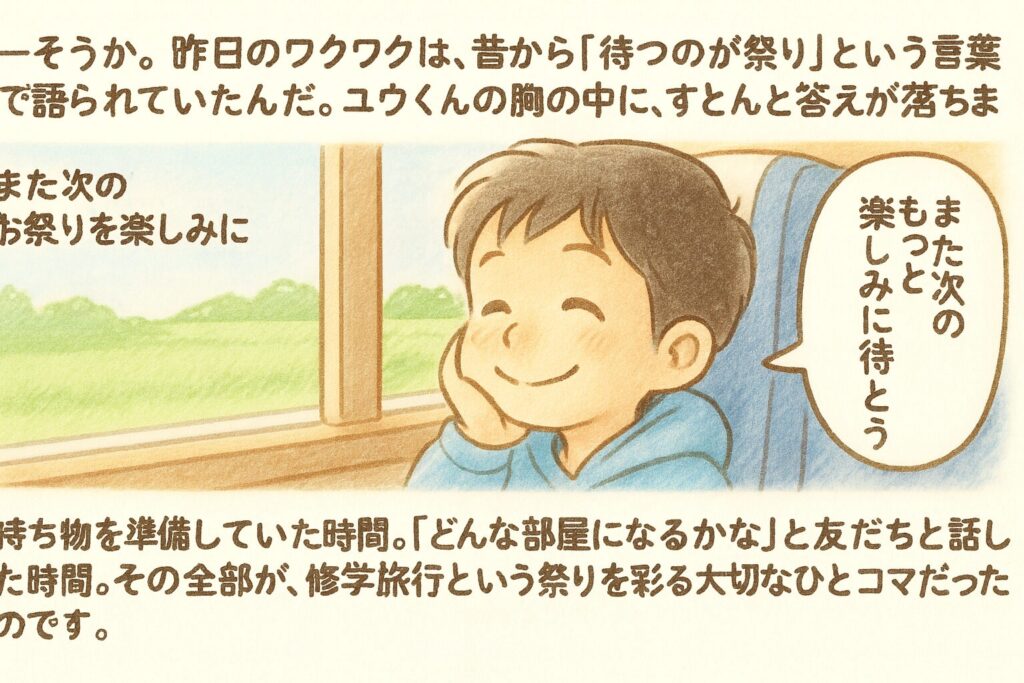
その気づきをどう活かすか
ユウくんは思いました。
「待っている時間が祭りみたいに楽しいと知ったら、
次はもっと準備を楽しもう」
予定をカレンダーに書き込むだけでもワクワクできる。
「これやりたいね」と友だちと話すだけでも胸が弾む。
そう考えると、修学旅行のような大きなイベントだけでなく、
日常のちょっとした予定も“祭り前夜”になることに気づきました。
「これからは、待つ時間も宝物のように味わっていこう」
そう心に決めたユウくんは、
次に待つ小さな楽しみを探しながら、
笑顔でバスの窓の外を見つめ続けました。
ブログの締め
私たちは誰しも、旅行の前夜やイベントを心待ちにする時間に、特別なときめきを感じます。
その感覚に昔の人が名づけたのが「待つのが祭り」。
心理学の研究やことわざの知恵を通して見えてきたのは、
「待つ時間をどう味わうかで、日常の豊かさは大きく変わる」ということです。
小さな予定を散りばめること、準備を楽しむこと、仲間と共有すること――。
どれもすぐに始められる工夫ばかりです。
今日のあなたのカレンダーにも、
ひとつ“前夜祭”を灯してみてください。
注意補足
📝 本記事の内容は、筆者が信頼できる情報源を調べた範囲でまとめたものです。
他の見方や新しい研究が出る可能性もあります。
「待つのが祭り」という言葉を入り口に、ぜひあなた自身でも探求を続けてみてください。
もし今日の記事で少しでも心が弾んだなら、
次はぜひ文献や資料の世界へ――
“待つ時間こそ祭り”の余韻を抱きながら、さらに深く探る旅に出てみてください。
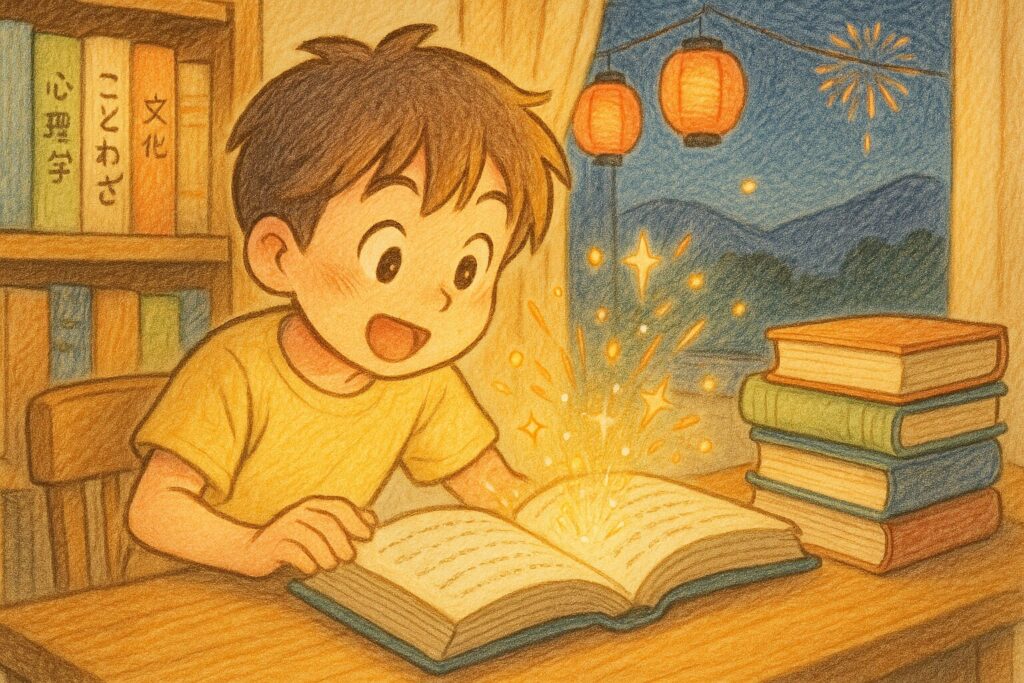
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました。
どうぞこれからの日々も、“待つ時間こそが小さなお祭り”として楽しんでみてください。







コメント