 絵本
絵本 つちって せんを かいたり けしたり あなを ほったり、 やまを つくったりもできる。
トマトの苗を育てたたいのに、土がなかったために、様々な場所で土を探す女の子、その途中で、土の用途に気がついた時の言葉です。
 絵本
絵本  絵本
絵本 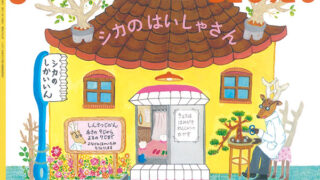 絵本
絵本 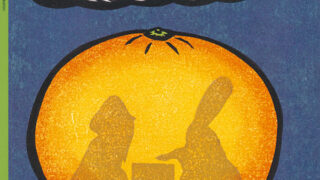 絵本
絵本  絵本
絵本 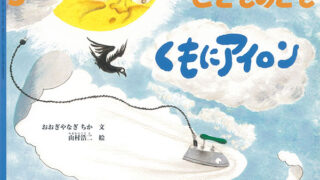 絵本
絵本  絵本
絵本 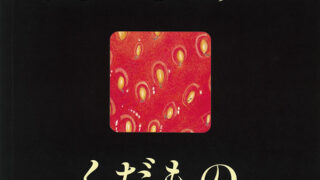 絵本
絵本 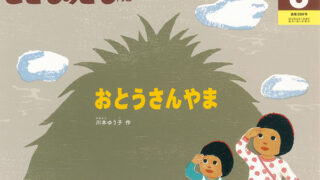 絵本
絵本 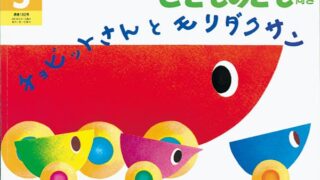 絵本
絵本