『アンカリング効果』とは?最初の情報があなたの判断を左右する心理トリック
「お得に感じたのは、気のせい?」実はそれ、心理のワナかもしれません。
中学2年のレンくんは、母親とショッピングモールにいました。
お目当ては、以前から欲しかったBluetoothイヤホン。
店頭で見つけたとき、ポップにはこう書いてありました。
「通常価格:12,000円 → 本日限定:6,800円」
レンくんは思わず口にします。
「うわっ、半額近いじゃん!これ買っていい?」
しかし家に帰ってネットを調べてみると、
なんとその商品は、普段から6,800円前後で売られていたのです。
「え、じゃあさっきのお得感って…なに?」
実は、これこそが『アンカリング効果』と呼ばれる心理的現象の影響なんです。
🎯 記事を読むとわかること
- アンカリング効果って何か、具体的に理解できる
- 買い物や人間関係で使われるテクニックがわかる
- 自分がだまされないための「思考の武器」が手に入る
- 心理学の面白さを体感できる
✅ すぐに分かる結論
『アンカリング効果』は“最初の情報”があなたを操る!
『アンカリング効果』とは、
最初に見たり聞いたりした数値や情報が、後の判断に強い影響を与える心理現象のことです。
たとえば、中学生のレンくんがイヤホンを見ていたとき、
まず目に入ったのは「12,000円」という定価。
そのあとに「6,800円」という値下げ後の価格を見たとき、
レンくんの頭の中では、自然と “比べる基準” が12,000円になってしまったのです。
だから、「6,800円って安いじゃん!」と感じてしまった。
この心理がまさに、アンカリング効果です。
⚓「基準のいかり」ってどういう意味?
「いかり(アンカー)」とは、船が海にとどまるために下ろす重りのこと。
アンカリング効果では、この“いかり”があなたの心に最初に下ろされた情報になります。
つまり、最初に受け取った情報が心の中に固定されてしまい、
それ以降の判断がその場所から動きにくくなるということなんです。
たとえば、こんなふうにイメージしてみてください
あなたが誰かに「その本、2,000円くらいかな」と聞いたあと、
実際の値段が1,500円だと、「お、意外と安い」と感じる。
でも先に「1,000円くらいかな?」と思っていたら、「ちょっと高いな」と感じるはずです。
どちらも同じ「1,500円」なのに、“最初の情報”によって見え方が変わってしまう。
これが、「基準のいかり」の力です。
このように、私たちの判断は「事実そのもの」よりも、
その前に与えられた“基準”に左右されていることが多いのです。
だからこそ、アンカリング効果を知っておくことは、
だまされないためにも、うまく使うためにも、とても大切なんですね。
アンカリング効果とは?
📌 定義
アンカリング効果とは、
「最初に接した情報」が心の中に“基準”として固定されてしまい、
その後の判断や意思決定がその基準に大きく引きずられてしまう心理現象のことです。
たとえば、値札に「定価:15,000円」と書かれた商品が「今だけ7,800円」と表示されていたとします。
実際にその商品が本当に7,800円の価値なのかは分からなくても、
最初の15,000円という情報に影響を受け、「安い」と感じてしまう。
このように、人間の思考は「冷静に比べているようで、最初の印象に縛られてしまう」ものなのです。
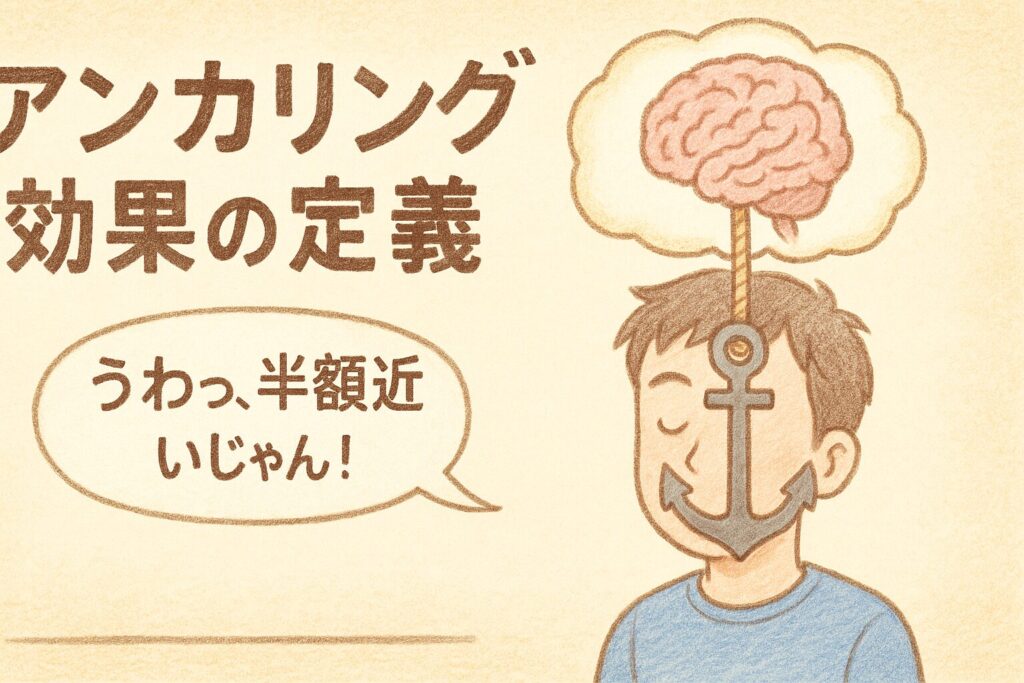
⛵ 名前の由来
「心に下ろされた、見えない“いかり”」
「アンカー(Anchor)」とは、船が海にとどまるために海底へ下ろす“いかり”のことです。
一度いかりを下ろすと、船は大きく動けなくなります。
これと同じように、私たちの判断も、最初に与えられた情報に縛られてしまうのです。
この「心理的いかり」が下ろされることで、
本来はもっと広く見渡せるはずの判断範囲が、無意識に限定されてしまうのです。
🧠 発見した人物
人間の“非合理”に挑んだ二人の心理学者
アンカリング効果を発見したのは、
心理学者のダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーです。
彼らは1970年代、人間が直面する「不確実な状況下での判断」に注目し、
「人間の意思決定は、合理的ではなく“バイアス(思い込み)”に左右されることが多い」
という仮説のもと、数々の実験を重ねました。
この研究分野は「行動経済学」と呼ばれ、
当時の経済学が前提としていた「人は常に合理的に行動する」という常識を覆したのです。
🏅 ノーベル賞に輝いた「人間の不完全さ」を見つめる視点
この研究成果を受けて、ダニエル・カーネマンは2002年にノーベル経済学賞を受賞しました。
彼の著書『ファスト&スロー』では、
人間の思考がどのように「早いけれど間違いやすい思考(システム1)」と、
「遅くて慎重だけれどエネルギーを使う思考(システム2)」の二重構造を持っているかが、詳しく解説されています。
アンカリング効果は、この「システム1(直感的・無意識的な思考)」に潜む盲点の代表例なのです。
なぜアンカリング効果が注目されるのか?
🌍 情報社会における「判断の省エネ装置」
スマホを開けば、1日に何百という情報が流れ込んできます。
この情報過多の時代に、人間はすべての情報をいちいち分析していられません。
そこで、**「最初に見た情報を“基準”として採用する」という脳のショートカット(ヒューリスティック)**が働きます。
この思考の省エネ化が、便利である一方で、
私たちを誤解や誘導に巻き込むきっかけにもなってしまうのです。
🎲 実際に行われた有名な実験例【ダン・アリエリーの研究】
行動経済学者のダン・アリエリーが行った実験をご紹介します。
📊 実験の内容
ある大学の学生に、次のようなアンケートを行いました。
- 最初に、自分の学生番号の末尾の2桁(たとえば「87」など)を紙に書かせる
- 次に「このボトルワインにいくら払いますか?」と質問する
ここで重要なのは、学生番号の数字とワインの価値はまったく関係ないという点です。
💡 結果
- 学生番号の末尾が「90」に近い学生は、平均して高い価格を提示
- 学生番号の末尾が「10」に近い学生は、低い価格を提示
つまり、まったく関係のない数字にさえも、
人間の判断が引きずられてしまうということが証明されたのです。
🧩 結論:私たちは「意味のない情報」さえ基準にしてしまう
この実験は、アンカリング効果が「意味ある情報だけではなく、無意味な数字にも影響される」ことを示しました。
つまり、**私たちの判断は驚くほど簡単に“方向づけられてしまう”**ということです。
ニュースの見出し、SNSで流れる価格、セール情報――
それらすべてが、私たちの心に見えない“いかり”を下ろしているかもしれません。
🧑🔬 ダン・アリエリーとは?
「予想どおりに不合理」な人間を愛した研究者
今回ご紹介した実験を行ったのは、
行動経済学者のダン・アリエリー(Dan Ariely)氏です。
彼はイスラエル出身の心理学者・経済学者で、
人間が非合理な行動を取るメカニズムをユニークな視点から研究しています。
アリエリー氏の研究の特徴は、実験がとても身近でリアルであること。
ショッピング、恋愛、健康、意思決定など、
日常の中で誰もが感じたことのある「なぜかそうしてしまう」を、科学的に解き明かします。
彼の代表作『予想どおりに不合理(Predictably Irrational)』は世界的ベストセラーとなり、
「人は合理的に行動する」という従来の経済理論に対して、
**「人は、驚くほど一貫して不合理である」**という現実を突きつけました。
🤝 カーネマン&トヴェルスキーとの関係性は?
ダン・アリエリー氏は、ダニエル・カーネマンとエイモス・トヴェルスキーの研究を土台に、
行動経済学をさらに発展・応用した後続世代の研究者です。
直接の弟子ではありませんが、
カーネマンたちが確立した「人間の非合理性」に関する理論をベースに、
アリエリー氏はより実践的で現代社会に根差した研究を行っています。
つまり、こう言えます。
カーネマンとトヴェルスキーが“理論の骨組み”を作ったのに対し、
ダン・アリエリーはその骨組みに“日常の皮膚感覚”を与えた人物。
日常の皮膚感覚とは、
「理屈ではなく、普段の生活の中で“なんとなく感じていること”や“実際に肌で感じるような現実的な感覚”」のことを指します。
日常生活への応用例
アンカリング効果はこんなに身近
アンカリング効果は、専門的な交渉の場だけではなく、
実は私たちの日常の中でも頻繁に起きている心理現象です。
ここでは、よくあるシーンごとに具体的にご紹介します。
🛒 買い物にて:数字マジックにご用心
ある日、あなたが家電量販店でドライヤーを探していたとしましょう。
1台目は「定価12,000円 → 今だけ6,800円!」というポップ付き。
2台目は、最初から「6,800円」とだけ書かれていました。
よく考えれば、どちらも同じ価格です。
でも不思議なことに、**1台目の方が“お得感がある”**と感じませんか?
これは、最初に「12,000円」という高いアンカーが示されたため、
その後の6,800円が相対的に「安く見える」構造が働いているのです。
📍日常の「買い物アンカー」あるある
- スーパーの「◯%オフ」シール
- 通販の「限定価格!通常価格の半額!」
- 福袋やセット商品の「合計金額は◯円分!」という表記
すべて、最初に大きな数字を見せて、実際の価格が魅力的に見えるように設計されています。
💬 交渉にて:印象の主導権を握るために
アンカリング効果は、人と人との交渉ややりとりにも大きく影響します。
たとえば、あなたがフリマアプリで商品を出品しているとしましょう。
「希望価格は5,000円」と書いた商品に対して、買い手からこうメッセージが来たらどう思いますか?
「いきなり失礼ですが、2,000円でお願いできませんか?」
最初は驚いてしまうかもしれません。
でも、次に「では3,800円ではどうでしょう?」と提示されると、
さっきより高いにもかかわらず、“少し譲ってくれた”ように感じてしまうのです。
このように、最初にあえて“極端な条件”を出すことで、
次の提案が受け入れやすくなるという効果は、営業やプレゼンの現場でもよく使われています。
🧠 自己管理・習慣化にも使える!小さなアンカーの力
意外かもしれませんが、アンカリング効果は自分自身の行動にも活かせます。
たとえば、毎日の勉強習慣に取り組もうとするとき――
「今日は3時間勉強しよう」と目標を立てると、
気が重くなり、最初の一歩がなかなか踏み出せないことがあります。
そんなときは、「まず10分だけ勉強しよう」と決めてみてください。
最初に“小さなハードル(アンカー)”を設けることで、
気持ちが楽になり、実際には30分以上取り組めた…なんてことも珍しくありません。
このように、アンカリング効果をポジティブな方向に使うことも十分に可能なのです。
🛠 活用のコツまとめ:自分を守り、賢く動かすために
以下のような意識を持つことで、アンカリング効果を日常に取り入れやすくなります。
- ✔ 最初に見る数字は「ただのスタート地点」と考える
- ✔ 判断前に「他の選択肢は?」と問いかけてみる
- ✔ 感情ではなく「数字の根拠」を確認する癖をつける
- ✔ 一つの基準に縛られず、第二・第三の比較材料を持つ
- ✔ 調べる・比べる・考えるを面倒くさがらない

注意点や誤解されがちな点
使い方を間違えると逆効果
アンカリング効果は非常に強力な心理ツールです。
しかし、使い方を誤ると、信頼や関係性を損なうリスクもあります。
🚫 アンカリング=相手を操作する手口?いいえ、違います。
「最初に高い数字を見せれば、なんでも安く見せられる」
「極端な条件を出せば、交渉で得できる」
そう考えると、アンカリング効果は「人をコントロールするための技術」にも見えてしまいます。
ですが本来、アンカリングは**「人間の認知のクセを知る」ためのもの**であって、
相手をだます手段ではありません。
もしこの効果を**“自分の都合だけ”で使いすぎれば、
「なんかあの人、ずるいな…」という印象を与えかねません。**
それは結果として、信用や人間関係を失うことにもつながります。
📎 アンカリングにも「効きにくい人」がいる
アンカリング効果は誰にでも働くとは限りません。
特に以下のような人には、効果が限定的です。
- 知識や経験が豊富で「相場感」がある人
- 価格や価値を比較することに慣れている人
- 感情よりも論理やデータで判断するタイプの人
こうした人々は、アンカーに頼らず「根拠」や「市場全体の情報」で判断する力を持っています。
つまり、アンカリング効果は万能ではないのです。
だからこそ大切なのは、
「自分が影響されているかもしれない」という視点を持つこと。
そして、「相手も影響を受けているかもしれない」と配慮することです。
💡 使い手である前に、理解者であれ
アンカリング効果の本当の価値は、
「自分の思考を見直す視点」を与えてくれることにあります。
他人を操作するのではなく、
自分の思考を整え、冷静に選択する力を育てる――
それが、アンカリング効果と上手につき合うための、
もっとも大切な“心得”ではないでしょうか。
5. おまけコラム
怒られなかった理由は「時間設定」にあった!?
📚 小さな気配りが生んだ、予想外のやさしさ
高校2年生のユウくんは、いつもより少し早めに家を出たものの、
途中の電車が人身事故でストップ。どうやっても遅刻は避けられそうにありません。
「どうしよう…先生、怒るかな…」
迷った末に、彼はスマホでこうメッセージを打ちました。
「先生、すみません!45分くらい遅れそうです…!」
電車が再開したあと、彼は必死に移動し、
最終的には「30分遅れ」で教室に到着。
すると先生はこう言いました。
「お、意外と早かったじゃないか。大丈夫だった?」
ユウくんは拍子抜け。怒られるどころか、ねぎらわれたのです。
🧠 これはまさに「期待値アンカー」の効果!
ユウくんは無意識のうちに、先生の心に**「45分遅れる」というアンカー(基準)**を下ろしていました。
それに比べて30分という実際の遅れは、
“予想よりマシ”というポジティブな印象につながったのです。
これは、「アンカリング効果」が時間や感情の期待値にすら作用することを示す、
とても日常的で興味深い一例です。
もちろん、毎回遅刻して「予防線」を張るのはおすすめしませんが、
「どう伝えるか」が相手の受け取り方に影響するという事実は知っておいて損はありません。
このテクニックを応用して
アンカリング効果で遅刻もやわらぐ!?
「30分遅れる」と正直に言うより、あえて「45分遅れます」と伝えておいて、
30分で到着すると「早く来たね!」と思ってもらえる。
このように、予測を操作することで印象を変えることも、
アンカリング効果の面白い使い方です。
ただし、使いすぎると「いつも大げさ」と思われるのでご注意を!
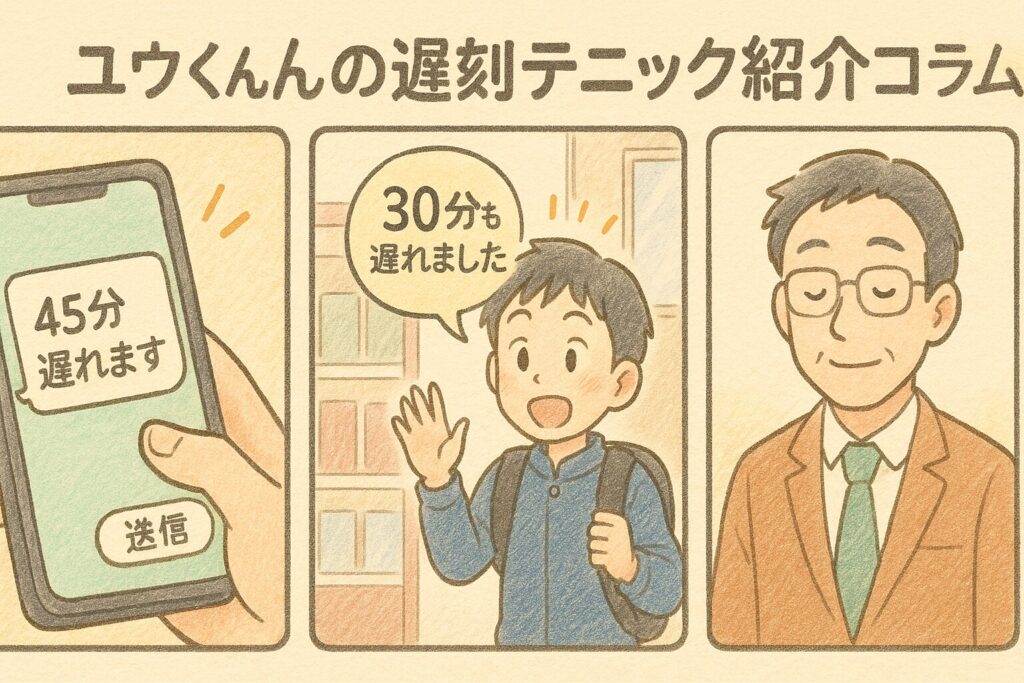
まとめ・考察
気づかぬうちに、選択の“錨”を下ろしているかもしれない
アンカリング効果は、「最初に与えられた情報に判断が引きずられる」現象です。
でもこれは、単なる心理テクニックではありません。
もっと根本的には、人間が“効率よく考える”ために脳が使っているショートカット機能のようなものです。
つまり私たちは、気づかぬうちに「最初の情報」に縛られて、
選択や評価、感情までも動かされているかもしれないのです。
💡 たとえば、こんな経験はありませんか?
- 飲食店でセットメニューの価格を見たあと、単品が割高に感じた
- テストで難しい問題から始めたことで、その後の問題がやたら簡単に見えた
- ダイエットアプリで目標体重を先に設定したら、自然と意識が変わっていった
これらはすべて、アンカリング効果が“静かに作用している瞬間”です。

🤔 あなたなら、この効果をどう使いますか?
人は、無意識に流される側でいることが多いですが、
アンカリング効果を「知っている」だけで、
今後の判断はきっと変わってくるはずです。
自分の選択に自信を持つために、
まずは「最初の印象」や「出会った数字」を、
一度立ち止まって見直してみませんか?
その一歩が、「考える力」を育てる最初の習慣になるかもしれません。
さらに学びたい人へ
アンカリング効果をもっと深く理解したい方や、
心理学・行動経済学を日常に活かしたい方に向けて、信頼性が高く、評価の高い書籍をご紹介します。
おすすめ書籍
『ファスト&スロー(下巻) あなたの意思はどのように決まるか?』
『予想どおりに不合理――行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』
『人を動かす』
『行動経済学の使い方』
特徴とおすすめ理由
『ファスト&スロー(下巻) あなたの意思はどのように決まるか?』
著者:ダニエル・カーネマン
出版社:早川書房
📘 特徴
アンカリング効果を提唱した心理学者、カーネマン自身による集大成的著作です。
「人間の判断はどのように非合理に傾くのか?」を、システム1・2という2つの思考モデルで徹底解説。
🌟 おすすめ理由
アンカリング効果を含む思考バイアス全般を根本から理解したい人に必読の一冊。
難解な部分もありますが、ゆっくり読めば得られるものが非常に大きいです。
『予想どおりに不合理――行動経済学が明かす「あなたがそれを選ぶわけ」』
著者:ダン・アリエリー
出版社:早川書房
📘 特徴
日常生活の中の“なんで自分はこう選んでしまったのか?”という疑問を、
行動経済学の実験を通じて軽快に解説するロングセラー。
🌟 おすすめ理由
非常に読みやすく、親しみやすい語り口で書かれており、
アンカリング効果を含めた非合理な判断の数々を、身近な実例から楽しく学べます。
『人を動かす』
著者:D・カーネギー
出版社:創元社
📘 特徴
一見、行動経済学とは関係ないように見えますが、
人間関係や説得・印象形成の場面で、**無意識の心理操作(アンカリングを含む)**がどのように働くかが豊富に記されています。
🌟 おすすめ理由
80年以上読み継がれる名著であり、ビジネス・教育・家庭などあらゆる場面に応用可能。
「人の心にどんな“いかり”があるのか?」を知るうえでも役立ちます。
『行動経済学の使い方』
著者:大竹文雄(おおたけ ふみお)
出版社:中公新書(中央公論新社)
📘 特徴
日本人著者による行動経済学の入門書。
医療、税金、教育など、**日本の社会問題にどう活かせるか?**という実践的視点が豊富。
🌟 おすすめ理由
日本の制度や文化に合わせた応用事例が多く、実生活に落とし込む際のヒントが得られる点が秀逸です。
🛒 おすすめ書籍まとめ(一覧)
| 書名 | 著者 | 特徴 |
|---|---|---|
| ファスト&スロー | ダニエル・カーネマン | 理論と研究の根幹を理解できる名著 |
| 予想どおりに不合理 | ダン・アリエリー | 実験と日常のギャップに気づける |
| 人を動かす | D・カーネギー | 心理の原則と人間関係の極意 |
| 行動経済学の使い方 | 大竹文雄 | 日本社会に即した応用視点が豊富 |
締めとして
🧩 思考は自由。でも「最初の一言」に縛られることもある。
私たちは毎日、さまざまな選択をしながら生きています。
どれが正解かなんて、すぐには分からないことばかり。
けれど、その選択の背後には、最初に見た数字や言葉が静かに影響していることもあります。
アンカリング効果は、決して“だまされやすさ”を責めるための知識ではありません。
むしろ、自分の思考を少し客観的に見直すためのレンズなのです。
何かを選ぶとき、誰かに提案するとき、あるいは自分と向き合うとき――
ほんの一瞬、「これは“最初の情報”に引きずられていないかな?」と
心に問いかけてみてください。
そのたびに、あなたの選択は少しずつ、自分の意志に近づいていくはずです。
🔍 補足注意
本記事では、著者本人が個人で調べられる範囲で、
アンカリング効果に関する心理学的な理論・事例・応用例を、
信頼できる文献や学術情報に基づいて、わかりやすく解説してきました。
ただし、以下の点についてもご理解をお願いいたします。
🧠 この記事は「唯一の正解」を示すものではありません
心理学・行動経済学は、日々研究が進化している分野です。
今後の実証データや理論の更新によって、解釈が変わる可能性も十分にあります。
本記事は、**令和7年現在における信頼性の高い情報をもとにした“入り口”**であり、
すべてのケースや考え方を網羅したものではないことをご留意ください。
🧭 このブログのスタンス
「正しさ」よりも、「考えるきっかけ」になることを大切にしています。
知識は、自分で使ってこそ価値があります。
アンカリング効果を知ったあなたが、これからの判断や選択に活かしてくれるなら、
それがこの記事の最大のゴールです。
📝 ぜひ、あなた自身の視点でも考えてみてください
- あなたが無意識に受け取っていた“アンカー”は何だったのか?
- これから、どんな場面でこの知識を役立てていきたいか?
それを考えることこそが、
知識を「行動の武器」に変える最初の一歩です。
あなたのこれからの選択が、誰かに下ろされた“いかり”ではなく、
自分自身の意思で選んだアンカーによって導かれますように。
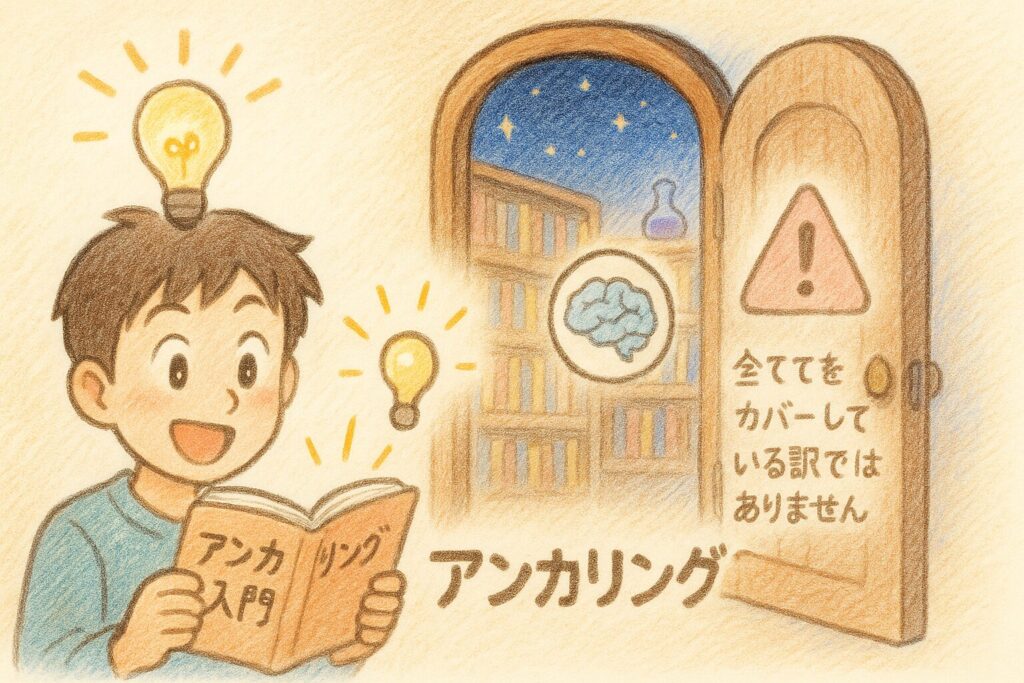
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました。







コメント