なぜか隣の席の人とは仲良くなるのに、少し離れただけで会話が減ってしまう――その不思議を解き明かすのが『アレン曲線』です。
席が近いと仲良くなるのはなぜ?人間関係を変える『アレン曲線』の法則
「クラスや職場で、気づけば“近くの席”の人と仲良くなっている」――そんな経験はありませんか。
朝の「おはよう」から、ちょっとした雑談、ふと視線が合って笑う瞬間まで。
なぜ“距離”が近いだけで関係が深まりやすいのでしょう。
思い当たるシーン、ありませんか。
授業中、消しゴムを貸し借りしているうちに、気づけば休み時間も一緒に行動している。
プリントを配る“中継役”を頼まれて、隣の人と話す回数が自然に増える。
席が近い同僚とは、資料の確認やちょっとした質問がサッとできて、会話がつながる。
プリンタや給湯スペースに行くたび、近いデスクの人と一言二言、近況を交わす。
模試の見直しや仕事の締切前、隣から聞こえる独り言やタイピング音に「今がんばってるんだな」とつい話しかける。
席替えで遠くになったら、同じ人なのに気軽に声をかけづらくなった――そんな感覚。
この不思議な現象には、ちゃんとした名前があります。
一緒にその正体を探っていきましょう。
読むメリット
・身近な人間関係の“もやもや”がスッキリします。
・席替えや座席レイアウトのコツがわかります(ストレス軽減・仕事の効率化にも)。
疑問が生まれた場面
新しい部署に異動したばかりのある日。
あなたはオフィスの一角に用意された席に座ります。
隣のデスクの同僚とは、書類を渡したり「ちょっといいですか」と声をかけたりするうちに、自然と雑談も増えていきます。昼休みには一緒に食事に行くことも当たり前に。気づけば、相談もしやすい“心強い存在”になっていました。
一方で、同じチームでも部屋の反対側や別フロアにいるメンバーとは、必要な連絡を交わすだけ。仕事内容はつながっているのに、会話の機会はぐっと少なく、関係が深まりにくいのです。
――どうしてだろう。
近い席の人とは自然に仲良くなるのに、距離があるだけで接点が薄くなる。
これは単なる偶然なのか、それとも人の行動に関わる“仕組み”なのか。
その理由を一緒に学んでみましょう。
すぐに理解できる結論
お答えします。
この現象は 『アレン曲線』 と呼ばれています。
人は、物理的な距離が近いほど会話ややりとりが増え、距離が離れると急激に減ってしまう――そんな人間の行動パターンを示したものです。
MITの経営学者トーマス・J・アレンが実際にオフィスでエンジニアたちを調査し、証明しました。つまり「近い席の人と自然に仲良くなる」のは偶然ではなく、統計的にも裏づけられた法則なのです。
たとえば、ほんの数メートルそばにいる人とは「ちょっと聞いてみよう」「つい話しかけてみよう」が積み重なります。逆に、50メートルほど離れると定期的な会話はほとんど途絶えると報告されています。だから、「同じチームなのに遠い席の人とはあまり話さない」と感じるのも自然なことなのです。
となりの席の人は声をかけやすいから仲良くなれる。遠くなると声をかける回数がどんどん減る“カーブ”があるということです。
――これが、クラスや職場で起きていた“不思議な現象”の正体です。
近いほど自然に言葉が行き交い、遠ざかるほど静けさが広がる――これがアレン曲線の示す人間関係の不思議です。
この不思議なカーブの正体を、もっと深く知りたいと思ったなら、さらに掘り下げた説明を一緒に読み進めていきましょう。「座席の配置を工夫する」「離れている人には会うきっかけを作る」など、すぐに使えるヒントも紹介します。

『アレン曲線』とは?
アレン曲線(Allen curve)とは、
「人と人の距離が離れるほど、会話やコミュニケーションの回数が急激に減っていく」
という法則を示したグラフのことです。
ポイントは “指数関数的に減る” という点。
ちょっと離れるだけで、やり取りがガクッと少なくなり、
50メートルほど離れると、定期的なやり取りはほとんどなくなると報告されています。
つまり、となりの席の人とは自然に仲良くなるのに、
フロアの端や別の階の人とは「用件だけ」になりやすい。
これは気のせいではなく、研究で証明された人間の行動パターンなのです。
誰が発見したの?
この研究を行ったのは、
MIT(マサチューセッツ工科大学)スローン経営大学院の教授、
トーマス・J・アレン(Thomas J. Allen, 1931-2020) です。
アレンは経営学者であり、特に
「イノベーションがどう生まれるか」
「研究開発組織の中で人と人の知識がどう伝わるか」
をテーマに長年研究してきました。
1970年代、アレンは実際のオフィスに足を運び、
エンジニアたちがどれだけの頻度で会話をしているかを丁寧に調査しました。
その結果をまとめた本が 『Managing the Flow of Technology』(MIT Press, 1977) です。
この本の中で、アレンは「人と人の距離と会話頻度」の関係をグラフに描き、
その曲線が後に「アレン曲線」と呼ばれるようになりました。
要点を整理すると
近いほど話す/遠いほど話さない
低下の仕方は「指数関数的」=ちょっとの距離が大きな差になる
50m離れると、定期的なやり取りはほぼゼロ
対面だけでなく、電話やメールなどの連絡も同じように減っていく
アレン曲線が示しているのは、
「近さが会話のきっかけをつくる」という
シンプルだけど強力な人間関係の法則です。
なぜ注目されるのか?
アレン曲線はただの“雑学”ではありません。
現代の働き方や学び方に、とても大きな意味を持っています。
イノベーションと偶発的な会話
新しいアイデアは、机に向かって考えるだけでは生まれにくいものです。
「ちょっとした雑談」「思いつきの相談」から生まれることが多いのです。
距離が近いと、こうした偶然の会話が起こりやすく、
結果としてイノベーションや学びの速度を上げることにつながります。
50mの壁
研究によると、50m以上離れると定期的な交流はほぼ途絶えるとされています。
同じ会社にいても、フロアが違ったり建物が違うと、
「同じチームなのにほとんど話さない」という現象が起きやすいのです。
デジタル時代でも残る距離効果
「オンラインでつながれるから距離は関係ないのでは?」
そう思われがちですが、調査では違う結果が出ています。
Microsoftが数万人規模で行った研究によれば、
リモートワーク中心になると、社内のネットワークが分断され、
部署やチームごとに“サイロ化”してしまうことが確認されました。
つまり、デジタルツールがあっても
「近くにいる人と自然に雑談する」効果を完全には代替できないのです。
まとめ
アレン曲線が教えてくれるのは、
「人は近さでつながる生き物」だということです。
隣の席なら「ちょっと聞いてみよう」と気軽に声をかけられる。
逆に数十メートル離れると、同じチームでも別世界のように感じてしまう。
これは単なる偶然ではなく、経営学者アレンが示した人間関係の法則です。
だからこそ、学校の席替えや職場の座席配置は、
人間関係や仕事の効率に大きな影響を与えるのです。
実生活への応用例
アレン曲線は、私たちの身近な場面でも活かせます。
学校でも職場でも「席の距離」が人間関係に影響するのは同じです。
学校での応用
席替えの効果
仲良くなりたい相手や、一緒に勉強したい友達と近い席になれば、自然と会話の回数が増えます。
グループ学習
机を寄せ合うだけで、相談や雑談が増えてチームワークが強まります。
先生の工夫
授業中に協力させたい生徒を近い席に配置することで、よりスムーズに活動が進みます。
職場での応用
席の配置
頻繁にやり取りが必要なメンバーは近くに配置する。
逆に、集中が必要な人は静かなゾーンにまとめる。
別フロア問題
遠い席やフロアを隔てると接点が減るので、定期的に「顔を合わせる時間」を設ける。
偶発的な交流のデザイン
プリンターや給湯室など、人が集まる場所を工夫して配置し、偶然の会話を増やす。
すぐできる小さな工夫
朝のあいさつを意識して声に出す
別フロアの人とはオンラインだけでなく「月に一度は直接会う」ルールを作る
座席を少し変えるだけでも会話のきっかけになる
まとめ
アレン曲線を意識すれば、人間関係は「偶然まかせ」ではなく「デザインできる」のです。
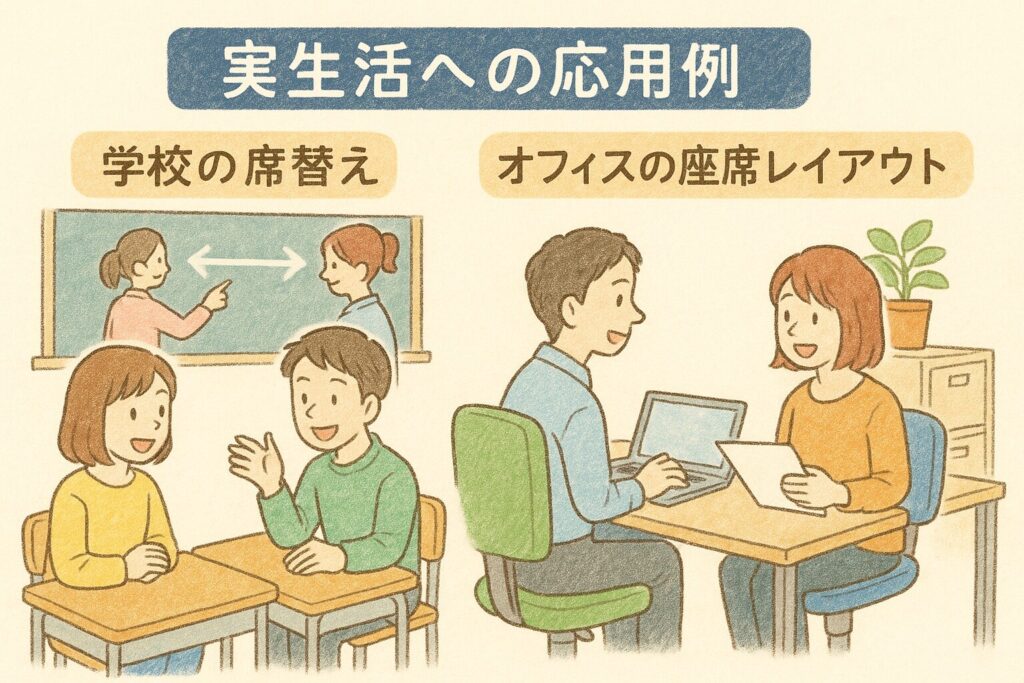
注意点や誤解されがちな点
アレン曲線は「近さが会話を生む」ことを示した強力な知識です。
でも、便利な一方で
誤解されやすい点や注意すべき落とし穴もあります。
誤解①「近ければ必ず仲良くなれる」
たしかに、隣にいると声をかける回数は増えます。
でも、それだけで必ず良い関係になるわけではありません。
相性が合わなければ、むしろストレスが増えることもあります。
これは心理学でいう 単純接触効果(たんじゅんせっしょくこうか/mere-exposure effect) の“過信”です。
単純接触効果(mere-exposure effect)とは?
心理学者ロバート・ザイアンス(Robert Zajonc, 1968)が提唱した現象で、
「人は、繰り返し接する対象に対して好意を持ちやすくなる」
という心理効果です。
ただし、この効果は「対象に対して強い嫌悪感がない場合」に限られます。
最初から苦手意識が強い相手に何度も接すると、
かえって嫌悪感が強まることもあるのです。
対策
「集中中は声かけNG」などのルールを先に共有する
話す時間や相手を本人が“選べる”環境にする
1日30秒だけ雑談する「小さな安心の接点」をつくる
誤解②「オンラインなら距離は関係ない」
Zoomやチャットがあるから距離ゼロで話せる。
そう思いたくなりますよね。
でも実際には違います。
研究では、電話やメール、チャットでも
遠い人ほど連絡が減ることが示されています。
理由はシンプル。
「つい声をかける」が起きにくく、
こちらからきっかけを作る負担が大きいからです。
対策
週1回10分の「雑談タイム」をオンラインで設定する
チャットは“既読リアクション”を必ずつけるルールにする
月1回は顔を合わせる日を作り、物理的接点で補う
誤解③「近ければ生産性が上がる」
近ければ相談しやすい。
でも、それが集中力を高めるとは限りません。
声をかけられるたびに
作業の流れが途切れる「中断コスト」が発生します。
結果的に生産性は下がることもあります。
対策
協働ゾーンと静音ゾーンを分けて座席を配置する
「1時間は声かけ保留」の集中タイムを宣言する
緊急用だけ“ホットライン”を決め、通常相談はまとめて行う
誤解④「距離だけ変えれば文化も変わる」
座席を近づければ人間関係がよくなる。
そう考えるのは短絡的です。
信頼やフィードバックの習慣がなければ、
近接はかえって摩擦を増やすこともあります。
対策
「否定しない」「遮らない」など、安心できる約束を共有する
毎日1回「ありがとう」を言う小さな儀式を取り入れる
部署間は“連絡係”をローテーションし、橋をかける

まとめ
アレン曲線は「近さ=きっかけ」を可視化したものです。
けれども、魔法の解決策ではありません。
人の性格
仕事内容
チームの文化
これらを考えて調整してこそ、効果を発揮します。
近さと静けさのバランスを決めること。
オンラインの摩擦をルールや儀式で補うこと。
その工夫が、距離のカーブをあなたの味方に変えてくれるのです。
おまけコラム
数字の“読み方”
よく見かけるフレーズに
「1.8m と 18m では、会話の回数が約4倍違う」
というものがあります。
わかりやすい例えですが、これはあくまで
“イメージを伝えるための説明” です。
アレン曲線の本質は、
「距離が離れるほど、会話が指数関数的(しすうかんすうてき)に減っていく」
というカーブにあります。
どうやって調べたの?
1970年代、MITの経営学者トーマス・J・アレンは、
研究所のエンジニアを対象に、
「誰が、誰と、どれくらい話しているのか」を
実際に観察してデータ化しました。
その結果をまとめたのが、
『Managing the Flow of Technology』(1977, MIT Press)。
アレン曲線を世に知らしめた トーマス・J・アレン(Thomas J. Allen) の代表的著作です。
アレン曲線の「距離と会話頻度は指数関数的に減少する」という知見は、この本にまとめられています。
ここで示されたのが、距離と会話頻度の関係を表すグラフ。
これが「アレン曲線」と呼ばれるようになりました。
数字が持つ意味
1.8m(約となりの席)
机を少し横にのぞけば声をかけられる距離。
「ちょっといい?」が自然に生まれるゾーンです。
18m(部屋の向こう側)
立ち上がって歩かないと声が届かない距離。
心理的にも「後でメールにしよう」となりがちです。
50m前後(別フロア・別棟と同じ感覚)
週に一度の定期的なやりとりがほぼ消える。
「物理的な壁=人間関係の壁」になりやすい分岐点です。
ポイントは「数字に縛られすぎない」こと
“4倍”という表現はわかりやすいですが、
現場のレイアウトや文化によって実際の数値は変わります。
大切なのは、自分の現場で観察すること。
「誰と誰が、どのくらいの距離で、どれだけ話しているか」を見て、
そこから小さく配置やルールを調整していくのが正解です。
まとめ・考察
距離が近いほど、会話は増える。
離れるほど、会話は急激に減る。
50mを超えると、定期的なやり取りはほぼ消える。
別フロア・別棟は「同じ組織でも別世界」になりやすい。
デジタル全盛の今でも、“偶然の橋渡し”は自然には起きにくい。
だからこそ、設計して交流を生む工夫が必要です。
考察
「知は接面から生まれる」と言われます。
人と人の偶然の出会いが、新しい学びや創造を生み出すのです。
オフィスや教室は、ただ机を並べる場所ではなく、
人を動かし、出会わせる“戦略資源”でもあります。
学校の「席替え」を思い出してみてください。
隣が変わるだけで、クラス全体の空気が変わりませんでしたか?
実はこれ、最小コストの“イノベーション政策”。
次の席替えでは、情報をつなぐ“橋渡し役”を真ん中に置くだけで、
クラス全体のつながりが変わるかもしれません。
あなたへの問いかけ
こんな体験はありませんか?
席を一つ近づけただけで、相談が増えた
部署横断ランチで、別フロアの人と雑談が生まれた
あなたなら、この「距離の知恵」をどう活かしますか?
ぜひコメントで教えてください。
仕上げに
近いと声が届き、心も届く。
けれど近さは万能薬ではありません。
工夫次第で、アレン曲線はストレスの源にも、
安心と信頼の土台にもなります。
今日からできるのは、たった一歩。
席を少し寄せる。
ひと言、挨拶を加える。
その小さな工夫が、あなたの周りに新しい橋をかけてくれます。
アレン曲線は「人は近さでつながる」というシンプルな真実を示しています。
けれど、それをどう活かすかは一人ひとりの工夫次第。
あなたが今日、誰にどんな一歩を近づけるのか――その選択が、未来の人間関係を描いていきます。

さらに学びたい人へ
アレン曲線や「人と人の距離」をテーマに、もっと深く学びたい方へ。
おすすめの書籍をご紹介します。
📘 組織を変える5つの対話
著者:ダグラス・スクワイア、ジェフリー・フレドリック
出版社:オライリー・ジャパン
特徴:アジャイル経営やチームづくりで重視される「対話」を体系化。5つのステップを使って、信頼関係を築き、協働を生み出す方法を解説しています。
おすすめ理由:アレン曲線が示す「距離の近さが会話を増やす」という発見を、実際の組織づくりに応用するなら必読の一冊。偶然の会話をどう“設計”するかという視点を得られます。
📗 組織と人を活性化する インナー・コミュニケーションと社内報
編集:産業編集センター
出版社:産業編集センター
特徴:社内報や社内広報の工夫を通じて、社員同士のつながりをどう活性化するかを解説。距離や部門の壁で分断されがちな情報を「どう橋渡しするか」が中心テーマです。
おすすめ理由:アレン曲線が課題とする「離れると話さなくなる」現象を、制度や情報発信の工夫でどう補うかが学べる実務的な一冊です。特に人事・広報・組織開発に関わる方におすすめ。
💡 まとめ
理論を現場で応用したい人 → 『組織を変える5つの対話』
制度や広報の工夫で橋渡しを考えたい人 → 『インナー・コミュニケーションと社内報』
どちらも「アレン曲線」を直接解説する本ではありませんが、
“距離と交流”の知見を、実際の組織や職場でどう活かすかを考えるヒントになります。
疑問が解決した物語
異動してからしばらく経ったある日。
あなたは休憩スペースで社内報を手に取り、
「アレン曲線」という言葉を見つけます。
――人は、物理的な距離が近いほど会話が増え、
離れると急激に減ってしまう。
MITの研究で示された、そんなグラフの存在。
ページを読み進めるうちに、
「ああ、だからか」と胸の中でつぶやいていました。
思い返せば、隣の席の同僚とは自然に雑談が増えた。
でも、部屋の反対側のメンバーとは“用件だけ”。
それは偶然ではなく、距離が会話のきっかけを左右していたのです。
「なるほど、仕組みがあったんだ」
そう気づくと、心の中のもやもやが一気に晴れていきます。
そして小さな工夫を思いつきます。
――席が遠い人には、意識して話しかけてみよう。
――週に一度は、別フロアにも顔を出してみよう。
物語の主人公である“あなた”は、
答えを知ったことでただ安心するだけでなく、
「距離を超える工夫」を自分の行動に加えるきっかけを得たのでした。
記事の締めとして
人との関係は、偶然だけでなく「距離」という見えない要素にも左右されます。
アレン曲線は、その仕組みを教えてくれるヒントです。
近ければ声が届き、心も届く。
遠ければ声は途絶え、心の距離も広がりやすい。
けれど、距離を工夫し、意識して声をかけることで、
私たちはつながりを取り戻すことができます。
明日からできることは、とても小さな一歩。
席を少し寄せる。
休憩時間に遠い席の人へ「こんにちは」と声をかける。
その一言が、思わぬ関係を育ててくれるはずです。
この記事が、あなたの周りの「いい距離感」を考えるきっかけになれば嬉しいです。
そして、ここで紹介した考え方はひとつの視点にすぎません。
研究が進めば、新しい発見や別の見方も生まれてくるでしょう。
どう活かすかは、あなた次第です。
あなたの毎日が、少しでも心地よく、つながりのあるものになりますように。
注意補足
今回の記事は、著者が個人として調べられる範囲でまとめた内容です。
他の考え方や研究成果も存在しますので、あくまでひとつの参考としてご覧ください。
今回紹介した「アレン曲線」は、経営学や組織心理学で広く認められた知見ですが、
「これが絶対の答え」ではありません。
人間関係は、距離だけで決まるものではなく、
性格や文化、組織のルール、時代背景によっても変わります。
また、研究は1970年代に行われたものが中心です。
その後のリモートワークやデジタル環境で、
新しい研究や発見も次々に出てきています。
つまり、この答えは“いまの最適解”であって、未来にはアップデートされる可能性があります。
🧭 本記事のスタンス
この記事は「これが唯一の正解です」と伝えるものではありません。
読者の皆さんが 「自分の環境にどう当てはめられるか」 を考えるための入り口です。
異なる立場や考え方にも価値があります。
ぜひご自身の現場で試し、観察し、調整してみてください。
もしこの内容が心に残ったなら、ぜひ「アレン曲線」のカーブを辿るように、
さらに深い文献や資料へと歩みを進めてみてください。

最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました。
出会いも学びも、距離が近いほど広がり、遠ざかるほど静けさに包まれていきます。
けれど、そのカーブを意識して一歩近づけば、新しいつながりも知識も生まれる。
どうぞ「アレン曲線」に導かれるように、あなた自身の学びの曲線を描いてみてください。





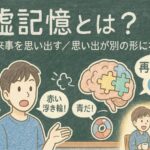

コメント