七夕に願い事をする理由 色・由来・伝説までまるごと解説!
7月7日になると願い事を短冊に書いて笹に飾りますよね。
でも、どうして七夕に願い事をするのでしょうか?この慣習の起源や意味、色選びの背景について気になったことはありませんか?
普段は気にかけない七夕の願い事の意味や、短冊にはそれぞれ意味があります、
五色の短冊にも、実は深い意味が込められているんですよ。
ミライちゃんは、学校で「七夕に願いを書こう!」と言われ、赤い短冊に「家族みんなが元気でいてね」と書きました。
兄のケンタくんは紫の短冊に「テストでいい点が取れますように」と書きました。
色の選び方まで知らないふたりでしたが、後で母親から「短冊の色にも意味があるんだよ」と教えられ、驚いて笑い合ったのでした。

記事を読むメリット
七夕の習慣の本当の由来と意味がわかります。
短冊の色の選び方が理解できます。願いの質に合わせて書けるようになります。
歴史・文化・心理が交わるこの習慣を大人にも子どもにも深く楽しめるようになります。
すぐに理解できる結論
お答えしますと…
七夕の願い事は、本来「技芸や学芸の上達」を星(織姫星)に祈る行事として伝わり、短冊に書く慣習へと発展しました。
七夕に願い事を書くのは、奈良時代に中国の宮中行事「乞巧奠(きこうでん)」が伝わり、平安時代以降、機織りや書道などの上達を星に願う宮中行事となり、江戸時代に五節句の一つとして庶民にも広まりました。
それでは、さらに深掘りした詳しい内容を覗いてみましょう。
七夕の由来や起源
中国の『牛郎織女伝説(ぎゅうろうしょくじょ)』とその内容
まず、中国の牛郎織女(牽牛星と織女星)伝説は、西周や春秋戦国にまでさかのぼる星座信仰が起源で、漢代以降に二人の切ない恋物語として広まりました。
民衆は古くから天の川を隔てた二つの星に思いを馳せ、その再会を年一度の特別な夜としました。それがやがて「乞巧節=七夕」と結びつき、女性たちが織りの技芸や学芸の巧さを星に願う風習が成立しました。

牛郎織女
※または中国音で「ニウラン・ジーヌー(牛郎・織女)」と読むこともあります。
意味:中国の民間伝承に登場する恋人たちで、天の川をはさんで年に一度だけ会えるという伝説の人物(星)です。
牛郎=牽牛星(けんぎゅうせい)=わし座のアルタイル
織女=織女星(しょくじょせい)=こと座のベガ
星座信仰とは?
夜空に見える星々や星座に神聖な力や意味を見出し、それらに願いをかけたり、季節や人生の運命を占ったりする信仰のことです。
西周(せいしゅう)
時代:紀元前1046年 ~ 紀元前771年ごろ
場所:中国大陸の中原地方
特徴:封建制度の基礎を築いた古代王朝。儀礼や礼節を重んじた文化が発展しました。
春秋戦国(しゅんじゅう・せんごく)時代
これは2つの時代に分かれます。
春秋時代(紀元前770年~紀元前403年)
名称の由来:『春秋』(孔子が編纂した歴史書)にちなんでいます。
周王朝が衰え、各地の諸侯が実権を握り始めた時代。
戦国時代(紀元前403年~紀元前221年)
中国全土で戦乱が広がり、「戦国七雄」と呼ばれる大国が覇権を争った時代。
最後に秦(しん)が中国を統一し、始皇帝が登場します。
※ 日本の弥生時代はおよそ紀元前1000年~紀元後250年ごろまでとされ、中国の春秋戦国時代と大きく重なります。
宮中行事としての『乞巧奠(きこうでん)』
この風習は奈良時代に遣隋使を通じて日本に伝来し、平安時代には宮中行事として定着しました。
当時は天皇や貴族が「乞巧奠」と呼ばれる儀式を開き、裁縫や詩歌、相撲などを交えた文化的な催しとして楽しまれました。
書籍や詩歌、針遊びなどで技芸を披露し、織女に上達を願うのが主な内容でした。
宮中では天平六年(734年ごろ)には詩会や相撲が催され、やがて「乞巧奠」が主要行事となりました。
室町時代以降には庭に灯台や供物を置き、音曲を奏で、灯りと詩と技芸が織りなす六夜が催されたことも記録に残ります。

乞巧奠(きこうでん)
意味:中国・漢代に始まり、七夕の夜に女性たちが手芸や書道などの「巧みさ(=巧)」の上達を願って行った儀式です。織女星に向かって祈る文化行事で、豆や針で手先の器用さを競うこともありました。
宮中行事としての「乞巧奠」とは?
日本では、奈良~平安時代にかけてこの風習が朝廷に伝わり、「乞巧奠(きこうでん)」は宮中行事(=朝廷で催される年中行事)として取り入れられました。
宮中での主な内容:
和歌や詩歌を梶の葉に書いて献じる
裁縫や機織りの道具を供える
音楽や相撲などの文化行事も行うことがあった
織女星に技芸(ぎげい:芸術や技能)の向上を祈願
天皇や皇族、女房(にょうぼう)たちが中心となり、夜の庭園に設けた祭壇に五色の糸や花を飾り、星空の下で雅な祈りの宴が開かれていたそうです。
こうした文化的な行事が、日本独自の風雅な年中行事「七夕」として形を変え、現代まで引き継がれています。

日本独自の要素との融合
さらに日本には古くから、「棚機津女(たなばたつめ)」と呼ばれる水辺で織物を奉納する女性の神話があり、中国由来の星祭りと融合しました。
奈良時代以降、中国の織女伝説と日本古来の棚機伝承が重なり、「七夕」=「たなばた」と訓読みされるようになりました。
江戸時代の庶民文化への展開
江戸時代になると、「乞巧奠」は五節句のひとつとして幕府に公式認定され、庶民の行事として広く親しまれるようになります。
笹竹に短冊を吊るす形が定着し、詩歌や飾り、手習いの願いが込められた五色短冊が流行しました。笹には神が依りつくと考えられ、屋根の上に立てて神迎えの意味もあったようです。
このように、奈良時代→平安の宮廷文化→江戸の庶民習俗と時代ごとに形を変えながらも、今に続く七夕文化として綿々と受け継がれてきました。
五節句としての七夕と現代の意味
五節句とは何か?
五節句とは、陰陽五行思想に基づき、中国から伝わった「奇数が重なる日」を吉兆として日本で設けられた五つの季節の節目で、1月7日・3月3日・5月5日・7月7日・9月9日を指します。
江戸時代に幕府が公式に定めたことで、現代まで残る伝統行事となりました。
七夕が五節句に含まれた背景
七夕は季節の節目であるとともに、技芸の上達や無病息災を願う星祭として扱われました。
江戸期には五色の糸飾りが短冊に変化し、竹に吊るす風習が定型化され、公的にも地域行事として根付いていきました。
現代での七夕の重要性と願い事の意義
現代では、七夕は天の川を見上げながら願いを書くロマンティックな日として定着しています。
ただし、元々は技芸上達を願う礼節的な文化に根ざしており、「願いごとを書いて整理する心理的効果」も現代に通じる実用性があります。
また、地域ごとの七夕祭り(仙台・平塚・一宮など)が観光資源となり、地域の経済振興や文化伝承としても重要です。
実生活への応用例
「短冊の色」と「五行思想」のつながり
七夕の短冊は、実はただの色付きの紙ではありません。
その色には、中国古代の陰陽五行説(いんようごぎょうせつ)という哲学に基づいた意味が込められています。
五行とは、自然界を構成する5つの要素「木・火・土・金・水」のこと。
この考え方は、季節・方角・臓器・感情などあらゆるものと結びつけられてきました。
それぞれの色は次のように意味を持ち、願いごとと組み合わせると「何を祈るのか」がより明確になります。
| 色 | 五行 | 象徴する価値 | おすすめの願い例 |
|---|---|---|---|
| 青/緑 | 木(仁) | 成長・人間力・誠実さ | 「挑戦を恐れず前に進みたい」 |
| 赤 | 火(礼) | 愛情・感謝・家族愛 | 「お母さんがいつまでも元気でいますように」 |
| 黄 | 土(信) | 安定・信頼・人間関係 | 「大切な人と仲良く過ごせますように」 |
| 白 | 金(義) | 約束・正義・責任感 | 「毎日コツコツ努力できますように」 |
| 紫(黒) | 水(智) | 学問・知恵・内面の成熟 | 「試験に合格できますように」 |
たとえば、もし「進学」を願うなら、紫の短冊が最適です。
逆に、「家族の健康」や「愛する人の幸せ」を願うなら、赤の短冊が心にぴったりと寄り添います。
✨色を選ぶだけで、願いごとの方向性がはっきりと見えてくる。
曖昧だった思いが、色の力で“言葉”になります。
なぜ「笹」に短冊を吊るすのか?
七夕といえば、笹の葉に願いを書いた短冊を吊るすイメージが浮かびますよね。
これはただの飾りではありません。
笹には、日本古来の自然信仰の中で“神が宿る依代(よりしろ)”とされる力強い象徴がありました。
笹は真っすぐ伸びる植物 → 成長・誠実・前進を象徴
殺菌力が強く枯れにくい → 邪気を払う「魔除け」として信仰
風にそよぐ音 → 神の気配を知らせる「神迎え」の意味も
古くは、神事や祭礼で笹竹が使われていた地域も多く、清浄なものとして扱われてきた歴史があります。
だからこそ、願いを清らかな笹に結びつけるという行為が、より神聖で意味のあるものとして根づいてきたのです。
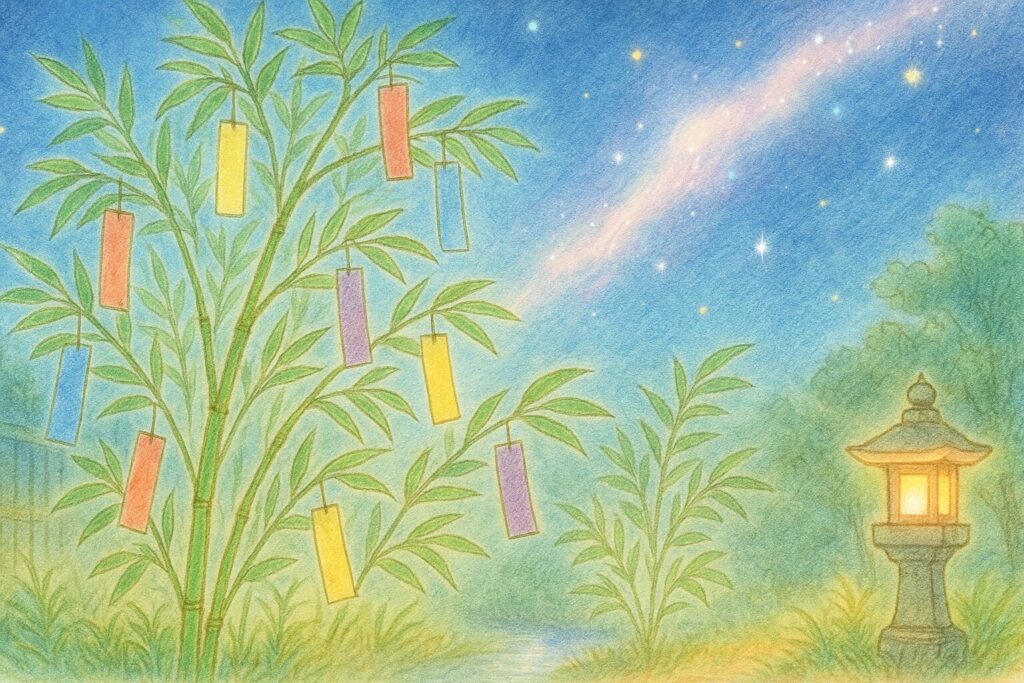
暮らしでの具体的な活かし方
七夕の文化は、「短冊に願いを書く」という行為を通じて、自分の思いや目標を見える化する効果があります。
🌿活かし方のヒント集
家族や子どもと短冊を一緒に作って話し合う
→「何を願う?」「どうしてその色にしたの?」という会話から、親子の心が通じ合うきっかけに。
職場や学校で、目標設定やモチベーション管理に活用
→「この色は自分の今の課題を表してる」と自覚できると、目標意識が自然と強まります。
五色そうめんや和菓子などで“食の七夕”を楽しむ
→ 家族団らんのひとときを演出。彩りある食事で「五行の意味」を体験的に学ぶことも可能。
🎋「願い」を書くだけで終わらせず、「言葉にして向き合う」ことが、自分自身を見つめ直す大切な時間になります。
注意点や誤解されやすいこと
「黒は使ってはいけない」は誤解?
一部で「黒は不吉」と誤解されがちですが、陰陽五行において黒は“水”=知恵と学問を象徴する正当な色です。
ただし、日本では祝い事や祈願では紫に置き換える慣習が定着しており、短冊でも「紫」が使われることが一般的です。
→ そのため「黒=悪い」というわけではなく、「見た目の印象」や「和の文化的配慮」から避けられるようになったと考えられます。

色の意味に縛られすぎないことが大切
短冊の色と五行の対応はとても参考になりますが、それにとらわれすぎて自分の本当の願いが書けなくなるのは本末転倒です。
たとえば「仕事がうまくいくように」でも、青・黄・白のどれに書いても意味はあります。
自分が直感で「しっくりくる」と感じた色に願いを託すのが一番。
📝大切なのは「誰のために、どんな思いで書くのか」。
色はその願いを“後押しするパートナー”であるべきです。
七夕の短冊に色があるのは偶然ではありません。
それぞれの色は、古代中国の五行思想に基づいた「願いの方向性」を映し出しています。
「この色で、こんな願いを」
――そう考えるだけで、今の自分の気持ちと真剣に向き合う時間になります。
そして、それを笹という生命力の象徴に結びつけることで、私たちは自然と一体になって願いを空へ届けようとしているのかもしれません。
短冊の色も、飾る笹も、そこに込めた思いも
――どれもが、あなたの「心の鏡」なのです。
おまけコラム
「棚機津女(たなばたつめ)」とは?
「たなばた」という言葉の語源をご存知ですか?
実は、日本に古くから伝わる「棚機(たなばた)神事」が由来とされています。
昔むかし、日本のある村で、若い乙女がひとり、川辺に設けられた小屋に入り、神様に捧げる布を一心に織っていました。
彼女の名は「棚機津女(たなばたつめ)」。その手は祈りに満ちて、心は村の安寧と人々の幸せを願っていました。
やがてその祈りと、空に瞬く星の物語が交差します。
天の川の向こう側にいる「織姫」に願いを届けようとする中国の風習「乞巧奠」が伝来し、布を織る女性の姿と重なっていきました。
それが、日本の七夕です。
織姫=空の神、
棚機津女=地の祈り。
この二人の祈りが交わり、今の私たちの「願いごと」という文化になりました。
短冊に込める思い、紙衣を吊るす願い。
それはすべて、「誰かのために、少しでも良くなりたい」という想いの形です。

融合に込められた願い
融合の背景には、ただの文化的な模倣ではなく、人々の“祈り”という普遍的な想いがありました。
乙女が神のために織った布 → 自分自身の努力を形にする
織姫に願う行為 → 技や知恵の成長を願う姿勢
つまり、「自分を磨き、誰かのために尽くす」という日本の価値観と、「技芸を極めることに対する尊敬」が、自然と結びついていったのです。
それはまさに、古代から続く“願いのかたち”の原点ともいえるでしょう。
紙衣(かみごろも)の飾りが意味すること
七夕飾りには「短冊」だけでなく、「紙衣(かみごろも)」という小さな紙の着物もあります。
これは、棚機津女が神に捧げた“神衣”の名残だと言われています。
現在では、災いや病気から身を守り、健康や長寿を願うお守りのような意味を持ちます。
紙衣に願いを込めることは、現代に生きる私たちが、
「大切な人のために、祈りの衣を織る」 という優しさを形にすることでもあるのです。
今あなたが願うその一言も、
古の棚機津女の祈りと、織姫の星のきらめきと、つながっているのかもしれません。
まとめ・考察
七夕の願い事は、技芸上達を祈る宮中儀礼から庶民文化へと広がり、色にも意味がある五色短冊の習慣へと進化しました。
真面目に願いを伝える行為は、自分の気持ちを整理する行為にもなり、願いを意識化する効果があります。
色や形の意味を知ることで文化との対話が始まる。
例えば、紫の短冊に「昨年よりもっと親切な自分になれますように」と書くことで、願いそのものが人格形成へのステップになります。
あなたならどの色の短冊に、どんな願いを書きますか?
📚 さらに学びたい人へ
『たなばたまつり』
著者・出版社:松成真理子/講談社
特徴:幼児~小学校低学年向けの創作読みきかせ絵本。温かみのあるイラストと簡潔な物語で、七夕の由来と風習を自然に理解できる構成になっています。短冊に書かれた願いが空へ昇る文体は、心に響く表現です。
おすすめ理由:親子で楽しみながら七夕の文化を学べる入門書。年少の子どもがいる家庭や教育現場で、季節の行事紹介として利用しやすく、七夕のイメージを育むのに適しています。
『行事のおはなし12か月』
著者・出版社:左近蘭子/くすはら順子(イラスト)/世界文化社
特徴:一年を通して日本の伝統行事を12の月ごとに物語形式で紹介する絵本集。七夕をはじめとする行事ごとの背景や風習が視覚的に豊かに説明されています。
おすすめ理由:七夕のみならず、四季の行事と比較しながら文化を理解したい人に最適です。行事の流れと意味がストーリー化されているため、子どもも大人も一緒に学べます。
『七夕伝説の謎を解く』
著者・出版社:勝俣隆(長崎大学名誉教授)/大修館書店
特徴:七夕に関する多くの疑問(なぜ七月七日? 「たなばた」と読む理由は?短冊の由来など)を、文学史・天文学・民俗学・歴史文献から丁寧に解き明かす学術的解説書です。古典作品から民俗行事の変遷まで広範囲をカバー。
おすすめ理由:七夕の背景について深く学びたい方や、文化史・日本文学・天文との関連を知りたい人にぴったり。専門的な探究を望む中学生以上や文化研究者にもおすすめです。
🌌 文章の締めとして
七夕の夜、私たちが空を見上げて短冊に願いを書くのは、ただの行事ではなく、古代から続く“想いを言葉にして届ける”という、深く美しい文化の形です。
織姫と彦星の物語、棚機津女の祈り、色と五行に込められた願いの意味──
それぞれが時代を超えて今に受け継がれ、私たちの日常にそっと寄り添っています。
あなたが短冊に込めるその願いも、誰かの心と、星のきらめきと、きっと静かにつながっているはずです。
七夕の夜が、あなたの願いにとって、最初の一歩となりますように。
注意補足
本記事は、著者が個人で調べられる範囲の中で現在得られる信頼できる情報や文献に基づいて構成しておりますが、すべてが唯一の正解ではありません。
他にもさまざまな視点や説があります。研究や文化は日々進化しています。
もしこの七夕の物語に心が動いたなら──
ぜひあなた自身でもさまざまな視点から七夕の魅力を探してみてください。
その想いの先へ。
願いごとのように、一歩ずつ、深い知と出会えますように。
七夕は、空に願うだけの日ではなく、あなたの心にある“祈りの種”を、言葉にして育てる時間です。
今宵、願いごとを一つ書くことで、あなたの未来が静かに動き出すかもしれません。
どうか、
あなたの願いごとが、星空にそっと届きますように――七夕の夜に願いをこめて。

最後までお読みいただき、
本当にありがとうございました。







コメント