 考える
考える 『雨模様』の意味は「降りそう」?「降ってる」?|由来・使い分け・調査データで迷いを解消
雨模様の本来の意味は「降りそう」。文化庁調査で受け取りが割れる現状と、誤解されない言い換えをまとめて解説します。
 考える
考える 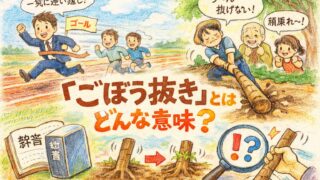 考える
考える 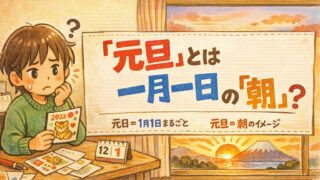 考える
考える 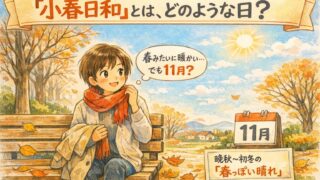 考える
考える  考える
考える 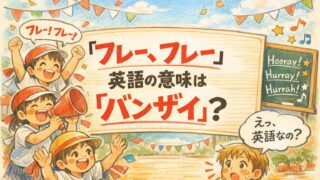 考える
考える 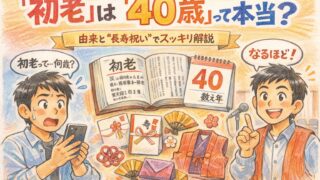 考える
考える  考える
考える 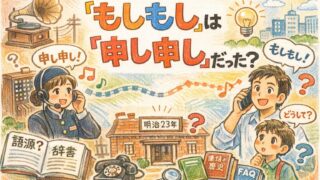 考える
考える  考える
考える