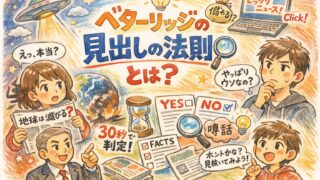 考える
考える 『ベターリッジの見出しの法則』とは?「疑問符見出しはNo」の真偽をやさしく検証
「?」で終わる見出しは信用していい?ベターリッジの見出しの法則をもとに、意味・由来・例外をやさしく解説。“見出しで反応、本文で判定”を身につける30秒チェックで、情報に振り回されない読み方がわかります。
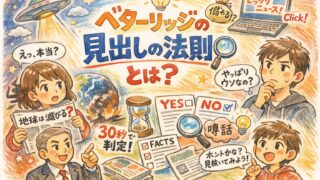 考える
考える  考える
考える 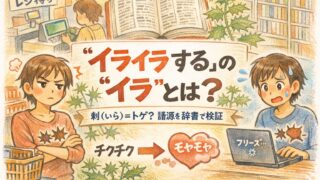 考える
考える  考える
考える 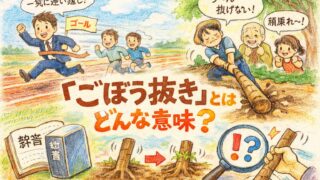 考える
考える 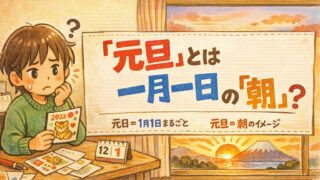 考える
考える 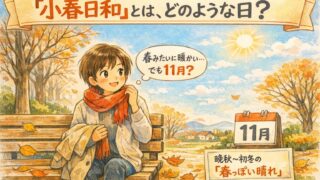 考える
考える  考える
考える 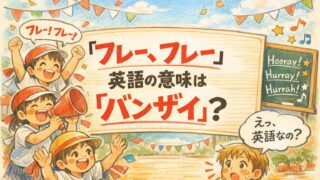 考える
考える 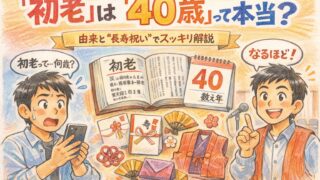 考える
考える