「めし」の本当の意味と歴史|ごはんとの違いと上品な語源の秘密
昔は上品な敬語だった『めし』が、なぜ今ではくだけた響きになったのか? 実はただの「ごはん」じゃない、その奥にある歴史をやさしくひもときます。
📖 目次
- 🍵 日常シーンから始まる小さな疑問
- 💡 すぐにわかる結論
- 🗝 「めし」のルーツと他の呼び方
- 📜 時代背景と使い分け
- 🛠 実生活での応用
- ⚠ 注意点と誤解
- 🍙 おまけコラム:干し飯の歴史
- 📚 さらに学びたい人へ(書籍紹介)
- 🎯 締めのメッセージ
🍵 日常シーンから始まる小さな疑問
カナ:お母さーん、めしできた?
母:カナ、その言い方ちょっと乱暴じゃない?
テレビや漫画でもよく聞く「めし」。でもなぜ、くだけた響きになったのでしょうか? そもそも昔は、もっと上品な言葉だったのです。
💡 すぐにわかる結論
- 「めし」= 尊敬動詞「召す」→ 名詞形「召し」→「召し上がるもの」= 食事。
- 室町時代から使用。もとは上品な語感、のちに口語化。
- 「ごはん」= 漢語「飯(はん)」+「御(お)」→「おばん」→ 江戸末期に「ごはん」。
- 古くは「いい」、保存食は「干し飯(ほしいい)」。
🗝 「めし」のルーツと他の呼び方
「めし」は尊敬動詞「召す」(食べる・着るなど)から派生した名詞形「召し」に由来。室町時代には「召し上がるもの」=食事全般を指す言葉として使われ始めました。
「ごはん」は全く別ルート。中国語由来の「飯(はん)」に丁寧の「御(お)」をつけた女房言葉「おばん」が音変化して江戸末に「ごはん」へ。
📜 時代背景と使い分け
室町期:いいに代わりめしが台頭。
江戸末期:ごはんが広く普及。
現代:めしはくだけた口語、ごはんは丁寧寄り。
使い分けのコツ
- 家族・友人:めし/ごはん
- 公的・改まった場:食事/お食事
- 目上の相手:召し上がりますか
🍙 おまけコラム:干し飯(ほしいい)の歴史
干し飯は炊いた米を乾燥させた保存食。平安期の『延喜式』にも糒として記録され、神饌や供御として制度的に備蓄されていました。
大阪・藤井寺市の道明寺ゆかりの道明寺糒は、やがて挽き割って道明寺粉となり、関西風桜餅や蒸し料理に利用されます。
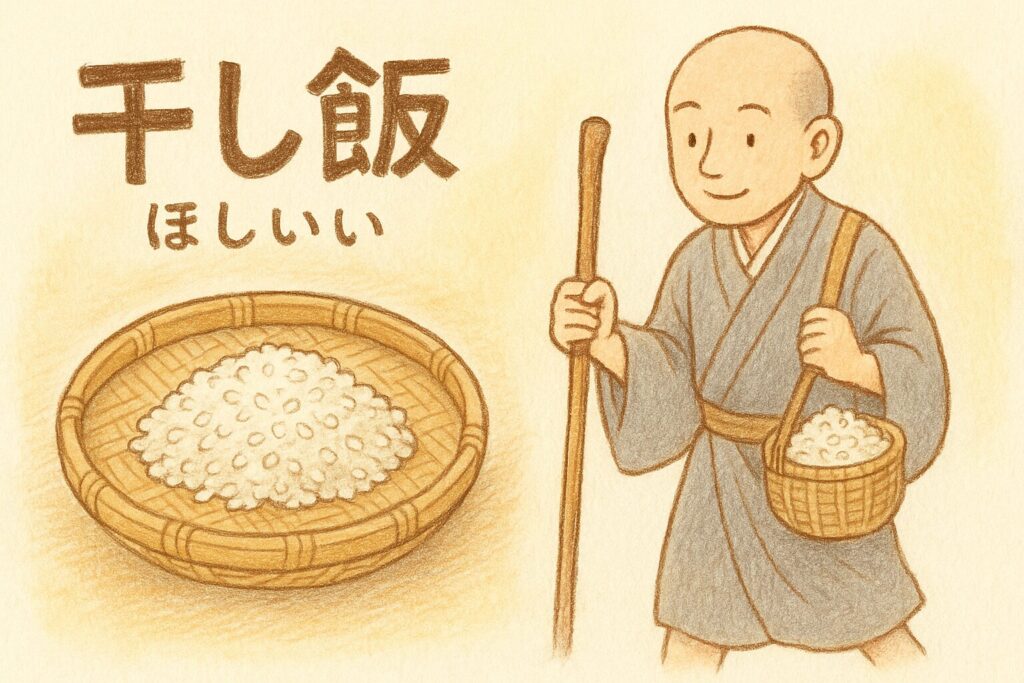
📚 さらに学びたい人へ
日本語源広辞典
増井 金典(東京堂出版/2010年)
体系的に語源を収録。今回の「めし/ごはん」のルーツをさらに掘り下げられます。
〈目からウロコの〉日本語「語源」辞典
学研辞典編集部(学研/2004年)
日常語の語源をやさしく解説。家族で読んでも楽しい一冊。
米の日本史
佐藤 洋一郎(中公新書/2020年)
稲作と米文化の全体像。干し飯や食文化史の背景理解にも役立ちます。
🎯 締めのメッセージ
言葉は時代と共に姿を変えます。かつて敬語だった「めし」も、今では日常の口語に。背景には日本人の暮らしと文化が息づいています。
この「めし」の話に興味がわいたら、ぜひ文献に“召し”進んで、もっと深い味わいを探してみてください。
それではまた次の言葉でお会いしましょう――ごちそうさま「めし」た。
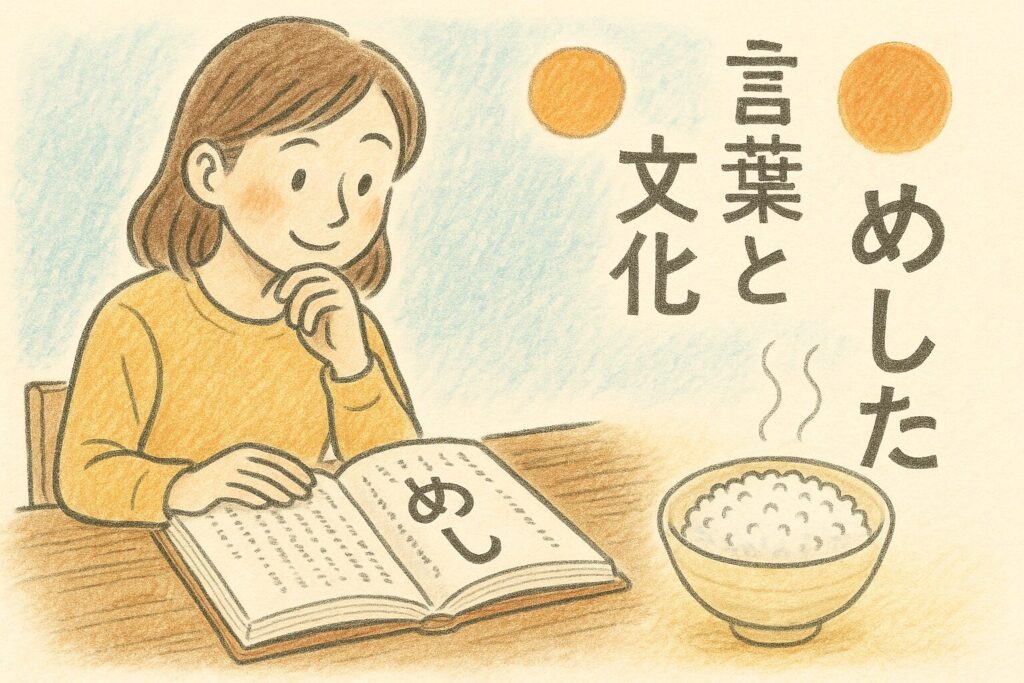
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました。






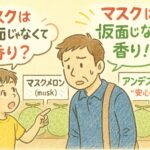
コメント