見ているだけなのに、なぜ自分まで赤面するのか?『共感性羞恥』
『共感性羞恥』とは?“もらい恥”の正体をわかりやすく解説【観察者羞恥との違いも紹介】
こんなことはありませんか?
家族のカラオケ:音程が外れた瞬間、自分の頬が熱くなる。
学校の発表:仲良しの友だちが台詞を噛んだら、自分の手のひらが汗ばむ。
職場のプレゼン:先輩のスライドが進まず沈黙、胸がキュッと縮む。
配信や動画:企画が滑ってスタジオが静まり返ると、画面の前の自分が赤面。
「見ているだけ」なのに、どうして自分の体が反応するのでしょう。
この正体を、今日のうちに言葉にします。

疑問が生まれた場面
ふしぎ。
親戚が集まった日曜のカラオケ。
お母さんは少し緊張しながら、あなたの好きな曲を選びました。イントロが流れ、1行目。音程がふらつき、声が小さくなる。
あなたの心臓はドクン。視線の置き場がなくなる。
「がんばれ」と応援したいのに、頬は熱く、指先は汗ばむ。
ステージに立っているのはお母さんのはずなのに、舞台の灯りはなぜか自分にも当たっている気がする——。
「見てるだけ、なのに身までミニッと縮む——“ミ”が重なるこのナゾ」
…一緒に、スッキリ解き明かしましょう。
すぐに理解できる結論
お答えします。
それは——共感性羞恥(きょうかんせいしゅうち)です。
他者が恥ずかしい状況にあるとき、観察している自分も“同じ恥ずかしさ”を感じてしまう心理を指します。
英語では empathic embarrassment(エンパシック・エンバラスメント)、または vicarious embarrassment(ヴァイケリアス・エンバラスメント)と呼ばれます。
とくに、家族や親友など心理的に近い相手で強まりやすいことが研究で示されています。脳画像研究でも、こうした“他者の気まずさ”を見たときに感情処理や心の推測に関わる領域が動くことが報告されています。
ポイント:あなたはお母さんの「恥ずかしい」という感情に寄り添ってしまい、自分の身体にも同じ反応(赤面・発汗・そわそわ感)が起きた——それが共感性羞恥です。
1分セルフチェック
① 親しい人の失敗で、自分の体が反応(赤面・発汗)しやすい。
② 「自分がやらかしたみたい」と身代わり感が生じる。
③ その場で応援したい気持ちが強くなる。
——2つ以上当てはまれば、共感性羞恥が起きている可能性が高いです。
すぐ判別のひとこと
共感性羞恥=相手も恥ずかしい → 自分も一緒に恥ずかしい。
観察者羞恥=相手は平気でも → 見ている自分だけ恥ずかしい。
(本記事の主題は前者。後者は「状況の気まずさ」による“もらい恥”です)
「見て、身が縮む、このミの謎——正体へスイッチ!」
——この恥の不思議、正体を更に詳しく解き明かしていきましょう。
共感性羞恥とは?
共感性羞恥(きょうかんせいしゅうち)とは、
他人が「恥ずかしい」と感じている場面を見たときに、
自分まで同じように恥ずかしさを感じてしまう現象です。
英語では
empathic embarrassment(エンパシック・エンバラスメント)
vicarious embarrassment(ヴァイケリアス・エンバラスメント)
ドイツ語の俗称
Fremdschämen(フレムトシェーメン)=「他人のために恥ずかしい」
👉 1987年に心理学者 Rowland S. Miller が初めて学術的に提示しました。
特徴(観察者羞恥との違い)
共感性羞恥
相手本人も恥ずかしい → その感情に同調して自分も赤面。
家族や友人など「心理的に近い相手」で強く起こりやすい。
観察者羞恥
相手本人は平気でも、状況が気まずいと観察者が赤面。
知らない人やテレビの芸人でも起こる。
👉 本人が恥ずかしがっているかどうかが大きな境目。

世間での呼び方と文化的背景
英語圏では secondhand embarrassment(セカンドハンド・エンバラスメント=もらい恥)とも呼ばれる。
ドイツ語の Fremdschämen は「他人の失敗にこちらが赤面する」として有名。
日本では「共感性羞恥」「観察者羞恥」という言葉が広がりつつある。
研究でわかっていること
代表的な研究
Rowland S. Miller(ローランド・S・ミラー, 1987年)
アメリカの社会心理学者。
共感性羞恥を初めて心理学的に定義。
1987年に empathic embarrassment(共感的羞恥) という概念を初めて学術的に提示しました。
「他者の恥ずかしさを見て、観察者が同じように恥ずかしさを体験する」という現象を体系的に論じ、共感性羞恥研究の基盤を築きました。
Tilmann A. Krach(ティルマン・クラッハ, 2011年, PLOS ONE)
ドイツの神経科学者。
fMRI研究で「共感性が高い人ほどACC(前帯状皮質)や前島が強く反応」することを発見。
2011年に発表したfMRI研究で、「他人の失敗や気まずい行為」を見たときに、観察者の脳の 前帯状皮質(ACC) や 前島(insula) が活発化することを示しました。
また、共感特性が高い人ほど脳活動が強いことも明らかにしました。
これにより「もらい恥」に神経科学的な根拠が与えられました。
Felix Müller-Pinzler(フェリックス・ミュラー=ピンツラー, 2016年, SCAN誌)
ドイツ・ハンブルク大学の心理学者。
「親しい人の失敗ほど強く恥ずかしさを感じる」ことを実証。
内側前頭前野(mPFC)や側頭極など“心を読む脳領域”が関与。
2016年に「社会的な近さが“もらい恥”を強める」ことを実験的に示しました。
特に 内側前頭前野(mPFC)や側頭極といった「他者の心を推測する脳領域」が、親しい人の失敗で強く働くことを発見。
「家族や友人ほど見ていて恥ずかしくなる」という日常感覚を科学的に裏づけました。
Kai Melchers(カイ・メルヒャーズ, 2015年, NeuroImage)
ドイツの神経心理学者。
テレビの「気まずいシーン」を見ているだけで脳が反応。
島やmPFCが「自己意識的な恥ずかしさ」に関わっていた。
2015年に「リアリティ番組などの“気まずい場面”」を視聴したときの脳活動を調べました。
観察者自身が体験しているわけではないのに、島(insula)や内側前頭前野(mPFC)が反応し、恥ずかしさを「自己意識的感情」として処理していることを明らかにしました。
「テレビを見ていてこちらが赤面する」感覚を脳科学で説明した重要な研究です。
脳の働き(わかりやすく地図化)
前島(anterior insula)
→ 胸がざわつく感覚や不快さを処理。
前帯状皮質(ACC)
→ 「居たたまれない!」と感じると反応。
内側前頭前野(mPFC)
→ 他人の心を推測する働き。親しい人の失敗で特に強い。
特性まとめ
親しい人ほど強く起こる(友人・家族>他人)
共感性が高い人ほど感じやすい
相手が恥ずかしがっていなくても → 観察者羞恥として発生することもある
すぐに区別できる早見
| 共感性羞恥 | 観察者羞恥 | |
|---|---|---|
| 相手本人の感情 | 恥ずかしがっている | 恥ずかしがっていない場合も |
| 恥ずかしさの由来 | 相手の感情に同調 | 状況の気まずさ |
| 起こりやすい対象 | 家族・友人など親しい人 | 芸人・見知らぬ人でも |
| 例 | 友人の赤面を見て自分も赤面 | 芸人のスベリ芸に自分が赤面 |
👉 覚えやすいフレーズ
共感性羞恥=共に感じる恥
観察者羞恥=観て恥ずかしい恥
読者への問いかけ
あなたはどちらの「もらい恥」を感じやすいですか?
親しい人の失敗に一緒に赤面する → 共感性羞恥タイプ
見知らぬ人の気まずさに赤面する → 観察者羞恥タイプ
自分の傾向を知ることで、
「なぜ自分だけ赤面するのか?」が腑に落ちて、
気持ちを軽くできるかもしれません。
人は誰かの「失敗」を笑うだけの存在ではありません。
近しい人が震えると、こちらの胸も震える。
それは弱さではなく、つながりの証拠です。
共に感じる恥(共感性羞恥)と、観て恥ずかしい恥(観察者羞恥)。
あなたが今、どちらを感じているのかが分かれば、
相手を守る振る舞いも、自分を楽にする視点も、選べます。
人はときに、他人の失敗で笑うのではなく、
「一緒に赤面する」ほど心が近づいてしまう存在です。
それが家族なら胸がざわつき、
友人なら汗ばむ手のひらを隠し、
職場なら自分まで声が震えそうになる。
——これは弱さではなく、人と人とがつながる証拠。
共感性羞恥(エンパシック・エンバラスメント)と
観察者羞恥(ヴァイケリアス・エンバラスメント)。
その違いを知ることで、
「自分がなぜ赤面したのか」が腑に落ち、
気持ちを軽くする第一歩になります。
実生活への応用例
共感性羞恥は「ただ恥ずかしいだけの厄介な感情」ではありません。
扱い方次第で、自分も楽に、相手も救える力に変えられます。
① その場での“しんどさ”をやわらげる
観客ではなく「観察者」になる訓練
👉 自分を頭上から見下ろすイメージを持ち、
「私は今、この場を観察している人」と言葉にしてみましょう。
研究では、こうした俯瞰的な視点が恥ずかしさをやわらげることが示されています。
相手への“支え”に切り替える
👉 小さくうなずく、さりげなく拍手する、視線をそっと外す。
相手の尊厳を守る振る舞いは、あなた自身の気まずさも下げます。
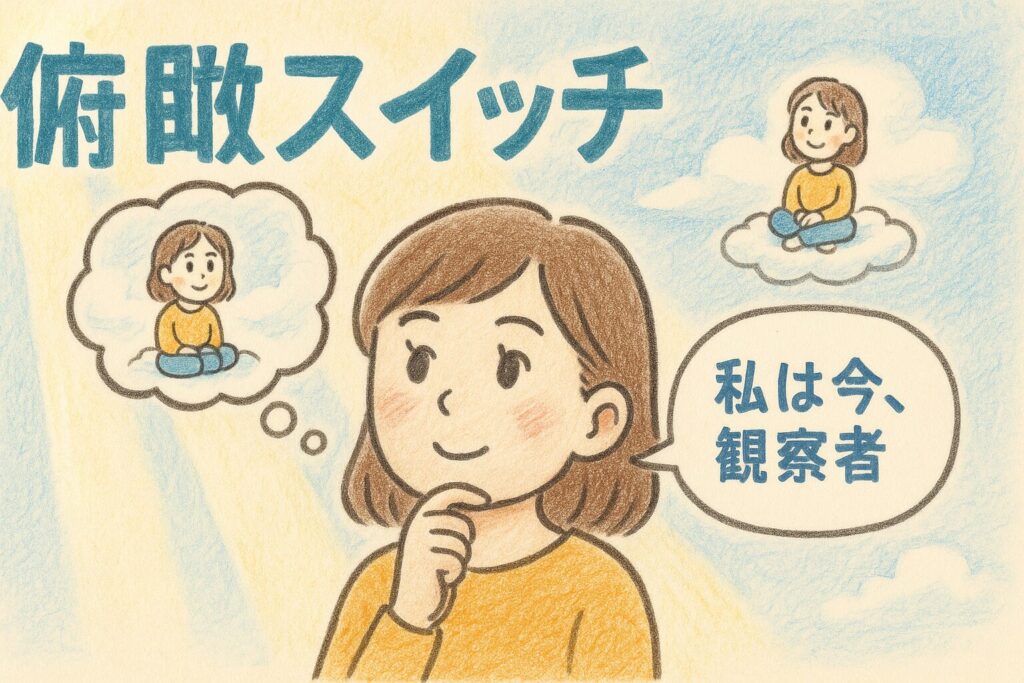
② 起こりやすい場面を知って備える
近しい人 × 公の場(家族のスピーチ、友人のプレゼン、子どもの発表会…)はハイリスク。
あらかじめ「俯瞰スイッチ」を準備しておくだけで、当日の動揺が小さくなります。
③ 後からの整え方
日記に3行だけ書き分けてみましょう。
事実(何があったか)
解釈(自分がどう感じたか)
望み(次はどうしたいか)
👉 自分と相手の境界を言葉で整理することで、「後から思い出して赤面…」を防ぎやすくなります。
注意点や誤解されがちな点
これは病名ではありません
共感性羞恥は、一般に心理現象として説明されます。診断名ではありません。名称だけが独り歩きして「自分は弱いからだ」と決めつける必要はありません。
対応法:ラベルを“性格判定”に使わない。「誰にでも起こりうる社会的感情」と言い換えて、自分を責める言葉を控える。
“見下し”とは真逆の感情です
他人の不幸で快を得るシャーデンフロイデ(独語:Schadenfreude)とは別物です。共感性羞恥は、相手に自分を重ねることで生じる“痛み寄り”の反応です。
対応法:その“痛み”は思いやりの副産物だと再定義する(自己批判を弱める)。
観察者羞恥との線引き(混同しやすい)
共感性羞恥:相手本人も恥ずかしい → その感情に同調して自分も赤面。
観察者羞恥:相手本人は平気でも → 状況の気まずさで自分が赤面。
国際論文では主にvicarious embarrassment が用語として使われますが、文脈により2つを使い分けます。
🔑 2つの用語と読み方
empathic embarrassment(エンパシック・エンバラスメント)
英語の学術文献で使われる用語。
意味:相手が本当に恥ずかしがっているとき、その感情に共感して自分も恥ずかしくなる。
日本語では → 「共感性羞恥」 とほぼ一致。
vicarious embarrassment(ヴァイケリアス・エンバラスメント)
英語圏では「代理的な恥」「もらい恥」と訳される。
意味:相手本人が恥ずかしがっていなくても、状況を見ている自分が恥ずかしいと感じてしまう。
日本語では → 研究紹介の中で便宜的に 「観察者羞恥」 と訳されることがある。
⚠️ 注意点
英語圏の論文では、vicarious embarrassment という言葉の中に 両方の現象(相手が恥ずかしい場合も/そうでない場合も) を含めて使うことが多いです。つまり、日本語で「共感性羞恥」「観察者羞恥」と分けているのは、主に日本語圏で説明をわかりやすくするための区別。
対応法:まず状況診断:「本人は恥じている? いない?」→ 対応を選ぶ。
本人が恥じている(共感性羞恥):支える振る舞い(うなずき・拍手・視線の逃げ道づくり)。
本人が平気(観察者羞恥):俯瞰に切り替え、状況を“演出”として眺める。
強くしんどい時の“その場の対処”
俯瞰スイッチ:頭上から自分を見るイメージを言語化(「私は今、観察者」)。
研究では、第三者視点の採用が“恥ずかしさ回避”を和らげることが示されています。
支え行動に置き換え:小さな応援・穏やかな拍手・視線を外して逃げ道を確保。
環境を1つ整える:深呼吸、飲み物、席の位置調整など“身体側”から落ち着かせる。
再燃を防ぐ“あとからの整え方”
3行メモ:①事実 ②自分の解釈 ③望み を分け書き。
自他の境界を言語化すると、あとからの“再赤面”が起きにくくなります。
個人差と文化差を前提に
近しい人ほど強く起きやすい(社会的近さ)。
個人の共感特性が高いほど強まる傾向(ACC・前島の活動と関連)。
恥の感じ方・ロボットへの態度には文化差も影響します。
受診の目安:日常生活に支障が出るほど苦しい/回避が増えている—こうした場合は、早めに専門家へ相談してください(不安症・社交不安など他の要因が背景にあることもあるため)。
おまけコラム
——ロボットにも“もらい恥”は起きる?
どんな研究?誰が提唱?
2023年、Harin Hapuarachchi(ハリン・ハプアラッチ)氏らのチーム(富山大ほか)が『Scientific Reports』に発表。VR環境で、人型アバター(人間)とロボット・アバターが“恥ずかしい場面/恥ずかしくない場面”に直面する映像を見せ、参加者の自己報告(共感的羞恥・認知的共感)と皮膚電気反応を測定しました。
あわせて、EurekAlert! など科学ニュースもこの研究をわかりやすく紹介しています。
何が分かった?(結果のポイント)
恥ずかしい場面では、人間アバターでもロボットアバターでも、共感的羞恥も認知的共感も上昇。
認知的共感は人間アバターの方が高い(“ロボットは心を持たない”という素朴理論の影響が示唆)。
皮膚電気反応(発汗指標)は人間アバターの方がやや高い傾向だが、今回のサンプルでは有意差は限定的。
“もっと人間らしく見える”こと(刺激の説得力=プラウジビリティ)が差の一因かもしれない。
⇒ 総じて、ロボットを見ても“もらい恥”に近い反応が起きうることが示されました。
研究の注意点:VR・アバターという条件、サンプルサイズ、皮膚反応の有意性は限定的(著者も限界として明記)。「人間≒ロボット」だと主張しているのではなく、“ロボットに対しても一定レベルの共感的羞恥が生起し得る”**ことを示した段階です。
どう活かす?
HRI(人とロボットのインタラクション)設計
公共空間でロボットが“気まずい行為(失敗・規範逸脱)”をすると観客側がもらい恥で不快になり得る。
→ 失敗演出の頻度・見せ方に配慮/回避不能の“公開赤っ恥”を避けるUI設計。
VRトレーニング
俯瞰スイッチの練習素材として、恥ずかしい場面を安全に再体験し、第三者視点の採用を訓練する(観察者としての練習)。
教育・医療
対人恐怖や過度の“恥回避”が強い人の曝露・リフレーミングの低強度教材として活用の余地。
恥は、社会を保つセンサーです。
近しい人ほど胸が痛み、知らない人でも場が凍れば頬が熱い。
それは弱さではなく、つながりの証。
俯瞰して観る力と、支える手をそっと差し出す勇気があれば、
あなたの“もらい恥”は、人の尊厳を守る力に変わります。
VRのロボットが示してくれたのは、
私たちの心は“人間そのもの”だけでなく、恥を想像させる意図にも反応するという事実。
だからこそ、設計も、教育も、ふるまいも、やさしさ前提で選びましょう。
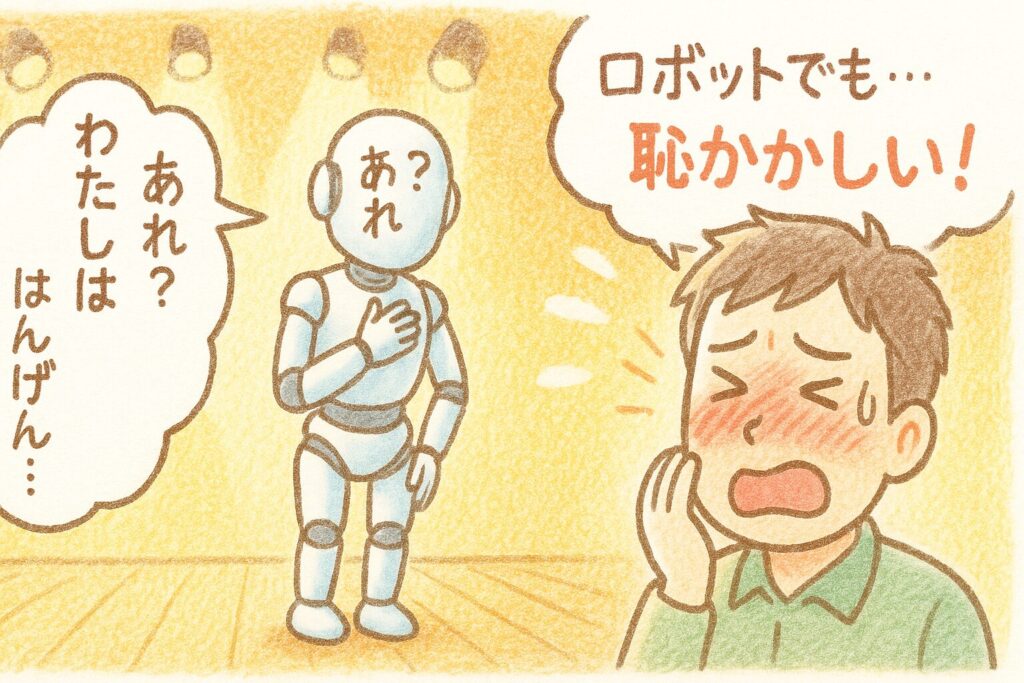
まとめ・考察
まとめ
共感性羞恥は、
近しい人ほど起こりやすい
共感性の高さや社会的評価への敏感さと結びついている
恥の共有は「社会を円滑にする感情のセンサー」
ということが、心理学や脳科学の研究で明らかになっています。
つまりこれは「弱さ」ではなく、人が人と共に生きるための自然な反応なのです。
考察
共感性羞恥は、他者の失敗を「自分の痛み」として受け止める仕組み。
これは人間関係を守るセンサーであり、
「恥を共に感じること」は、実は思いやりの証なのかもしれません。
カラオケで“もらい恥”を感じたら、先に自分がちょっと外して歌ってみる。
そうすれば場が和み、相手も救われ、自分の緊張も軽くなる。
👉 「自分を少し笑いの装置にする」ことで、場をやさしく着地させることができるのです。
想像してみましょう
「共感性羞恥を意識して生活したら、家族の“失敗”に過剰反応せず、むしろ温かく支えられる余裕が生まれた」
——そんな経験をした人もきっといるはずです。
👉 あなたなら、この“もらい恥”をどう活かしますか?
今日から一度だけでも「俯瞰スイッチ」を試してみませんか。
更に学びたい人へ
おすすめ書籍
『NVC 人と人との関係にいのちを吹き込む法 新版』
著者:マーシャル・B・ローゼンバーグ(Marshall B. Rosenberg)
アメリカの心理学者、臨床心理士。非暴力コミュニケーション(NVC)の提唱者。
出版元:日本版は 日本経済新聞出版(旧:日本経済新聞社/2021年新版)
本の特徴:「共感をベースにしたコミュニケーション」を、実際の対話例やワーク形式で紹介。怒り・恥・葛藤といった感情にどう向き合い、言葉にするかを平易に説明。
おすすめの理由:共感性羞恥のように「相手の恥ずかしさを自分が抱えてしまう」現象は、境界線と共感の扱い方が鍵。本書を通じて「他者に寄り添いながらも自分を保つ」技術が学べるため、日常での“もらい恥”対処に直結します。
『感情心理学・入門〔改訂版〕 (有斐閣アルマ)』
著者:大平英樹(おおひら ひでき) 編
名古屋大学大学院環境学研究科教授。感情心理学・健康心理学の専門家。
出版元:有斐閣
本の特徴:感情心理学の入門書として大学でも広く使われているテキスト。感情の定義・種類(喜び、怒り、羞恥、罪悪感など)を学術的に整理。基礎理論から応用までカバーし、心理学的に「感情とは何か」を体系的に学べる。
おすすめの理由:共感性羞恥は“社会的情動”の一つ。本書で羞恥や共感が心理学の中でどう位置づけられているかを知ることで、現象を「病気」ではなく「心理現象」として理解する視点が得られます。
『情動はこうしてつくられる──脳の隠れた働きと構成主義的情動理論』
著者:リサ・フェルドマン・バレット(Lisa Feldman Barrett)
米ノースイースタン大学心理学教授。情動研究の世界的第一人者。
翻訳:高橋 洋(監訳・翻訳者)
出版元:紀伊國屋書店(2019年邦訳出版)
本の特徴:最新の脳科学・心理学に基づき、「感情は脳が構成するもの」という構成主義的情動理論を提示。感情は生得的な反射ではなく、経験・文脈・文化に応じて“つくられる”と説明。
おすすめの理由:共感性羞恥は「なぜ同じ場面でも人によって強さが違うのか」という個人差が大きい現象。本書の理論を知ることで、「恥ずかしさも脳の解釈で生み出される」ことが理解でき、共感性羞恥を科学的に俯瞰する力がつきます。
| レベル | 書籍名 | 出版元 | 特徴 | 今回おすすめの理由 |
|---|---|---|---|---|
| 初学者 | 『NVC 人と人との関係にいのちを吹き込む法 新版』 | 日本経済新聞出版 | 共感的コミュニケーションの実践書 | 共感性羞恥の対処に直結する“境界と支え方”が学べる |
| 中級者 | 『感情心理学・入門〔改訂版〕』 | 有斐閣 | 感情心理学の標準テキスト | 現象を病気でなく心理学的情動として理解できる |
| 全体 | 『情動はこうしてつくられる』 | 紀伊國屋書店 | 脳科学に基づく最新感情理論 | 恥の個人差・文化差を「脳の解釈」として整理できる |
📚 この3冊を組み合わせることで、
👉 「日常の実践(NVC)」+「心理学の基礎(感情心理学)」+「脳科学的理解(情動理論)」
という 三層構造の学び ができ、共感性羞恥を多角的に理解できるようになります。
疑問が解決した物語
あの日のカラオケ。
お母さんが音程を外した瞬間に、
あなたの胸まで熱くなったのは——偶然ではありません。
それは 『共感性羞恥』。
大切な人の赤面を、自分の心が映しとる不思議な鏡。
弱さではなく、やさしさの証。
「一緒に舞台に立つよ」と、心がそっと差し出した共鳴の灯り。
——もらい恥は、もらい心。
その瞬間、あなたとお母さんは、恥を分け合うことで確かにつながっていたのです。
「共感性羞恥——それは、恥をわかち合うことで心を近づける、小さな奇跡なのです。」
✍️ 締めの文章
私たちがふと感じる「もらい恥」は、弱さの証ではなく、
人と人とのつながりを映す感情のセンサーです。
大切な誰かの失敗に心が揺れるのも、知らない人の場面で胸が熱くなるのも、
あなたの中にある「共感する力」が働いているから。
今日からほんの少し、俯瞰スイッチを試したり、
相手をそっと支える小さな行動をしてみてください。
それは、あなた自身を守りながら、周りの人を安心させる力にもなります。
本記事が、あなたの「もらい恥」との付き合い方を見直すきっかけとなり、
感情をやさしく見つめる入り口となれば幸いです。
補足注意
ここで紹介した内容は、学術研究や信頼できる資料をもとに整理していますが、
感じ方やとらえ方には個人差があります。
研究が進むことで、新たな発見や別の見方が加わる可能性もあります。ここで紹介した内容がすべての人に当てはまるわけではありません。
強い苦痛や生活への支障が続く場合は、公的な相談窓口や専門機関に早めにご相談ください。
🧭 本記事のスタンス
どうか「これが唯一の正解」ではなく、
「自分で調べ、考え、日常に活かすための入り口」として受け止めてください。
さまざまな立場や視点も、ぜひ大切にしてください。
もらい恥が知への“もらい火”になりますように。
小さなきっかけから、もっと深い文献や研究に触れて、学びを広げてみてください。

📌 最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました。
🌱 最後にひとこと:
「もらい恥」は弱さではなく、他者と心を共有できる力の証。
学べば学ぶほど、その優しさの意味が見えてきます。
そして——
この“共感性羞恥”という小さな恥の共有が、 あなたと誰かを優しくつなぐ力になりますように。







コメント