人を助けたあとだけ訪れる「クタクタなのに心は軽い」不思議な感覚──その名前と科学的なしくみ、そして日常での活かし方をやさしくひもときます。
ボランティアのあとだけスッキリする不思議?その気持ちよさの正体は『ヘルパーズ・ハイ(人助けの幸福感)』でした
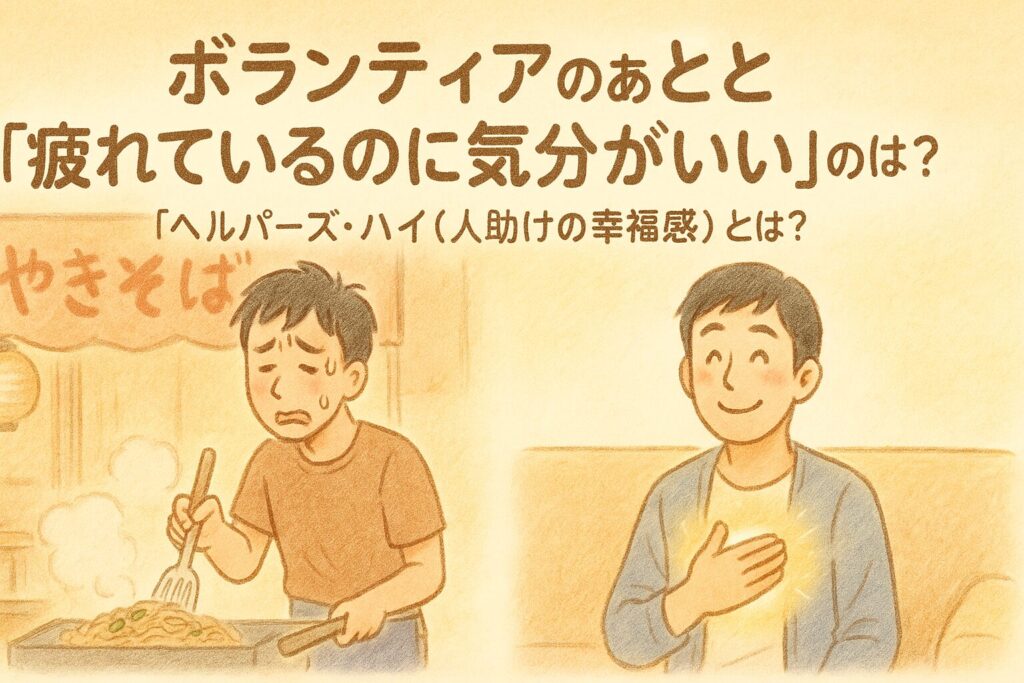
代表例
仕事が終わったあと、ヘトヘトになりながら
子ども会の「夏祭り」の手伝いに参加したとします。
焼きそばを焼いたり、かき氷を配ったり、
人混みの中で立ちっぱなし。
汗だくになって「来年はもういいかな…」と思うくらい大変でした。
それなのに、家に帰ってシャワーを浴びるころには、
なぜか 心の中だけはスっと軽くなっている。
「すごく疲れたのに、気持ちだけはなぜかスッキリしてる…」
この“ちぐはぐ”な感覚。
これが、今回のテーマとなる不思議な現象です。

3秒で分かる結論
結論:
ボランティアのあとだけスッキリするのは、
『ヘルパーズ・ハイ(人助けの幸福感)』と呼ばれる
“人を助けたあとに脳が感じるごほうび反応”が起きているからです。
人の役に立ったと実感したとき、
脳の中で「うれしい!」を感じる物質が分泌され、
その結果として「疲れているのに気持ちいい」という
不思議なスッキリ感が生まれます。
小学生にもスッキリわかる結論
「大変なお手伝いをしたあと、
なんだか胸の中があったかくて、いい気分になるのは
脳が『よくがんばったね!』ってごほうびをくれているから」
・ゴミひろいを手伝ったとき
・クラスメイトを助けたとき
・募金のお手伝いをしたとき
人の役に立つことをすると、
脳の中で「うれしいスイッチ」がオンになって、
気分がパッと明るくなる。
この「人を助けたあとだけ起きるうれしい気持ち」のことを
『ヘルパーズ・ハイ』 と呼びます。
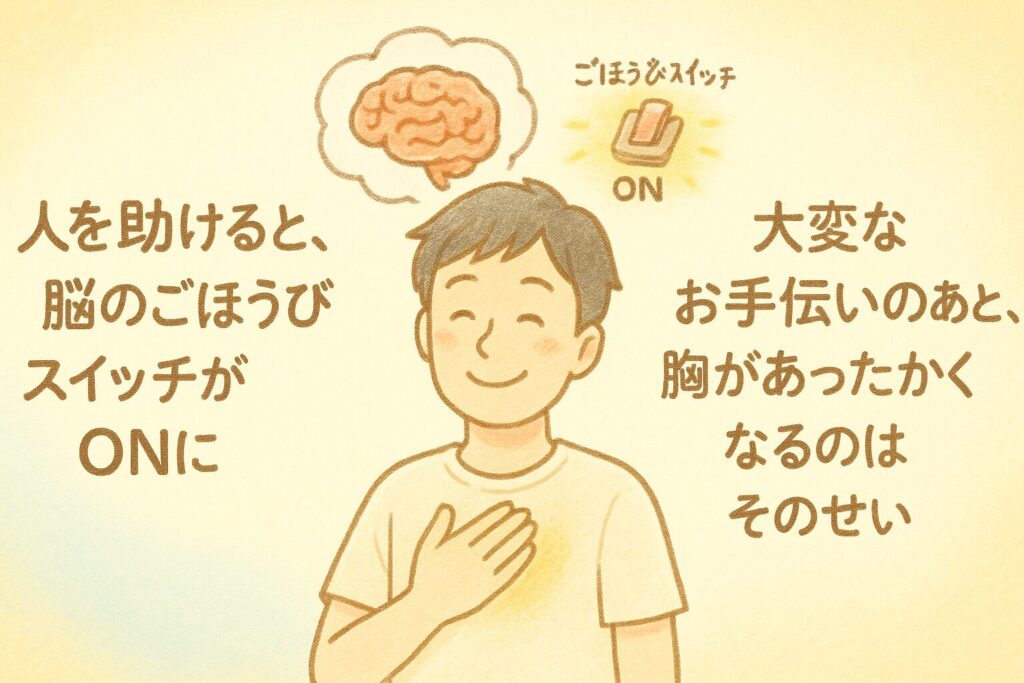
今回の法則の「よくある疑問」キャッチフレーズ集
- ボランティアのあとだけ元気になるのはどうして?
―『ヘルパーズ・ハイの法則』とは? - しんどいのに、また手伝ってもいいかなと思うのはなぜ?
―『人助けの幸福感』のしくみとは? - 「自分のため」より「人のため」に動いたときのほうが
心がスッキリするのはなぜ?
―脳のごほうびシステムのナゾとは?
この「なんで?」に、
この記事全体を通して答えていきます。
1. 今回の現象とは?
「大変なのに、終わったら気持ちいい」あの不思議
行く前は正直おっくうな、地域のごみ拾い。
立ちっぱなしでクタクタになる、イベントのボランティア。
仕事終わりのPTAや町内会の手伝い。
やっている最中は
「早く帰りたいな……」
「なんで引き受けちゃったんだろう…」
と、心の中で何度もつぶやいてしまうのに、
家に帰って一息つくと、なぜか 心がふわっと軽くなっている。
「このようなことはありませんか?」あるある例
- 道案内あるある
急いでいるのに、道に迷っている観光客に声をかけて
行き先を一緒に調べてあげた。
別れたあと、なぜかちょっと誇らしい気持ちになる。 - 募金・寄付あるある
コンビニのレジ横の募金箱に、
おつりの小銭を入れたあと、
胸のあたりがじんわり温かくなる。 - クラス・職場の助け合いあるある
困っている友だちや同僚の作業を少し手伝ったら、
その日一日は、少しだけ気分がよく過ごせる。 - 家族サポートあるある
家事で疲れている家族の代わりに
ゴミ出しや皿洗いを引き受けたら、
「いいことしたな」と自分までうれしくなる。
どれも「お金をもらったわけではない」のに、
なぜか心の中だけはプラスになっている――
これが今回の現象です。
この記事を読むメリット
この記事を読むことで、
- なぜボランティアや親切のあとに、
「疲れているのにスッキリする」 のかがわかる - その気持ちよさ(ヘルパーズ・ハイ)を、
日常のストレス軽減や気分転換に活かすヒント が得られる - 「自分ばかり損している?」というモヤモヤが減り、
人のために動くことを前向きにとらえやすくなる
といったメリットがあります。
「毎回しんどいのに、終わったあとはなぜか気持ちいい」
この不思議な現象の名前と仕組みを、
これから一緒に見ていきましょう。
2. 疑問が浮かんだ物語
舞台は、日曜日の朝。
主人公のユウタさんは、友人の引っ越しを手伝うために、
眠い目をこすりながら電車に乗っていました。
本当は、久しぶりの休み。
「今日は家でゆっくりゲームでもしたかったな…」
そんな本音を胸にしまい込み、「まあ、頼まれたしな」と
少しだけ重い足取りで待ち合わせ場所に向かいます。
──いざ作業が始まると、想像以上の重労働です。
大きな段ボールを何往復も運び、
本棚や家電を持ち上げるたびに、腕も腰も悲鳴をあげます。
「うわ、これマジでキツい…」
「なんでこんな重い本、こんなにあるの…?」
心の中では、何度も弱音がよぎります。
汗はじっとり、Tシャツは背中までぐっしょりです。
それでも、作業が終わって
最後の段ボールを運び終えたとき。
友人が、ほっとした顔でこう言いました。
「ほんと助かったよ。ユウタが来てくれなかったら
まだ終わってなかったと思う。ありがとう!」
その瞬間、ユウタさんの胸のあたりに、
じんわりとあたたかいものが広がります。
帰り道の電車の中。
座席に腰を下ろした途端、全身の疲れがどっと押し寄せてきました。
「腕も脚もパンパンだし、正直ヘトヘトだな…」
そう思いながらも、
ふと、心の中を見つめてみると気づきます。
「あれ? 体はぐったりなのに、
気持ちだけはスッキリしてる…?」
さっき見た、友人の安心した笑顔。
「助かったよ」「ありがとう」という言葉。
それらが何度も頭の中でリピートされるたびに、
胸の奥から、ふわっとあたたかい風が吹いてくるような感覚があります。

「なんでだろう? しんどいはずなのに、嫌な感じじゃない」
「むしろ、ちょっといいことしたなって気分になってる…」
「この“クタクタなのにスッキリしてる感じ”、いったい何?」
そうやって、ユウタさんの心には
「この不思議な気持ちの正体を知りたい」という
小さな“謎解き欲”が芽生えます。
この「疲れているのに、心だけ晴れているような感覚」。
意外と身近にあるこの不思議な現象の正体を、
次の段落で一緒に探しに行きましょう。
3. すぐに分かる結論
お答えします
ユウタさんが感じた
「大変だったのに、心だけスッキリしている」不思議な感覚。
この正体は、心理学の世界で
『ヘルパーズ・ハイ(Helper’s High)』 と呼ばれている、
“人助けをしたあとに起こる特別な幸福感” です。

浮かんだ疑問への「ざっくり答え」
Q. どうして、人を手伝ったあとのほうが気分がよくなるの?
→ 誰かの役に立てた、と実感したとき、
脳は「これはいい行動だよ!」というサインを出します。
そのとき、ドーパミンなどの「うれしい物質」が分泌され、
疲れているのに心が軽く感じる という不思議な状態が生まれるのです。
Q. 引っ越しみたいにしんどいのに、また手伝ってもいいかなと思うのはなぜ?
→ 脳の中に刻まれた「感謝された」「役に立てた」という記憶が、
“ごほうびの思い出” として残るからです。
そのおかげで、
「大変だったけど悪くなかったな」
「また頼まれたら、ちょっとは力になってもいいかも」
と、心が前向きに感じやすくなります。
Q. 自分のためにだけ頑張ったときと、どこが違うの?
→ 研究では、
「自分のためだけに使う時間」よりも、
「人のために使った時間」のほうが、
幸せ感や心の満足感が高まりやすい ことが示されています。
つまり、
「相手の笑顔」がプラスされるぶんだけ、
心の中のエネルギーの満タン度が違う のです。
ここまでの話を、一言でまとめると……
「人のために動くと、脳と心が“ありがとう”と反応して、
体はくたびれているのに、気持ちだけごほうびをもらえる」
ということです。
ただ、ここで新しい疑問が出てきますよね。
- なぜ、私たちの脳には
「人助けをすると気持ちよくなる仕組み」が
最初から組み込まれているのか? - どんな親切なら、ヘルパーズ・ハイが起こりやすいのか?
- やりすぎたり、無理をしすぎたりすると、
逆に心や体が疲れきってしまうことはないのか?
こういった“もう一段深いナゾ”は、
まだ解き明かされていないままです。
もっと詳しく知りたいあなたへ
今回の現象には「ヘルパーズ・ハイ」という名前があり、
大まかな仕組みも見えてきました。
でも、ヘルパーズ・ハイは
ただの「いい気分」ではありません。
- 脳のごほうびシステム
- 心の健康やストレスとの関係
- そして、人とのつながり方や生き方そのもの
こうしたものとも、深く結びついていることが
心理学や脳科学の研究から少しずつわかってきています。
「この不思議な“人助けの幸福感”の中身を、
もうちょっとちゃんと知ってみたい」
そう感じた方は、
この先の段落で、ヘルパーズ・ハイの仕組み・歴史・実生活への活かし方を
一緒にじっくりひも解いていきましょう。
きっと、
「誰かを助けること」と「自分の幸せ」のつながり方 が、
今より少しクリアに見えてくるはずです。
4.『ヘルパーズ・ハイ』とは?
『ヘルパーズ・ハイ(Helper’s High』のシンプルな定義
人を助けたり、親切にしたあとに感じる
“あたたかくてスッキリした幸福感”
を指す言葉です。
1980年代にアメリカの心理学者・社会活動家の
**アラン・ラックス(Allan Luks/アラン・ラックス)**が、3,000人以上のボランティアを調査した研究で提唱した概念だとされています。
ラックスは、ボランティアをしている人の多くが
- 強い高揚感(ワクワクした感じ)
- 深い落ち着き(ふしぎな安心感)
- ストレスの軽減や健康感
などを感じていることを報告し、
この独特の“ハイな感覚”を 「ヘルパーズ・ハイ」 と名付けました。
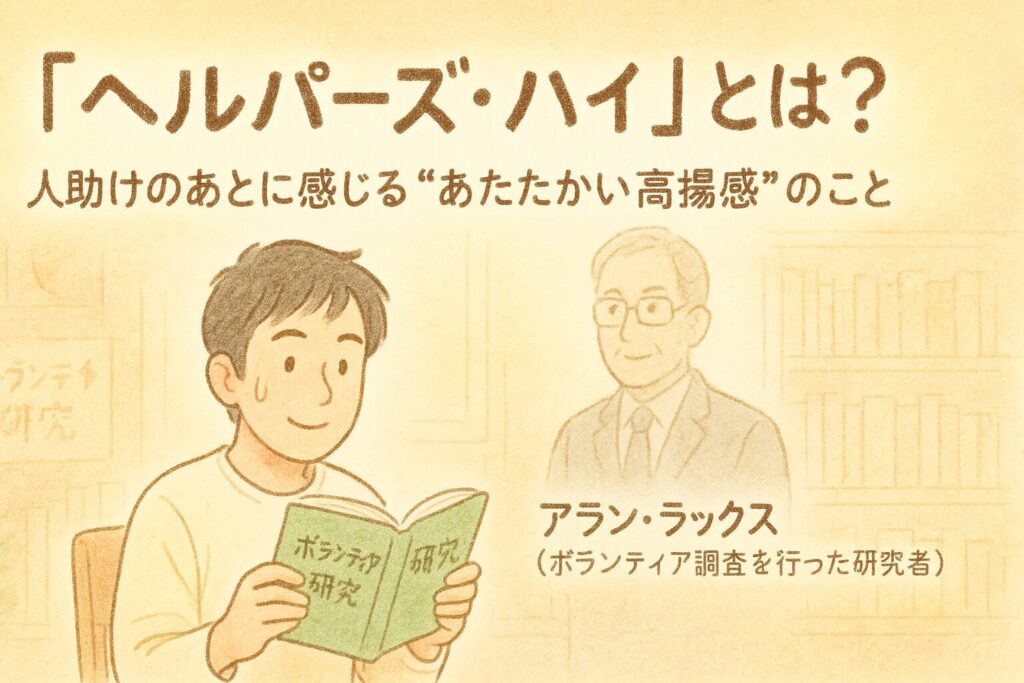
科学的にはどんな状態?
その後の研究や医療機関の解説では、
ヘルパーズ・ハイは次のような「脳と体の反応」と結びつけて説明されています。
- **報酬系(ほうしゅうけい)**と呼ばれる
脳の「ごほうび回路」が活性化する - そのとき、
- ドーパミン(うれしい・やる気のホルモン)
- エンドルフィン(天然の痛み止めのような物質)
- オキシトシン(きずなホルモン)
- セロトニン(気分を安定させる物質)
などが増えると考えられている
- その結果、
- 気分が明るくなる
- ストレスがやわらぐ
- 自分への信頼感(自己肯定感)が少し上がる
という、心身のプラスの変化が起こる——
これが「ヘルパーズ・ハイ」の大まかなイメージです。
ポジティブ心理学から見たヘルパーズ・ハイ
ポジティブ心理学の研究者
ソニア・リュボミアスキーらは、
約473人を対象に6週間の実験を行い、
- 「他人や社会のために親切をするグループ」
- 「自分を喜ばせることをするグループ」
- 「いつも通りに過ごすグループ」
を比べました。
その結果、
人のための親切だけが、
幸福感(フラリシング=よく生きている感覚)を
有意に押し上げた
ことが示されています。
つまり、
「人のために動くと気持ちが上がる」という
私たちの“体感”は、
心理学的にも裏づけがある、ということです。
名前の意味と、今の使われ方
- Helper(ヘルパー)…助ける人
- High(ハイ)…気分が高ぶる状態
なので、直訳すると
「人助けをしたときのハイな状態」 です。
今では、
- ボランティア団体の紹介記事
- 心理学・ポジティブ心理学の本
- 医療・メンタルヘルス系のブログ
などで、
「人のために何かすると気持ちがよくなる現象」
の総称として、広く使われています。
ここまでで、「ヘルパーズ・ハイとは何か?」という
名前と中身のイメージはつかめてきたと思います。
次は、
「どうして人を助けると、
私たちの脳は“ごほうび”をくれるのか?」
という 背景(なぜそんな仕組みがあるのか) を
一歩深く見ていきましょう。
5. なぜ注目されるのか?
背景・重要性
① 「人助け=生き残るための戦略」という見方
人間は、一人では生きていけない生きものです。
進化心理学や社会神経科学では、
助け合う集団のほうが、生き延びやすかった
という考え方が重視されています。
この視点から見ると、
- 助け合う
- 協力する
- 分け合う
といった行動に「気持ちよさ」というごほうびを付けることで、
人間の脳は、“助け合う社会”を維持しようとしている
とも考えられます。
② 脳の「ごほうび回路」が光るから
脳の中には
**「報酬系(ほうしゅうけい)」**と呼ばれる
ごほうび回路があります。
とくに
- 腹側線条体(ふくそくせんじょうたい)
- 側坐核(そくざかく)
- 内側前頭前野(ないそくぜんとうぜんや)
などが含まれる
**メソリムビック経路(報酬系のネットワーク)**は、
- おいしいものを食べたとき
- 欲しかったものを買ったとき
- ゲームで勝ったとき
などに反応して「うれしい!」を生み出す場所です。
fMRI(エフエムアールアイ:機能的MRI)を使った研究では、
寄付や募金のような「人のためのお金の使い方」をしたときにも、
この報酬系が光る
ことがわかっています。
つまり、
「自分のためのごほうび」と
「人のための親切」は、
同じ“快楽回路”を使って
気持ちよさを生み出している
ということです。

③ 心と体の健康への影響
医療機関や心理学の解説では、
- 親切やボランティアをする人は
ストレスホルモンの コルチゾール が低めになりやすい - エンドルフィンやドーパミンが増え、
「ヘルパーズ・ハイ」と呼べる高揚感を感じる - セロトニンやオキシトシンが増え、
不安や落ち込みがやわらいだり、
人への信頼感が高まりやすくなる
といった可能性が報告されています。
また、高齢者のボランティア参加と
寿命・健康状態の良さの関連を示す研究もいくつかあり、
「人を助けること」は、
メンタルだけでなく身体の健康とも関係していると考えられています。
④ 「なぜ、最初からこの仕組みがあるのか?」への答え
ここまでの話をまとめると、
- 助け合う集団は生き残りやすい
- そのため、「人を助ける=気持ちいい」と感じる脳になった
- その結果、
人は「助け合い」を繰り返しやすくなり、
社会全体も安定しやすくなった
という進化+脳科学のストーリーで
ヘルパーズ・ハイを説明することができます。
言いかえると、
「人を助けると気持ちよくなる」仕組みは、
私たちが長く生き延びるために
身につけてきた“生存戦略”の一部
というわけです。
ここまでで、ヘルパーズ・ハイが
- ただのキレイごとではなく
- 脳・心・社会の3つをつなぐ大事な現象
だということが見えてきました。
次の章では、
「じゃあ、どんな親切なら
ヘルパーズ・ハイが起こりやすいの?」
という疑問に、
具体的な生活場面の例をまじえてお答えしていきます。
6. 実生活への応用例
どんな親切でヘルパーズ・ハイが起きやすい?
ポイントは「自発的」「相手の顔が思い浮かぶ」「ちょうど良い負荷」
研究や実務の現場での話を整理すると、
ヘルパーズ・ハイが起こりやすい行動には
いくつか共通点があります。
ヘルパーズ・ハイが起こりやすい条件(ざっくり版)
- 自分の意思でやっている(自発的)
- 「やらされている」より
「自分で選んだ」ほうが起こりやすい
- 「やらされている」より
- 相手の顔が思い浮かぶ
- 誰に届くか分からないより、
具体的な顔や状況が想像できるほうが実感しやすい
- 誰に届くか分からないより、
- ちょっと大変だけど、やり切れる程度の負荷
- 楽すぎると“ハイ”になりにくい
- 逆に、つぶれるほど大変だと「消耗」になってしまう
- 「役に立った」と自分で感じられるフィードバックがある
- 「ありがとう」の一言
- 相手の表情の変化
- タスクが片づいた達成感 など
日常でできる、具体的な応用例
① 仕事・学校でのミニ助け合い
- 同僚の資料づくりを10分だけ手伝う
- 忙しそうな人の電話を代わりに取る
- クラスメイトのプリントを一緒に探してあげる
ポイントは、
「自分の時間をほんの少し、人のために分ける」
ことです。
② お金の使い方を“ちょっとだけ”人のために
研究では、
「自分のためにお金を使う」より
「誰かのためにお金を使う」ほうが
幸せ感が高まりやすいことが報告されています。
- 友達にコーヒーを1杯おごる
- 家族に小さなスイーツを買って帰る
- 少額をオンライン寄付してみる
など、無理のない範囲で“誰かのために使う”枠を
作ってみるのも一つの方法です。
③ ボランティアや地域活動での本格的な体験
- 地域の清掃活動
- 子ども会・PTAのイベント手伝い
- 災害支援やチャリティイベント
こうした活動は、
体力的にはきつくても
- 「一体感」
- 「やり遂げた感」
- 「感謝される体験」
がセットでやってきやすく、
強めのヘルパーズ・ハイを感じやすい場面です。

メリットと、ちょっとしたデメリット
メリット
- 気分転換やストレス軽減になる
- 「自分も誰かの役に立てる」という自己肯定感が育つ
- 人とのつながりが増え、孤立感がやわらぐ
デメリット(注意点)
- 「頼まれるがまま」にやり続けると、
心身が疲れ切ってしまう - 「いい人でいなきゃ」と無理をすると、
ヘルパーズ・ハイではなく「消耗モード」になる
“気持ちいいボランティア”と
“つらい自己犠牲”は紙一重
6.5Q&A/FAQ
ヘルパーズ・ハイに対するよくある疑問
Q1. ヘルパーズ・ハイって、どれくらい続くんですか?
人によってかなり差がありますが、
ボランティア直後〜その日のうちに強く感じることが多い
余韻は、数時間〜その日いっぱい続くこともある
と言われています。
ただし、
「30分きっかり」などの明確な時間が
研究で決まっているわけではありません。
大切なのは、
「あ、今ちょっと心が軽いな」
という自分の変化に気づけること
だと考えてみてください。
Q2. ランナーズ・ハイとヘルパーズ・ハイは同じものですか?
“仕組みは似ているけれど、きっかけが違う”
というイメージが近いです。
ランナーズ・ハイ
→ 長時間の運動でエンドルフィンなどが出て、気分が高まる現象
ヘルパーズ・ハイ
→ 人を助けたり、親切にしたときに、
ドーパミンやエンドルフィンなどが出て、
「クタクタなのにスッキリ」する感覚が生まれる現象
どちらも「脳内のごほうびシステム」が関わっていますが、
運動か、人助けか でトリガーが違う、と考えると分かりやすいです。
Q3. オンラインの寄付や、SNSで誰かを応援するだけでもヘルパーズ・ハイは起きますか?
起きる可能性はじゅうぶんあります。
ポイントは、
「この行動が、誰かの役に立っている」と
自分で実感できるかどうか
相手の顔や状況を、少しでもイメージできるかどうか
です。
信頼できる団体へのオンライン寄付
SNSで落ち込んでいる人に、ていねいなメッセージを送る
クラウドファンディングを少額支援する
といった行動でも、
「役に立てた実感」 があれば、
ヘルパーズ・ハイに近い感覚を味わえる人は多いです。
Q4. 毎日誰かに親切をしていたら、ヘルパーズ・ハイに慣れてしまいませんか?
「完全に効かなくなる」とまでは言いきれませんが、
同じことを機械的に繰り返す親切 は
慣れて効果が弱まりやすい
一方で、
意識して「今日はこれをやろう」と決めた親切は
ポジティブな影響が出やすい
と示唆する研究もあります。
おすすめは、
いつも同じことだけをするのではなく、
小さな親切の内容に 変化 をつける
「ちゃんと相手を見て選ぶ」感覚を大事にする
というやり方です。
「ノルマ」のように感じ始めたら、
一度立ち止まって休んでOKです。
Q5. ヘルパーズ・ハイは、うつ病や不安の“治療”になりますか?
いいえ、「それだけで治る魔法の方法」ではありません。
人を助けることが、気分の浮上や自己肯定感アップの
助けになる可能性 はあります
しかし、うつ病・不安障害などの治療は、
医師や専門家の診断とサポートが基本です
すでに心がとてもつらい状態にある場合は、
まずは医療機関・相談窓口などに
しっかり頼ること
を最優先にしてください。
そのうえで、心や体の状態に余裕が出てきたら、
「ちょっとだけ誰かの役に立ってみる」ことを
補助的なセルフケアとして取り入れるイメージが安全です。
Q6. 人付き合いが苦手な人や、内向的な人でもヘルパーズ・ハイは感じられますか?
はい、感じられます。
ヘルパーズ・ハイは
「大勢とワイワイする人だけのもの」
ではありません。
手紙を書く
誰かの資料をこっそり分かりやすく整えておく
家族の家事を一つだけ肩代わりする
など、一対一・静かな親切 でも十分です。
大事なのは、
自分のペースを守ること
無理に“社交的な自分”を演じないこと
です。
「これなら自分でもやれそうかな?」と思える小さな行動から、
ためしてみてください。
Q7. 子どもにもヘルパーズ・ハイは起こりますか?
起こると考えられます。
友だちを手伝えたときの誇らしさ
おつかいを頼まれて「ありがとう」と言われたときのうれしさ
などは、まさに 子ども版ヘルパーズ・ハイ と言えます。
言葉として「ヘルパーズ・ハイ」を知らなくても、
「誰かの役に立てた」「喜んでもらえた」
という経験が、
子どもの自己肯定感や人への信頼感を育てていきます。
親や大人が、
「今の、すごくいいことだったね」
「あの子、助かってうれしそうだったよ」
とことばにしてあげると、
その感覚が記憶に残りやすくなります。
Q8. 「立派な動機」がないと、ヘルパーズ・ハイは起きませんか?
いいえ、立派なスローガンは不要です。
「頼まれたから」「なんとなく」「断りきれなくて」
から始まった行動でも、
結果として「役に立てた」「喜ばれた」と実感できれば、
ヘルパーズ・ハイは十分起こりえます。
大切なのは、
自分にとっても
相手にとっても
「悪くないな」と思える行動かどうか。
完璧な善意でなくて大丈夫です。
そのぶん気楽に、“そこそこ親切” くらいから始めてみてください。
次の章では、誤解されがちな点と注意ポイントを
しっかり整理していきます。
7. 注意点や誤解されがちな点
ヘルパーズ・ハイは魅力的ですが、
いくつかの「落とし穴」もあります。
① .1「やりすぎる」とハイどころか燃え尽きる
心理学や臨床の現場では、
- 介護職
- 医療者
- 教育・支援職
など「人を助ける仕事」の人ほど、
**バーンアウト(燃え尽き)**や
**コンパッション・ファティーグ(共感疲労)**を
起こしやすいことが指摘されています。
ヘルパーズ・ハイがあるからといって、
「自分を犠牲にしてでも
とにかく助けまくればいい」
という話ではありません。
・体調が悪いのに無理をする
・限界を超えても断れない
といった状態が続くと、
- ストレスホルモンが増え
- 眠れなくなり
- やる気がなくなる
など、逆に 心身の不調につながるリスクがあります。
①.2「やりすぎ」の反対側にある、“慣れ”の落とし穴
ヘルパーズ・ハイには、「やりすぎて燃え尽きる」以外にも、
もうひとつ気をつけたいポイントがあります。
それが、“慣れ(なれ)”の問題 です。
心理学の研究では、
- 同じ行動をくり返しすぎると
- その行動から得られる「新鮮なうれしさ」が
だんだん小さくなっていく
という “ヘドニック・アダプテーション(快楽への慣れ)” と呼ばれる現象が、
いろいろな場面で指摘されています。
親切やボランティアでも、
- いつも同じ内容だけを
- 「なんとなく惰性(だせい)」で続けていると
最初のころに感じていた
「あ、今日はちょっと心が軽い」
「なんだか胸がポカポカする」
といった ヘルパーズ・ハイ特有の感覚が、薄くなっていく 場合があります。
これは、
- あなたが悪いからでも
- 親切が意味を失ったからでもなく、
脳が「このごほうびにはもう慣れたよ」と判断しているだけ
と考えると分かりやすいかもしれません。
② 「見返りを感じる=偽善」ではない
よくある誤解が、
「ヘルパーズ・ハイって、
けっきょく“自己満足”じゃないの?」
というものです。
しかし、多くの研究は
- 「相手のため」に行動することで
「自分も元気になる」 - その相乗効果で、
社会全体のつながりも強くなる
という、Win-Winの構造を示しています。
「うれしい」と感じること自体は
人間としてごく自然な反応です。
ポイントは、
「その喜びを、自分だけの利益に閉じ込めるか」
「次の親切につなげていくか」
という 使い方の問題 だと考えられます。
③ 「やりがい搾取」に使われる危険性も
日本語のブログやビジネス書の中には、
ヘルパーズ・ハイに触れつつ、
「“やりがい”の名のもとに、
低賃金・長時間労働を押しつける
“やりがい搾取”には注意」
と警告しているものもあります。
- 「ボランティアだからタダで当然」
- 「好きでやっているんでしょ?」
といった態度で、
構造的な不公平や搾取が隠されてしまうと、
それはもはや「健康的なヘルパーズ・ハイ」ではなく
疲弊と不信感の源 になってしまいます。

④ 誤解しないための「3つのセルフチェック」
- 自分の生活や健康を壊してまでやっていないか?
- やっていて、あとから「怒り」や「虚しさ」ばかりが残らないか?
- 断る自由を、自分にちゃんと許しているか?
この3つに「はい」と答えられる範囲での
人助けであれば、
ヘルパーズ・ハイは心強い味方になってくれます。
ここまでで、
ヘルパーズ・ハイの “光”と“影” を
ざっくり押さえることができました。
次の章では、
もう少し視点を変えて、
「見ているだけでうれしくなる親切」
「体の中で何が起きているのか」
といった“おまけの深掘りコラム”として、
より専門的なお話をやさしく見ていきます。
8. おまけコラム
「見るだけでもうれしい? ヘルパーズ・ハイの周辺現象」
① 見ているだけで、こちらもあったかくなる理由
実は、
誰かが親切にしている場面を見ているだけ
でも、
- 心がじんわり温かくなる
- 「自分も何かしたくなる」
という現象が起こることが報告されています。
これは、脳の中で
- 他人の感情や行動を“なぞる”働き
- 「自分ごとのように感じる」共感のネットワーク
が動いているためだと考えられています。
② ランナーズ・ハイと似ている「脳内カクテル」
ヘルパーズ・ハイは、
よく ランナーズ・ハイ と比較されます。
- ランナーズ・ハイ
→ 長時間の運動でエンドルフィンなどが出て
気分が高揚する状態 - ヘルパーズ・ハイ
→ 人助けや親切で、
同じような「脳内カクテル」が生まれる状態
医療機関の解説でも、
親切やボランティアによって
エンドルフィン・ドーパミン・オキシトシン・セロトニン
が増え、ストレスホルモンのコルチゾールが下がる
といった説明がされています。

少し難しい言葉ですが、
- エンドルフィン…天然の痛み止め
- ドーパミン……「やった!」の快感物質
- オキシトシン…きずな・安心のホルモン
- セロトニン……心の安定剤のような役割
- コルチゾール…ストレス時に出るホルモン
と覚えておけばOKです。
③ 「親切」が遺伝子レベルにまで届く?
ポジティブ心理学と生物学をつなぐ研究では、
- 何週間かにわたって
「人のためになる行動」を増やしたグループ - 変わらない生活をしたグループ
を比べ、
血液中の免疫細胞の遺伝子の働き方を調べた研究もあります。
結果として、
- 炎症(えんしょう)に関わる遺伝子の働きが
穏やかになる傾向 - ウイルスへの防御に関わる部分が
バランスよく保たれる傾向
などが示されました(※ただし、まだ研究は発展途上です)。
つまり、
「親切にすること」が、
気分だけでなく体の奥のレベルにまで
良い影響を与えている可能性
も見えてきている、ということです。
ヘルパーズ・ハイは、
単なる「いい気分」ではなく、
- 脳
- ホルモン
- 免疫
といった 体の深いところ と
つながっている現象だと分かってきました。
次の章では、
ここまでの内容をふまえて、
まとめと、これからに活かすためのヒントを
一緒に整理していきます。
9. まとめ・考察
「人を助けること」と「自分の幸せ」の関係
ここまでのお話を、
いったんシンプルに振り返ってみます。
① 今回わかったこと(ざっくり総まとめ)
- ヘルパーズ・ハイとは
「人を助けたあとに感じる、あたたかい高揚感」 - この現象は
アラン・ラックスの研究などをきっかけに広まり、
心身の健康との関連も示されている - ポジティブ心理学の研究では、
「自分のため」より「人のため」の行動のほうが
幸福感を高めやすいことが分かっている - 脳の報酬系やホルモン、遺伝子レベルにも
プラスの変化が見られる可能性がある
② 筆者なりの“高尚な”考察
人を助けるとき、
私たちは同時に
- 「自分はここにいていい」という存在感
- 「世界は完全に冷たいわけではない」という信頼感
- 「まだできることがある」という希望
も、少しずつ取り戻しているように思います。
つまり、ヘルパーズ・ハイは
「自分」と「他者」と「世界」の3つを
もう一度つなぎ直す瞬間に
生まれる感覚
なのかもしれません。
③ ちょっとユニークな視点
ヘルパーズ・ハイを
「無料でできる、合法的な“ごほうびタイム”」と
考えてみるのはどうでしょうか。
ゲームのように、
- 小さなクエスト(親切)をクリアすると
- 経験値(自己肯定感)がたまり
- アイテム(人とのつながり)が増えていく
そんな**「リアルRPG」的な視点**で
日々の親切を眺めてみると、
少しだけ世界が違って見えるかもしれません。
④ あなたなら、この現象をどう活かしますか?
- 日々のストレスで、気持ちがすり減っているとき
- 「自分なんて」と思ってしまうとき
- なんとなく毎日が単調に感じるとき
そんなとき、
あなたなら どんな小さな親切 から
ヘルパーズ・ハイを試してみたいでしょうか?
今日の帰り道、
誰かの“ちょっとした困りごと”に
1分だけ手を貸してみる。
それだけでも、
あなたの心の中に
小さな変化が生まれるかもしれません。

――ここから先は、少しだけ「応用編」です。
ヘルパーズ・ハイという言葉を、ただ知っているだけでなく、日常の会話やSNSで自分の言葉として使える状態にしていきましょう。
10.応用編:
ヘルパーズ・ハイを自分の言葉にする
1. 一言で説明したいときのフレーズ
まずは「とりあえずこれだけ覚えておけば話せる」一言フレーズです。
- 「人を助けたあとに、心だけスッキリする現象のことをヘルパーズ・ハイって言います。」
- 「ボランティアのあとに感じる、ふわっとした幸福感のことですよ。」
- 「誰かの役に立ったときに、脳からごほうびが出て気持ちよくなる現象です。」
一度声に出して読んでおくと、
いざというとき口から自然に出やすくなります。
2. 相手別の言いかえ(子ども/家族/職場)
同じ内容でも、誰に話すかで少しだけ言い方を変えると伝わりやすくなります。
子どもに説明するとき
「だれかを手伝ったあと、胸がポカポカすることあるでしょ?
あれは、脳が『よくがんばったね』ってごほうびをくれてる“ヘルパーズ・ハイ”なんだよ。」
家族に話すとき
「この前のボランティアのあと、不思議と気分よかったでしょ?
人助けのあとにだけ起きる“ヘルパーズ・ハイ”っていう現象があるらしいよ。」
職場の同僚に話すとき
「あのイベント、体力的にはきつかったけど、終わったあと変にスッキリしてましたよね。
ああいうの、心理学だとヘルパーズ・ハイって呼ぶそうです。」
相手を思い浮かべて、
どのパターンがいちばん使いやすいか選んでみてください。
3. 自分の体験を言葉にするミニテンプレ
ヘルパーズ・ハイを“自分ごと”にするには、
自分の体験を短く書いてみるのがおすすめです。
そのまま使える形でご紹介します。
「今日は〇〇(例:地域の清掃ボランティア)を手伝って、正直かなりクタクタになりました。
それなのに、帰り道の途中でふと『心だけはスッキリしているな』と気づきました。
友だちの“助かったよ、ありがとう”という言葉を思い出すと、胸のあたりがじんわり温かくなります。
こういう“クタクタなのに気持ちいい”感覚を、ヘルパーズ・ハイって言うんだなと思いました。」
ブログやSNSでそのまま使ってもいいですし、
自分用の日記として書き残しておくのもおすすめです。

4. 語彙ストック(スマホのメモに書いておく用)
最後に、ヘルパーズ・ハイのまわりで
よく使う言葉をコンパクトにまとめておきます。
- ヘルパーズ・ハイ
- 人助けの幸福感
- 「クタクタなのにスッキリ」する感覚
- 脳のごほうび回路
- うれしいホルモン(ドーパミン・エンドルフィンなど)
- 親切行動・利他的行動(人のための行動)
このあたりの語彙をちらっと見返すだけでも、
「自分の言葉で説明する」準備運動になります。
ここまでが、
ヘルパーズ・ハイを自分の言葉に落とし込むための応用編でした。
このあとは、
「もっと専門的に学びたい」「本や論文も知りたい」という方に向けて、
関連書籍や信頼できる情報源を紹介するパートへと進んでいきます。
11. 更に学びたい人へ
――「もっと深く知りたい」と思ったあなたへ
ここまで読んで、
「人を助けると気持ちがよくなる理由を、もう少ししっかり知りたい」
「ヘルパーズ・ハイだけじゃなく、“幸せ”全体の考え方も学んでみたい」
と感じた方に向けて、
おすすめの本を3冊ご紹介します。
① 初学者・小学生にもおすすめ
『きみだけの幸せって、なんだろう? 10才から考えるウェルビーイング』
前野マドカ 著/かるめ イラスト
どんな本?(特徴)
- 「ウェルビーイング(well-being/ウェルビーイング)=
幸せに生きている状態」を、10歳から読める言葉でやさしく解説した本です。 - 「幸せの正解はひとつじゃない」という前提から、
10の質問を通して
“自分だけの幸せ”を考える力 を育ててくれます。
おすすめ理由
- イラストが多く、文章も平易なので、
小学校高学年〜中学生、そして大人の読み直しにも向いている 1冊です。 - 「お金」「学校」「将来」など、
幸福とまちがわれやすいテーマをていねいに整理してくれるので、
ヘルパーズ・ハイのような
「人とのつながりから生まれる幸せ」を理解する土台作りにぴったりです。 - 家族で「幸せって何だろう?」と話すきっかけ本としても使えます。
② 人を助けることで自分も癒される理由を知りたい人へ
『人を助けるということ: 苦しい時を乗り越えるために』
スティーブン・ポスト 著/ケイ洋子 訳
どんな本?(特徴)
- 「助けることで助けられる」という
ヘルパー・セラピー原理 をテーマにした本です。 - 著者は予防医学・精神医学の専門家で、
自身の喪失体験や臨床経験をふまえながら、
「人を助けることが、なぜ自分の心と体をも支えるのか」を
生理学的・精神医学的な視点から解説しています。
おすすめ理由
- ヘルパーズ・ハイに近い
「人を助ける側が癒されるメカニズム」を、
体験談+医学の両方 から知ることができます。 - 「自己犠牲ではなく、健全な“助け方”とは何か?」という問いにも触れており、
ボランティアや支援職、介護に関わる方にも役立つ内容です。 - 本記事で書いてきた
「人を助けると、自分も少し楽になる」という感覚を、
もう一歩深く理解したい中級者におすすめです。
③ 幸福学・ポジティブ心理学を全体的に掴みたい人へ
『新装版 幸せがずっと続く12の行動習慣
「人はどうしたら幸せになるか」を科学的に研究してわかったこと』
ソニア・リュボミアスキー 著/金井真弓 訳/渡辺誠 監修
どんな本?(特徴)
- 「幸福を決める3つの要因
(50%が遺伝、10%が環境、40%が意図的な行動)」という有名なモデルを紹介し、
その “変えられる40%”に働きかける12の行動 を解説したポジティブ心理学の定番書です。 - 12の行動の中には、
「人に親切にする」「感謝を表現する」など、
ヘルパーズ・ハイと深く関わる行動も含まれています。
おすすめ理由
- 「人を助けると気持ちがいい」という話だけでなく、
“幸せ全体の科学”を俯瞰できる 一冊です。 - 各章に、読者が実践できるワークが用意されているので、
「知って終わり」ではなく、
生活の中で試しながら身につけられる構成 になっています。
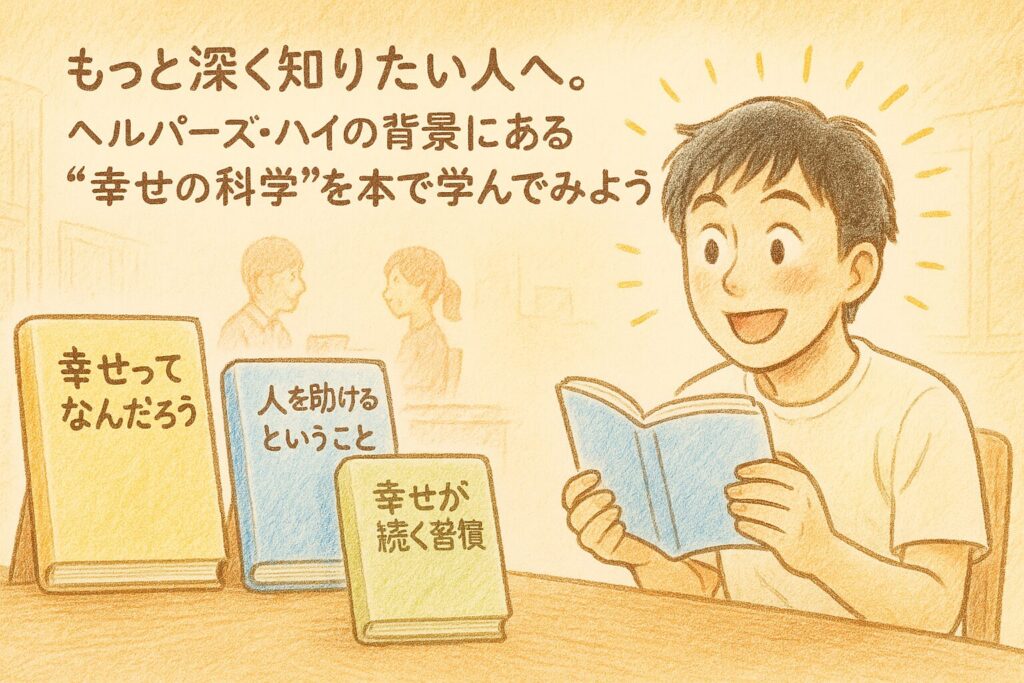
記事で触れた内容を、
「本のページをめくりながら、ゆっくり自分のペースで深めていきたい」
そう思ったときに、
今日ご紹介した3冊が、
きっと心強い“次の一歩”になってくれるはずです。
12. 疑問が解決した物語
あの日の引っ越しから、少し経った夜。
ユウタさんはなんとなく、スマホで
「ボランティア 疲れてるのに気分いい 理由」
と検索していました。
そこで目に入ったのが、
「ボランティアのあとだけスッキリする不思議?
その気持ちよさの正体は『ヘルパーズ・ハイ』でした」
という記事でした。
読み進めるうちに、
「人を助けたあとに感じる“クタクタなのにスッキリ”は
脳のごほうび反応で、“ヘルパーズ・ハイ”と呼ばれる」
と知り、
あの日の不思議な感覚に
ちゃんと名前があったことを知ります。
「なんだ、ちゃんとした理由があったんだ」
胸のモヤモヤが、少し誇らしい思い出に変わりました。
数週間後の週末。
今度は職場の先輩から、
「日曜のイベント、人が足りなくてさ……
半日だけでも手伝ってくれない?」
と頼まれます。
一瞬ためらいながらも、
ユウタさんはあの記事を思い出し、
自分の心と体にたずねました。
「丸一日はきついけど、午前中だけならいけるかも」
そして、こう答えます。
「午前中だけなら大丈夫です。
その代わり、午後は休みたいので、そこまででもいいですか?」
イベント当日。
やっぱり体はクタクタになりましたが、
参加者の「楽しかったです!」の一言や、
仲間との「おつかれ!」の笑顔に触れるうちに、
胸のあたりに、
またあの じんわりしたスッキリ感 が広がっていきます。
帰り道、ユウタさんは心の中でつぶやきました。
「ああ、これがヘルパーズ・ハイか。
無理をしすぎなければ、
人のために動くことって、ちゃんと自分のためにもなるんだな」

それからユウタさんは、
- できる範囲でなら、人の力になる
- 限界を超えそうなときは、きちんと断る
という 自分なりのルール を持つようになりました。
あの日の疑問、
「なんで“クタクタなのにスッキリ”するんだろう?」
は、今では
「それはヘルパーズ・ハイという、
人と自分を同時にあたためる仕組みなんだ」
という小さな確信に変わっています。
そして今、この物語を読み終えようとしているあなたにも、
同じ問いかけをしてみたくなります。
あなたなら、
どんな小さな「人の役に立つこと」で、
自分なりのヘルパーズ・ハイを味わってみたいですか?
13.文章の締めとして
ここまで読み進めてくださったあなたは、
きっともう「ヘルパーズ・ハイ」という言葉を
ただの専門用語ではなく、
自分の体験と結びついた“実感のあることば” として
受け止め始めているのではないでしょうか。
クタクタに疲れた日の帰り道。
誰かの「助かったよ」のひと言や、
小さな「ありがとう」の記憶が、
ふと胸の奥をあたためてくれる瞬間があります。
その正体に名前がつき、
しくみを少しだけ知れた今なら、
そのあたたかさを、前よりもやさしく見つめられるはずです。
人のために動くことは、ときに面倒で、
ときにしんどくて、
ときに「もうごめんだ」と思うこともあるかもしれません。
それでも、
自分をすり減らしすぎない範囲で
誰かの力になれたとき、
自分の心にもそっと灯りがともる――
その仕組みを知っていることは、
これからの日々を少しだけ歩きやすくしてくれるはずです。
もしまた、
「クタクタなのに、なんだかスッキリしている自分」に気づいたら、
どうか今日のこの記事のことを
すこしだけ思い出してみてください。
それはきっと、
あなたの中の「誰かを思う力」と、
あなた自身を支えてくれる力が、
同じ場所から静かに湧き上がっている証拠なのだと思います。
注意補足
本記事でご紹介した内容は、著者が本人で調べられる範囲で、
信頼できる研究論文や公開されている統計・レビュー論文をもとに、
できるだけ正確になるよう注意してまとめています。
しかし、
心や脳、免疫に関する研究は、今も世界中でアップデートが続いていること
研究ごとに結論が少しずつ異なる場合があること
もまた事実です。
ヘルパーズ・ハイという現象も、
今後の研究によって
新しい側面が見つかったり、解釈が変わったりする可能性があります。
その変化も含めて、
「人を助けること」の奥深さを、
一緒に楽しんでいけたらうれしいです。
🧭 本記事のスタンス
この記事は、「これが唯一の正解です」と言い切るためのものではなく、
「読者の方が、自分で興味を持ち、さらに調べてみるための入り口」
として書かれています。
このブログで少しでも
『ヘルパーズ・ハイ』に心がハイになったなら、
ぜひ本や論文といった“より深い世界”にも一歩踏み出して、
「もっと知りたい・学びたい・確かめたい」という、
あなただけのヘルパーズ・ハイを育ててみてください。
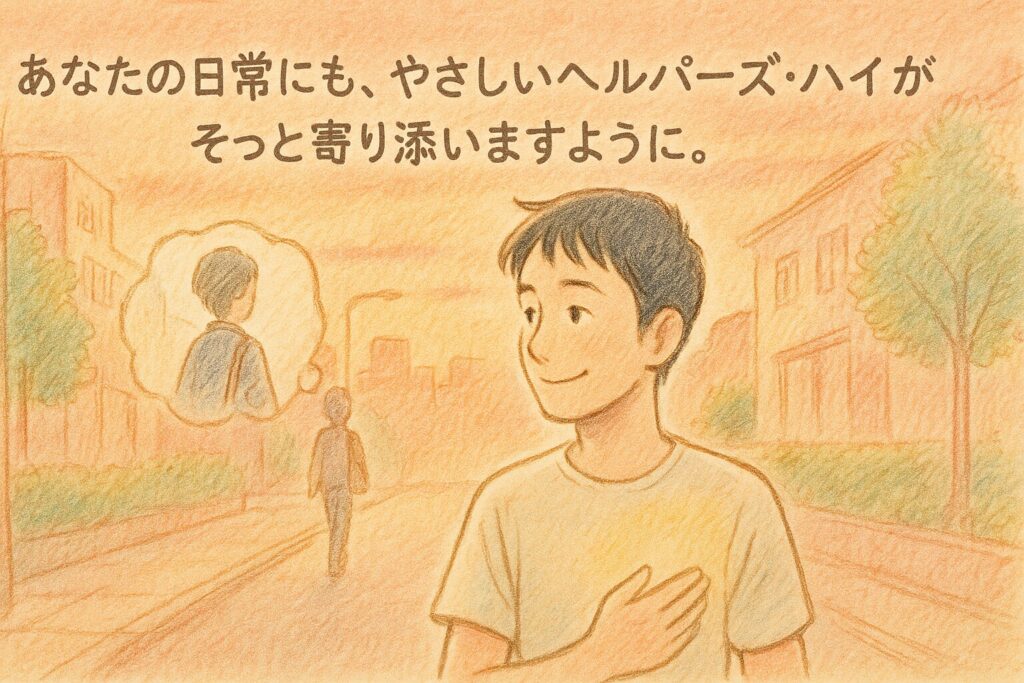
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました。
どうかこれからも、あなたの日常に、やさしいヘルパーズ・ハイがそっと寄り添い続けますように。







コメント