『ゴキブリの由来』とは?御器噛り(ごきかぶり)から生まれた名前の秘密
夜遅く、食器を洗わずにテーブルにおわんを置きっぱなしにしてしまったときのこと。
ふと視界のすみで黒い影がサッと走り抜けます。
「うわっ、ゴキブリだ!」
その瞬間、頭に浮かびませんか?
「ゴキブリって、なんで“ゴキ”と“ブリ”なの?」
響きが独特で、意味が気になる。そんな経験をした人は多いはずです。
3秒で分かる結論
答え:「ゴキブリ」という名前は、『御器噛(ごきかぶ)り』が変化したものです。
- 御器(ごき)=お椀(わん)などの食器のこと
- 噛(かぶ)り=かじること
つまり「御器をかじる虫」→「ごきかぶり」→「ごきぶり」と音が変わっていったのです。
今回の現象とは?
「“ゴキ+ブリ”ってどうして?(名前の法則とは?)」
このようなことはありませんか?
- 食器を片づけようとしたら、おわんのそばを黒い影がスッと横切る。その瞬間に「名前の由来が気になる」。
- 子どもに「なんでゴキブリっていうの?」と聞かれて、答えに困ってしまう。
- 「ゴキ? ブリ? 魚のブリ?」と冗談交じりに言葉の謎を考えてしまう。
- 英語の cockroach(コックローチ) という全然違う名前を知って、「どうして日本語は“ゴキブリ”なんだろう?」と不思議に思う。
※cockroach はスペイン語 cucaracha(クカラーチャ) がもとで、「コックローチ」と読みます。英語では単に“ゴキブリ”の意味です。

この記事を読むメリット
- 「すぐに答え」が分かってモヤモヤが解消する。
- 雑談や親子の会話で「由来を1分で説明」できるようになる。
- 昔の暮らしと日本語の関係が分かり、言葉の面白さに気づける。
疑問が浮かんだ物語
夜の食卓。洗い物を後回しにして、おわんをテーブルの端に置いたまま。
ふと暗がりの奥で、**カサ…**と音がします。黒い影が走り抜け、私は思わず息をのむ。
「なんで“ゴキブリ”っていうんだろう。ゴキって? ブリって?」
心の中で繰り返し、妙な違和感と小さな恐怖が入り混じります。
「子どもに聞かれたら、ちゃんと答えられないな…」
「昔の人は“食器の残り物をかじる虫”と呼んだって聞いたことがあるけど、本当にそうなの?」
目の前の黒い影に対する嫌悪感と、名前の謎を知りたい好奇心が、同時にふくらんでいく。
怖いのに気になる——そんなもどかしい心情に包まれていきました。

すぐに分かる結論
お答えします。
「ゴキブリ」という名前の由来は、**『御器(ごき)をかじる虫』=『御器噛(ごきかぶ)り』**です。
御器(ごき)はお椀や食器のこと。噛(かぶ)りは「かじる」という意味です。
つまり昔の人は、食器に残った食べ物をかじりに来る虫をそう呼んでいたのです。
この言葉が音の変化を経て「ごきぶり」になり、今の名前として定着しました。
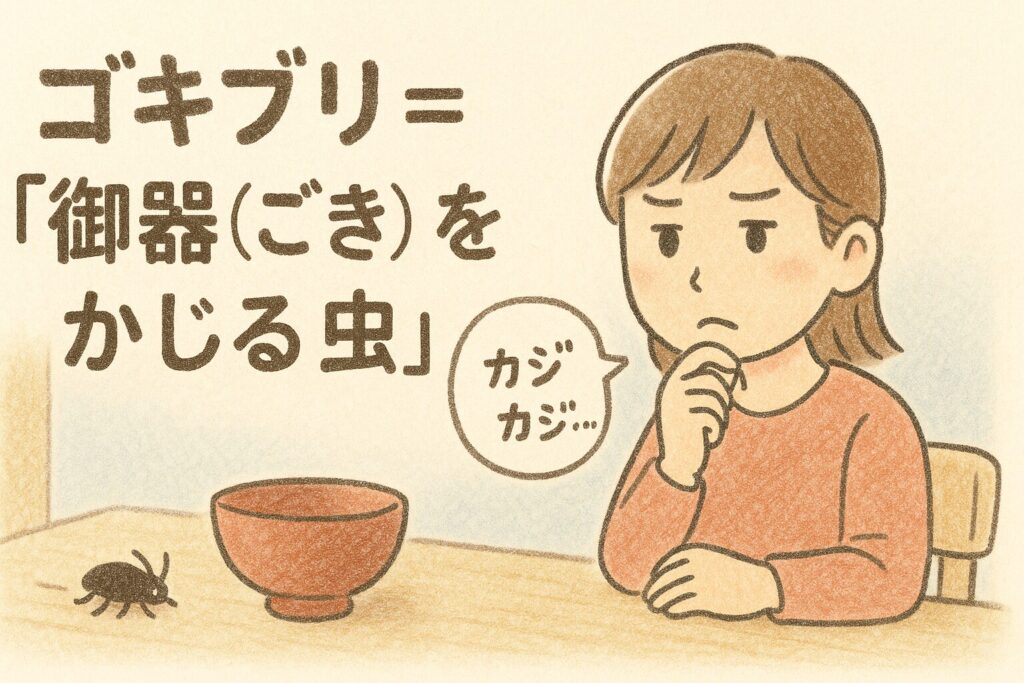
噛み砕いて言えば、「おわんをカミカミする虫」=ゴキブリ。
さらに近代になると、学術書の表記の誤りや振り仮名の影響で「ごきかぶり」ではなく「ごきぶり」が広まりました。
ここでモヤモヤは一度解けました。
でも、「なぜ御器なの?」「他の呼び方は?」「どの時代から定着?」といった細かい疑問が残りませんか?
次の段落からは、“御器の意味”“音の変化のしくみ”“江戸時代の呼び方”まで丁寧に解説します。
気になる方はぜひ一緒に、この言葉の奥深さを探ってみましょう。
『ゴキブリ』とは?
ゴキブリの基本的な定義
ゴキブリは、ゴキブリ目に属する昆虫の仲間です。
学術的には Blattodea(ブラットデア/ブラトデア) と呼ばれ、
体が平たく(扁平:へんぺい)、すばやく走ることが大きな特徴です。
日本語の漢字表記では 「蜚蠊(ひれん)」 という字があてられることもあります。
また、最新の研究では、シロアリもゴキブリの仲間に含められることが一般的になっています。
これは、遺伝子(ゲノム)や分子の研究から、両者に共通の祖先がいたことが分かったためです。
※昔はシロアリを「等翅目(イソプテラ)」という別のグループに入れていましたが、今では「ゴキブリ目」にまとめられています。
名前の語源
「ゴキブリ」という名前は、**『御器噛(ごきかぶ)り』**が変化したものです。
- 御器(ごき) … お椀(わん)などの食器を指す昔の言葉
- 噛(かぶ)り … 「かじる」という意味
つまり、「御器をかじる虫」=御器噛り(ごきかぶり) が短く発音されて、
現在の「ゴキブリ」になったのです。
名前の変化の歴史
昔の日本では、今の「ゴキブリ」とは別の名前でも呼ばれていました。
- 阿久多牟之(あくたむし)
- 都乃牟之(つのむし)
- 油虫(あぶらむし)
江戸時代の百科事典『和漢三才図会(わかんさんさいずえ)』(1712年)には、
「五器囓(ごきかぶり)」や「蜚蠊(ひれん)=油虫(あぶらむし)」の文字が出てきます。
このことから、当時は呼び名がいくつも使われていたことが分かります。
地域ごとに呼び方が異なる場合もあり、沖縄では「ヒーレー」という言い方が残っているとも言われます。
研究や事例
国語辞典(デジタル大辞泉や日本国語大辞典)では、
「ゴキブリ」は「御器噛り(ごきかぶり)の音の変化」だと解説されています。
また、一部の学術書や古い資料では、誤った振り仮名や表記が広まったことが、
「ゴキカブリ」ではなく「ゴキブリ」が一般化した理由の一つだとされています。
要するに、
① 生活の観察から生まれた言葉(食器をかじる虫)
② 印刷や辞書での表記の広まり
この二つの要因が重なって、今日の「ゴキブリ」という名前が定着したのです。
なぜ注目されるのか?
1) 言葉の背景=生活から生まれた名前
ゴキブリの名前の由来は、昔の人の生活観察そのものです。
台所に残った食べ物を「御器(ごき)」と呼ばれる食器に見つけ、
そこに集まって「かじる」姿を見て、そのまま名前にした。
このように、日常の光景が直接「言葉」として残るのは、
日本語ならではの生活に根ざした名づけのセンスです。
2) 社会での受け止め方
江戸時代には「ゴキブリ」というよりも、**「油虫(あぶらむし)」**の呼び方が一般的でした。
戦後になってから、「ゴキブリ」という表記が全国的に広まったといわれています。
こうした呼び方の変遷には、
人々の生活環境や衛生観念の変化も影響していると考えられます。
名前の歴史をたどると、社会がどのように虫と向き合ってきたのかも見えてくるのです。
3) 世界との比較(ちょっとした小ネタ)
英語で「ゴキブリ」は cockroach(コックローチ) と言います。
この言葉は、スペイン語の cucaracha(クカラーチャ) が元になっていて、
発音が変わって英語に取り入れられました。
スペイン語の「クカラーチャ」は、民謡「ラ・クカラーチャ」の歌でも有名です。
つまり、嫌われ者である一方、文化の中で親しまれる存在でもあるのです。
また、世界には約4,600種類のゴキブリがいますが、
人の住む家で害虫とされるのはごく一部にすぎません。
ここからも分かるように、「ゴキブリ」という名前の印象と実際の生物学的な姿には大きなギャップがあるのです。
小まとめ
「ゴキブリ」とは、ただの嫌われ者ではなく、
言葉の中に人々の生活と歴史を映した存在です。
食器に残った食べ物をかじる姿から「御器噛り(ごきかぶり)」と呼ばれ、
それが「ゴキブリ」へと変わっていきました。
江戸では「油虫」とも呼ばれ、
戦後になって「ゴキブリ」という名が一般的になりました。
世界に目を向ければ、英語では「コックローチ」、
スペイン語では「クカラーチャ」。
言葉も文化も違うのに、どこか同じように「厄介者」としての姿を映しています。
しかし一方で、4,000種以上いるゴキブリのうち、
人に迷惑をかけるのはほんの数十種にすぎません。
名前のイメージと現実の姿は、大きくずれているのです。
つまり、「ゴキブリ」という名前を知ることは、
単に語源の知識を得るだけでなく、
暮らしの工夫や社会の価値観を読み解く入口でもあるのです。
❓Q&A:ゴキブリの名前に関するよくある疑問
Q1. 「ゴキ」って何?魚のブリと関係あるの?
答え:関係ありません。
「ゴキ」とは 御器(ごき)=おわんや食器のこと を意味します。
「ブリ」は魚の名前ではなく、噛(かぶ)り=かじること を指します。
つまり、昔の人は「御器をかじる虫」→「ごきかぶり」と呼び、
そこから音が変化して「ゴキブリ」になったのです。
Q2. 英語ではなんて呼ぶの?
英語では cockroach(コックローチ) と言います。
これはスペイン語の cucaracha(クカラーチャ) が語源です。
あの有名な民謡「ラ・クカラーチャ」にも登場します。
👉 日本語は“生活の観察”から名前が生まれましたが、
英語やスペイン語は“言葉の響き”から変化したという違いが面白いポイントです。
Q3. 本当に2億年前から姿を変えてないの?
「ゴキブリは恐竜より昔から同じ姿」とよく言われますが、正確には違います。
🪨 化石の証拠では、現在の姿に近いゴキブリは 約1億2500万〜1億4000万年前(白亜紀:はくあき) に登場。
🧬 一方、DNA(ディーエヌエー/遺伝子)を使った**分子年代推定(ぶんしねんだいすいてい)**では、
共通の祖先は 約2億3500万年前 にさかのぼるとされています。
👉 つまり「そっくりそのまま変わってない」わけではなく、
進化しながら長い歴史を生き抜いてきた昆虫だということです。
Q4. ゴキブリは全部害虫なの?
実は違います。
世界には 約4600種類 のゴキブリが知られていますが、
人間の生活に害を及ぼすのは ほんの数十種類。
多くの種類は森や草むらに生息し、
落ち葉や動物のフンを分解して 自然界の掃除屋(デコンポーザー:分解者) として働いています。
Q5. 語源を知るメリットってあるの?
あります!
・雑談のネタになる
・子どもに聞かれても1分で説明できる
・昔の暮らしの知恵や日本語の面白さを理解できる
・「食器を片づけよう」といった行動の動機づけになる
👉 つまり「語源を知ること」が、生活や会話を豊かにしてくれるのです。
実生活への応用例
💬 雑談や教育での活かし方
「なんでゴキブリっていうの?」と聞かれたら――。
すぐにこう答えられます。
👉 御器(ごき)=おわんや食器 + 噛(か)ぶり=かじる → “御器噛り(ごきかぶり)” → ゴキブリ。
1分で話せるこの小ネタ、
ただの暗記よりも「昔の生活が見えてくる物語」として記憶に残ります。
子どもへの国語・歴史の導入にもなり、雑談でも盛り上がること間違いなしです。
🍚 暮らしのヒント(予防に直結)
語源が示すとおり、ゴキブリは食器の食べ残しや生ゴミに寄ってきます。
つまり「御器をかじる虫」という名前そのものが、生活の注意点を教えてくれているのです。
そこで大切になるのが IPM(アイピーエム)。
IPM = Integrated Pest Management(インテグレーテッド・ペスト・マネジメント)
日本語では「総合的有害生物管理」。
薬剤に頼り切らず、①寄せない、②入れない、③繁殖させない、の順で対策します。
✅ 今日からできる実践ポイント
- 食器は夜に残さない → 「御器をかじる虫」の語源どおり、残した食べ物は最大の誘因。
- 生ゴミはフタ付きの容器に → 特に夏は数時間で強いニオイ発生。
- 水回りを乾燥させる → シンクの水たまり・冷蔵庫の受け皿は要注意。
- すき間を塞ぐ(シーリング) → 配管まわりや巾木(へり板)の小さな穴をふさぐだけでも効果大。
- 段ボールを溜め込まない → 巣や卵の隠れ場所になりやすい。
- ベイト剤(誘引式の毒エサ)を計画的に → 人やペットの安全に配慮して配置。
🌟 メリットとデメリット
- メリット
家族で衛生習慣をシェアできる。
子どもが言葉の由来に興味を持ち、学びのきっかけになる。 - デメリット(注意点)
「2億年前から同じ姿」など、表現に幅のある俗説をそのまま言わないこと。
また、薬剤だけに頼ると根本解決にならないため、予防行動との組み合わせが必須です。
注意点や誤解されやすい点
❌ 誤解① 「恐竜より昔の2億年前から“今の姿のまま”」
- 事実
化石として残っている“今の形に近いゴキブリ”は 約1億2500万〜1億4000万年前(白亜紀)。
一方で、DNAを使った分子年代(ぶんしねんだい)推定では 約2億3500万年前に共通祖先がいた可能性があるとも言われます。 - なぜ誤解?
「化石で実際に見つかった年代」と「遺伝子から推定された年代」が混同されやすいからです。 - 対策
「化石=証拠」「分子=推定」。
この違いを意識して説明すれば、誤解は防げます。
❌ 誤解② 「語源は“器をかぶる(覆う)”」
- 事実
「かぶり」は「被る」ではなく「噛(か)ぶり=かじる」の意味。
御器=食器、噛り=かじる。これを辞書でも確認できます。 - なぜ誤解?
“かぶる”という日本語に「覆う」の意味もあるため、取り違えが起こりやすいのです。 - 対策
漢字を正しく示す(噛=かじる)ことが一番わかりやすい方法です。
❌ よくある追加の誤解
- 「シロアリは全く別の仲間」
→ 現在では分子解析により、シロアリもゴキブリ目(Blattodea:ブラットデア)に含めるのが一般的。 - 「世界中のゴキブリがみな害虫」
→ 実際には約4600種のうち、人間の生活に害を及ぼすのはごく一部です。
🔑 誤解を避けるための3つのポイント
- 一次資料(辞書・古典籍)にあたる
例:大辞泉、日本国語大辞典、『和漢三才図会』。 - 化石の年代と分子推定を分ける
→ 「証拠」と「仮説」を混ぜない。 - 生活対策はIPMを基本に
→ 食器・生ゴミ・水・隙間を管理するのが第一歩。
小まとめの一文
語源を知ると、単なる“嫌われ者”の虫が、昔の暮らしを映す鏡に見えてきます。
正しい理解を持てば、誤解に振り回されず、
「名前が教えてくれる暮らしの知恵」を毎日の行動に生かせるのです。
おまけコラム
ゴキブリと人類の意外な“つながり”
ゴキブリはただの害虫――そう思われがちですが、実は人類と深い関わりを持っています。
たとえば医療の分野。
中国や日本の漢方では、ゴキブリを乾燥させて**「蜚蠊(ひれん)」という生薬**として利用してきた歴史があります。
効能は血のめぐりをよくする(活血:かっけつ)、
ケガや打ち身の回復を助けるなどが記録されています。
現代でも中国では、ゴキブリ抽出物の医薬品が開発され、
胃炎や潰瘍(かいよう)の治療に使われている例もあるのです。
さらに生態学的な面では、ゴキブリは**分解者(デコンポーザー)**として自然界の栄養循環に重要な役割を担っています。
落ち葉や動物の排せつ物を分解し、土壌の肥沃(ひよく)さを保つ――
つまり、「嫌われ者」でありながら、地球の掃除屋でもあるのです。
このように見ていくと、ゴキブリは「不快な害虫」であると同時に、
人間の歴史や自然環境に必要な存在でもあると分かります。
まとめ・考察
ここまで、「ゴキブリ」という名前の由来から、
社会での受け止め方、そして実生活へのヒントまでを見てきました。
結論として、ゴキブリ=御器噛り(ごきかぶり)からの音変化。
つまり「食器をかじる虫」という生活感あふれる名づけがルーツでした。
そこから浮かび上がるのは――
言葉は単なる音ではなく、人の暮らしや価値観の記録だということです。
嫌われる存在であっても、名前をたどれば昔の台所の風景が見え、
世界の呼び名を比べれば文化の違いが分かり、
さらに現代の衛生習慣や医療研究にまでつながっていきます。
最後に問いかけです。
「あなたにとって“ゴキブリ”は、ただの不快な虫ですか?
それとも、暮らしと歴史を映す“ことばのタイムカプセル”ですか?」
もしかすると、今夜ふと見かけた黒い影が、
次の雑談や学びのきっかけになるかもしれません。
更に学びたい人へ
📖 『新明解語源辞典』
著者:小松寿雄(編集)・鈴木英夫(編集)
この辞典は、日本語の日常語や古語の語源(ことばの成り立ち)をコンパクトにまとめた定番の1冊です。
「ゴキブリ=御器噛り(ごきかぶり)」のように、身近なことばの背景を辞書的な裏付けとともに確認できます。
🔎 おすすめ理由
ただの暗記で終わらず、「なぜその言葉になったのか」という物語性まで教えてくれるのが魅力。
ブログや雑談のネタにもしやすく、語源探究の入口として最適です。
🐞 『昆虫はすごい』
著者:丸山宗利
昆虫学者として国内外でフィールド調査を続ける著者が、昆虫の驚くべき生態を一般向けに分かりやすく解説した新書です。
ゴキブリを含む昆虫たちが、自然界でどんな役割を担っているのかを知ることができます。
🔎 おすすめ理由
「害虫」というイメージが強いゴキブリも、実際は生態系の重要な一部。
この本を読むことで、ゴキブリを「不快な存在」から「自然の循環を支える生き物」として見直す視点が得られます。
🪳 『ゴキブリ研究はじめました』
著者:柳澤静磨
ゴキブリを専門に研究する昆虫学者による、初の一般向けゴキブリ本。
フィールドワークや研究室での観察を通じ、ゴキブリの生態や進化の秘密をユーモラスに紹介しています。
🔎 おすすめ理由
研究者のリアルな体験談が豊富で、単なる“嫌われ者”から「知れば知るほど奥深い存在」へと認識が変わります。
「ちょっと苦手…でも気になる」という人にこそおすすめの1冊です。
✨ 小まとめ
- **『新明解語源辞典』**で「言葉の正しいルーツ」を押さえる。
- **『昆虫はすごい』**で「昆虫全体の中での位置づけ」を知る。
- **『ゴキブリ研究はじめました』**で「専門研究者のリアルな視点」に触れる。
この3冊を組み合わせれば、
語源 → 生態系 → 最新研究と、段階的に学びを深められます。
疑問の解決した物語
夜の食卓。あの時の黒い影を思い出しながら、私は辞書をめくり、いくつかの資料を読み比べました。
「ゴキブリ」という言葉は、平安時代から使われていた御器噛り(ごきかぶり)=食器をかじる虫が変化したもの――。
読み進めるうちに、あの妙な違和感が、ひとつの納得に変わっていきました。
「なるほど、昔の人が台所で見た光景をそのまま名前にしたんだな」
そう思うと、不思議と心が落ち着いてきます。
名前のルーツを知ったことで、嫌悪感ばかりだったゴキブリが、言葉を通じて歴史や暮らしを映す存在に見えてきたのです。
私は食器をすぐに片づけ、シンクを軽く拭き上げました。
「御器をかじる虫」という語源を知ったからこそ、残り物を置かないことの大切さが、より実感として迫ってきたからです。
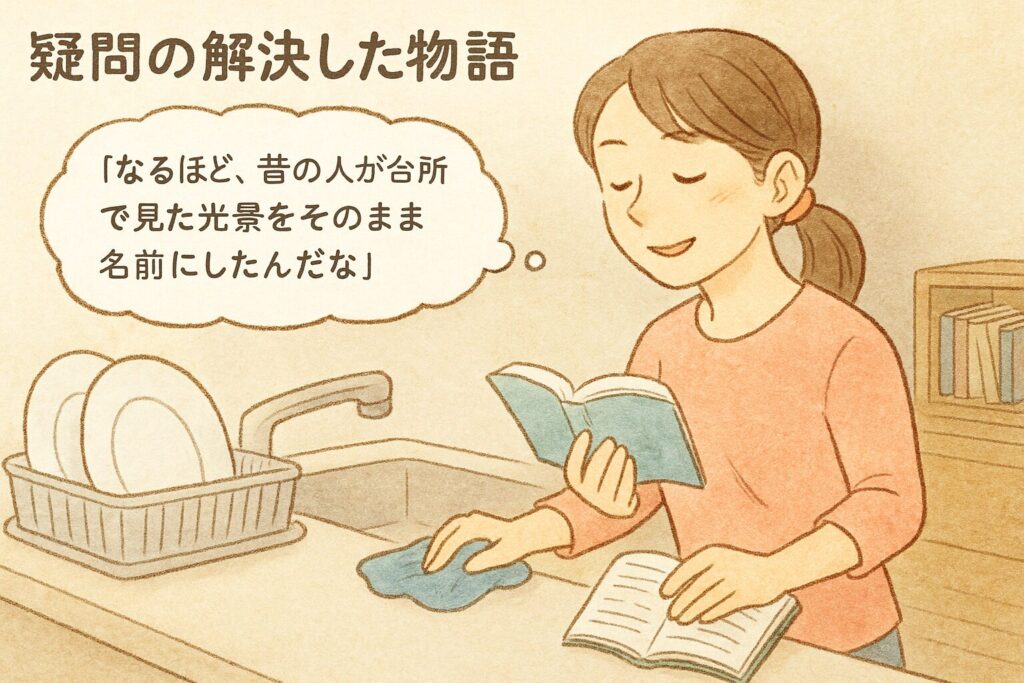
💡 教訓
嫌な存在でも、その名前や由来を知れば、暮らしの知恵や行動のヒントに変わる。
ことばは単なる音ではなく、過去の人々の体験が込められた記録なのだと気づきました。
❓ 読者への問いかけ
あなたにとって「ゴキブリ」という名前は、ただの不快な音ですか?
それとも、昔の人々の知恵を映す「ことばのタイムカプセル」ですか?
今夜、食器を片づけるとき、少しだけ違う視点で台所を眺めてみませんか。
✨ 記事の締め
「ゴキブリ」という名前は、単なる嫌われ者の呼び名ではなく、
平安時代の食器と暮らしの記憶が宿ったことばでした。
御器をかじる虫=御器噛り(ごきかぶり)。
この由来を知ることで、ただの恐怖や嫌悪の対象が、
昔の人の生活や知恵を映し出す“ことばのタイムカプセル”に変わっていきます。
日常の中でふと疑問に思ったことを調べ、
そこから歴史や科学に触れることは、
暮らしを少し豊かにし、行動を変えるきっかけにもなります。
たとえば食器をすぐ片づけることも、
語源を知れば単なる家事ではなく、生活を守る知恵の継承と感じられるでしょう。
注意補足
📌 本記事は、著者がk除塵で調べられる範囲で、
辞書・古典籍・昆虫学の研究など信頼できる情報をもとにまとめましたが、
研究が進むにつれて新しい発見が加わる可能性もあります。
つまり、今日の答えは“ひとつの入り口”にすぎません。
最後に。
「あなたが今ふと気になっている言葉の背景には、
どんな物語や知恵が隠れているのでしょうか?」
次の疑問が浮かんだとき、また一緒に探していきましょう。
御器のかけらをかじるように、ことばの欠片から学びを広げていけば、さらに深い世界が見えてきます。
もし今日の内容で興味が芽生えたなら、ぜひ文献や資料を手に取り、知の残りかすを味わうように深く学んでみてください。
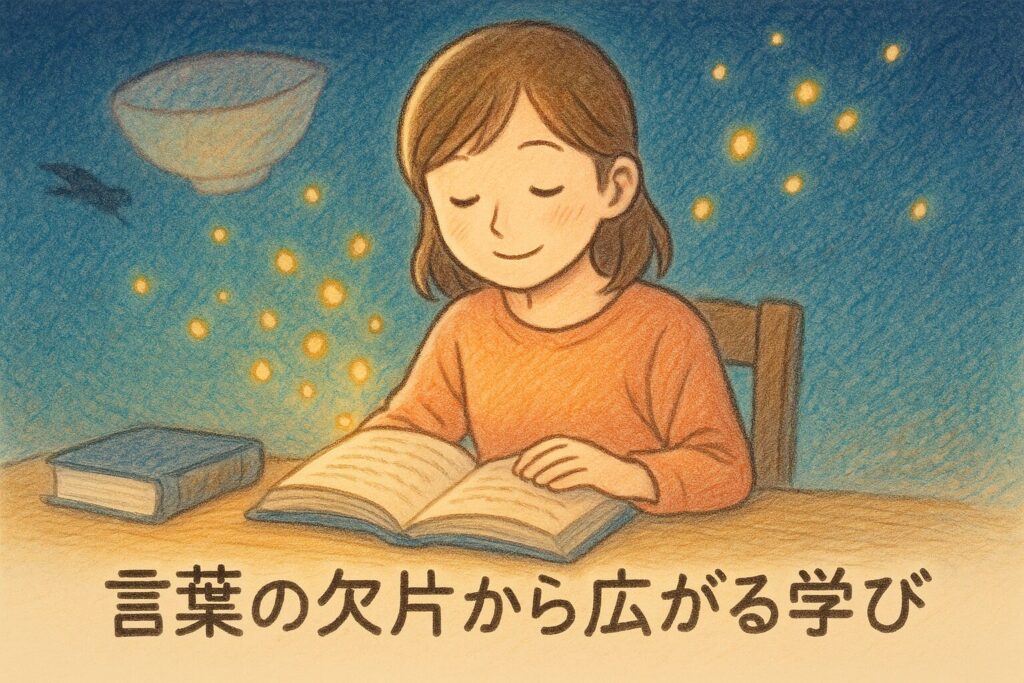
本日も最後まで読んでいただき、
心から感謝いたします。
そして――
言葉の残りかすをかじるように、日々の暮らしから小さな疑問を味わい続けてください。





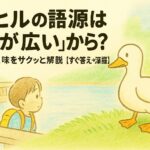

コメント