『相撲(すもう)』は本当に『日本の国技』?
「相撲って日本の国技だよね?」
そんな風に話している大人は多いのですが、
実はこの「国技」という言葉には驚くべき真実が隠れています。
例えば…
あなたはお相撲さんをテレビで見ながら
「日本の国技だから大切にされているんだな」と
なんとなく思ったことがありませんか?
ところが調べてみると、
相撲は法律で「国技」と決まったものではないのです。
「え?じゃあ、どうして『国技』と呼ばれるようになったの?」
と疑問が湧く方のために、
相撲の歴史とともに詳しく、
でもわかりやすく説明していきます。
読み終わるころには
「相撲の本当の立ち位置」が
きっとはっきり理解できるはずです。
相撲(すもう)とは?
相撲とは、日本で古くから続く伝統的な格闘技であり、
単なるスポーツを超えて 神事(しんじ:神さまに関わる儀式)としての意味も持つ文化です。
土俵(どひょう)と呼ばれる円形の舞台の上で、
二人の力士(りきし)が体をぶつけ合い、
相手を土俵の外に出すか、地面に倒すことで勝敗が決まります。
とてもシンプルなルールですが、
その中に込められた精神性や作法はとても奥深いものです。
相撲の起源をたどると、
日本神話に登場する
「建御雷神(たけみかづち)」と
「建御名方神(たけみなかた)」の力比べが
最古の相撲のルーツと言われています。
日本神話に登場する
建御雷神(たけみかづち) と 建御名方神(たけみなかた) の力比べは、
いわゆる「国譲り神話」と呼ばれる物語の一場面です。
出雲の大国主神(おおくにぬしのかみ)が治めていた国を、
天照大神(あまてらすおおみかみ)の命により「高天原(たかまがはら)」の神々に譲ってほしいと交渉するために
建御雷神が遣わされました。
しかし、大国主の息子である建御名方神が
「自分の力を試さずに国を譲るわけにはいかない」と反発し、
建御雷神に力比べ(相撲のような力競べ)を挑んだのです。
結果として建御雷神が勝ち、
建御名方神は降伏して国を譲ることに同意したとされています。
この物語が
「相撲の起源」ともいわれる理由は、
神々の間で行われた力比べという形が
現在の相撲の原型のように伝えられているからです。
つまり、相撲は「力比べ=神さまの裁き」という
とても神聖な意味を持って生まれたのです。
文献においては、
奈良時代にまとめられた
歴史書『日本書紀』(720年ごろ成立)に
「野見宿禰(のみのすくね)」と
「当麻蹶速(たいまのけはや)」が
力を競い合った話が書かれています。
歴史書『日本書紀』とは?
『日本書紀(にほんしょき)』は、
今から約1300年前の西暦720年に完成した
日本の歴史をまとめたとても大事な本です。
奈良時代の天皇である元正天皇(げんしょうてんのう)の時代に
編さんされました。
内容としては、
日本の国がどのように生まれ、
どのように発展してきたかを
神話の時代から当時の天皇までの歴史を
まとめたものです。
簡単にいえば
日本最古の国の歴史書であり、
日本の古代史を知るためのとても大切な資料です。
野見宿禰(のみのすくね)と当麻蹶速(たいまのけはや)とは?
この二人は『日本書紀』に登場する人物で、
日本の最初の相撲の勝負をした人たち
として有名です。
当麻蹶速(たいまのけはや)は、
とても強くて腕自慢で
「日本で一番の力持ち」と自慢していた人物です。
そこに野見宿禰(のみのすくね)という人物が挑戦し、
大きな力と技で当麻蹶速を打ち破りました。
この勝負の話が
「日本で最初の相撲の公式記録」として
歴史に残っているのです。
さらに野見宿禰は、
このあと朝廷に仕えて活躍した人物とも言われ、
相撲の祖(そ:始まりの人)と呼ばれることもあります。
このときの勝負が
日本で最初の公式な相撲とされ、
歴史的にも大きな意味を持つ出来事といえるでしょう。
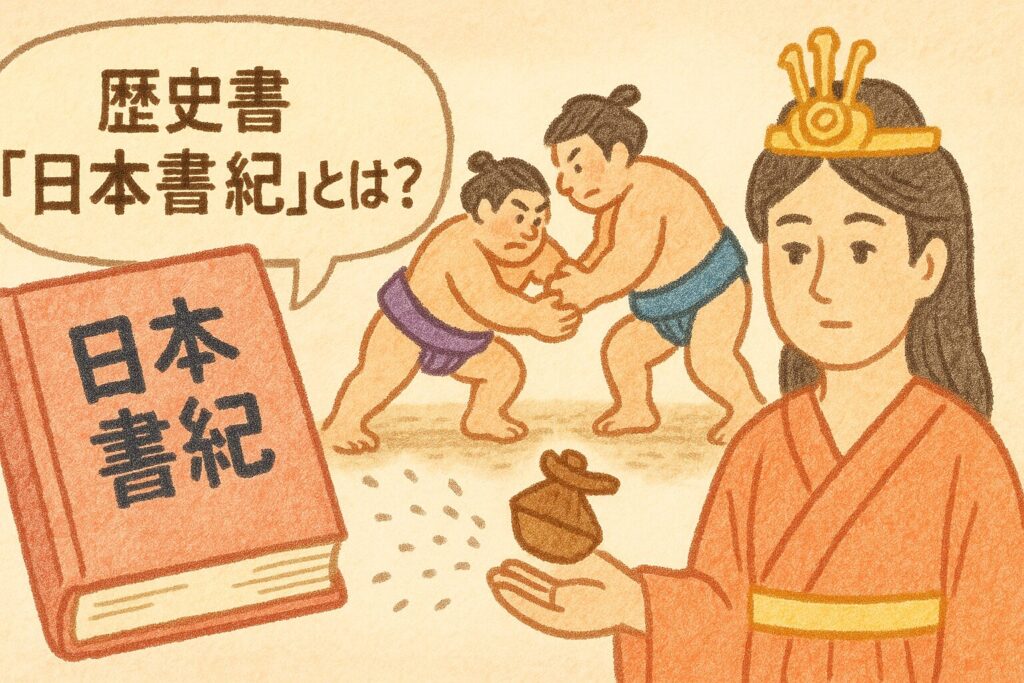
さらに時代が進むと、
相撲は単に力を誇るための勝負ではなく、
五穀豊穣や国家安泰を祈る神事として
平安時代には宮中行事に取り入れられました。
「相撲節会(すもうせちえ)」と呼ばれる行事は、
天皇の前で力自慢の者たちが技を競い、
農作物の豊作や国の平和を祈る儀式として行われていたのです。
その後、室町時代から安土桃山時代にかけて
庶民の間にも相撲が広まり、
江戸時代には興行(今でいうプロの相撲大会)としての形が整いました。
このころには現在のように
土俵が作られ、行司が勝敗を裁き、
まわしや化粧まわしなどの装飾文化も定着しました。
つまり相撲は、
神さまの世界の物語 → 皇室の行事 → 庶民の娯楽 → 日本を代表するスポーツ
へと、
何百年もかけて進化してきた伝統芸能だと言えます。
「ただのケンカ」ではなく
長い歴史の中で洗練され、
日本人の価値観を象徴する競技に育ったのです。
なぜ「国技」と呼ばれるようになったのか?
さて、ここが多くの人が勘違いしやすいポイントです。
「相撲は日本の国技です!」と
テレビなどでもよく言われますが、
日本には法律で正式に「国技」と定められたスポーツはありません。
ではなぜ相撲だけが
「国技」として広く知られるようになったのでしょうか?
その大きな理由が
1909年に誕生した
「国技館(こくぎかん)」という建物です。
当時、東京の両国に
日本初の常設の相撲場が建てられました。
その建物に「国技館」という名前が付けられたことで、
相撲=国技というイメージが
一気に広まったと言われています。
つまり
「国技館」という名前のインパクトが大きかった
というのが真実に近いのです。
実際に公益財団法人日本相撲協会の公式サイトでも
相撲が国技と「法律で決まっている」わけではないことを
明記しています。
「伝統文化としての相撲」
「多くの日本人が応援している競技」
という意味で
「事実上の国技」として
扱われているわけですね。

相撲の魅力を日常生活に活かすには
相撲は、単に勝ち負けを競うだけの格闘技ではありません。
その根底には、相手を敬う気持ちや、
自分を律する心を大切にする文化が根付いています。
たとえば
力士が土俵に上がるときに行う「塩まき」には
土俵という神聖な場所を清め、
正々堂々と勝負するという意味が込められています。
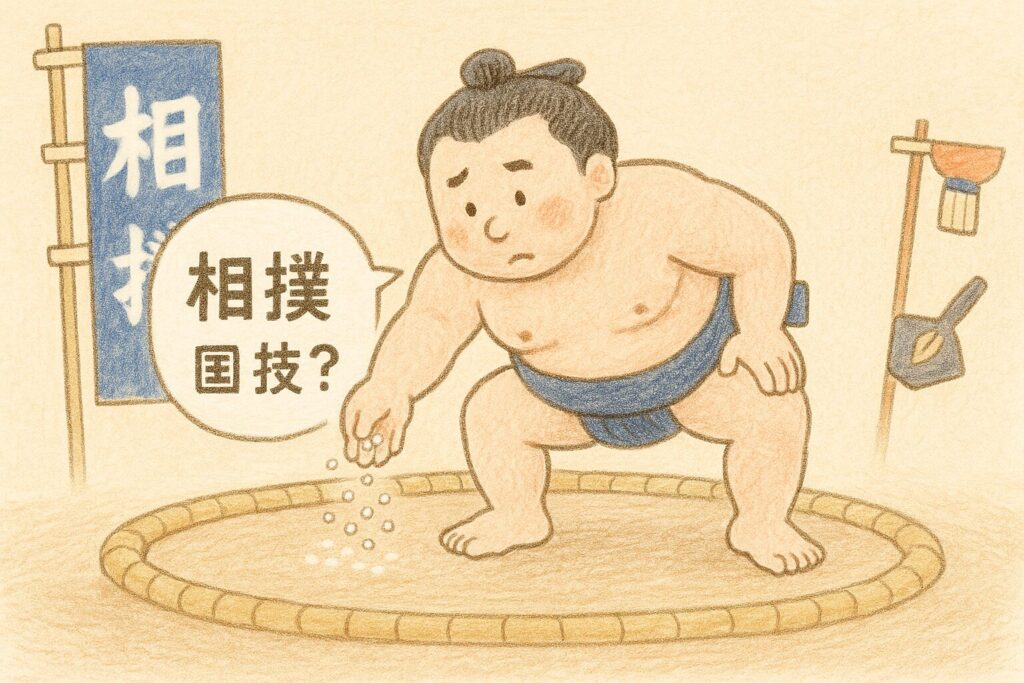
これは言い換えれば、
大切な場面に臨む前に心を整える習慣として
私たちの生活にも取り入れられます。
たとえば
大事なプレゼンの前に深呼吸して気持ちをリセットする、
部屋の掃除をしてから勉強や仕事に向かう、
といった行動は
「塩まき」と同じように
心を整える儀式として役立ちます。
さらに力士の「しこ名」や「化粧まわし」には
自分の誇りや覚悟を表す意味があります。
これも、
自分自身が人前に立つときに
「自分の名前に恥じないふるまいをしよう」と
意識することに置き換えられます。
相撲の精神は
日常の小さな行動にもヒントを与えてくれます。
たとえば
✅ けじめを大切にする → 約束を守る
✅ 挨拶や礼儀を欠かさない → 相手への敬意を表す
✅ 一度決めたことに全力で向き合う → 途中であきらめない
✅ 勝ち負けにこだわりすぎない → 自分がやれるだけやった達成感を大事にする
こうした相撲の考え方は
仕事のプレッシャーや人間関係のトラブルで
気持ちが乱れがちな現代人にとって
とても役立つメッセージです。
大切なのは
「勝つこと」だけではなく、
そこまでの努力や礼儀を大事にする
という価値観なのです。
相撲の「礼の型」とは?
相撲の世界では、
相手や観客、神さまに敬意を表すための
「礼(れい)」の型がとても大事にされています。
たとえば土俵に上がる前には
しっかりと腰を落として
両手を膝に置き、
背筋を伸ばしたまま深く頭を下げます。
これを「蹲踞(そんきょ)の礼(そんきょのれい)」と呼び、
「これから全力で勝負します」という
覚悟と礼儀を相手に伝える意味があります。
また、取組が終わった後には
勝った力士も負けた力士も
もう一度深く礼をして
相手への感謝を表します。
この礼には
「相手がいてこそ自分の力を試せる」という
相撲の精神が込められているのです。
さらに力士は土俵に上がる前に
結び目をきちんと整えた「廻し(まわし)」を直す動作をします。
これは「乱れた身なりで礼を欠かさない」という
日本の美意識の表れでもあります。
日常生活に置き換えると
✅ 面接の前に服装を整える
✅ お辞儀で相手に敬意を伝える
✅ 試合後に「ありがとうございました」と言う
など、当たり前のマナーの原点ともいえる
大切な習慣です。
こうした「礼の型」を知ると
相撲の魅力が
単なる勝負の迫力だけでなく
人としての振る舞いの美しさにまで
及んでいることがわかります。
あなたも
何かに挑戦するとき、
この相撲の精神を思い出してみませんか?
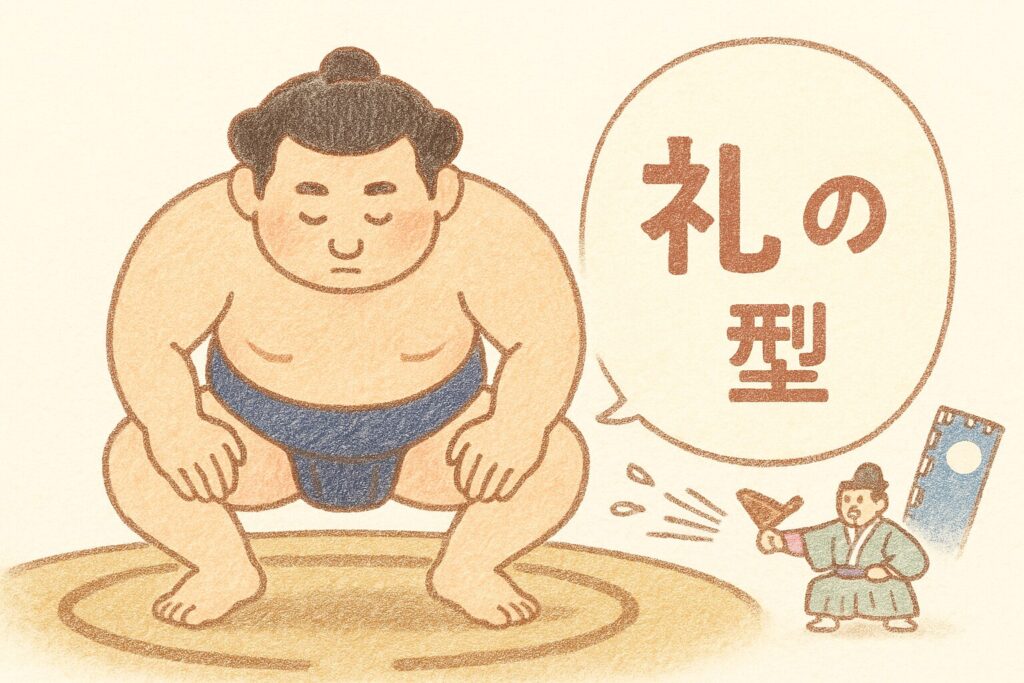
相撲にまつわる誤解と注意点
繰り返しになりますが、
相撲は法律で決まった「国技」ではありません。
「国技」という言葉はあくまで
国民に長く親しまれ、文化的価値が高い
という意味合いで使われているものです。
さらに
相撲には過酷な稽古やしきたりが多く、
力士の心身への負担が大きいことも事実です。
「相撲取りは健康的」と
単純にイメージしがちですが、
糖尿病や生活習慣病のリスクも高いという
研究報告もあります。
相撲を応援する気持ちはとても大切ですが、
現実の力士たちの健康問題にも
関心を寄せていくことが
これからの相撲文化には必要かもしれません。

おまけコラム
「相撲って日本の国技なんでしょ?」
と多くの人が感じていますが、
法律で定められた国技ではないというのが本当のところです。
実はこうした「事実上の国技」というのは
世界中に例があります。
たとえばインド。
インドではクリケットが圧倒的な人気を誇り、
試合ともなれば街中の人がテレビにかじりつき、
ワールドカップになると国を挙げてお祭りのように盛り上がります。
クリケット場には何万人もの観客が詰めかけ、
ヒーローとなった選手には街頭でパレードが行われるほどです。
ですが実はインドでも、
法律で「クリケット=国技」と決めているわけではありません。
国民の愛情と熱狂が「国技」という意識を生み出しているのです。
アメリカも同じです。
野球は「アメリカの国技」と言われますが、
法的にそう定めた条文は存在しません。
しかし、球場は家族の思い出の場所として親しまれ、
野球殿堂と呼ばれる「クーパーズタウン」のように
野球に特化した記念館があり、
まるで日本の国技館のように
人々が野球文化を讃えるシンボルになっています。
さらに韓国のテコンドーは
政府による普及活動が積極的に行われており、
教育課程にも取り入れられています。
この点は相撲と似ていて、
日本でも相撲の精神を学校教育に活かす取り組みがあります。
つまり
国技とは「法律」で決まるのではなく、
人々の心で決まるもの
といえるのです。
そしてそもそも「国技」という言葉自体は
明治時代以降に日本で広がったとされ、
国家の威信を示す競技を表す表現として
マスメディアなどで多用されるようになりました。
相撲の場合は、
1909年に建てられた「国技館」という建物の名前が
強烈なイメージを作り、
「相撲=国技」という意識が
さらに国民に浸透したと言われています。
国技館はまさに
相撲の聖地であり
大相撲の公式戦が行われる場所として
日本人にとって特別な意味を持つ施設です。
同じように
アメリカには野球殿堂(クーパーズタウン)、
インドには世界最大級のクリケットスタジアム、
韓国には国立テコンドー院があり
それぞれの競技を文化として守り伝える場所が存在します。
こうした「国技の象徴的な場所」は
単に競技を行うだけでなく
人々が集い、語り継ぎ、
次の世代へ伝える役割も担っているのです。
だからこそ、
相撲も単なる格闘技ではなく
礼儀や精神を重んじる文化として
今も人々に大切にされているのだと思います。
「あなたにとっての国技とは何ですか?」
そんな問いかけを、
この記事を読んだあとに
家族や友人と話してみるのも面白いかもしれません。
まとめ・考察
相撲は、
神事としての歴史を持ち、
日本文化に深く根ざしている
大切な伝統競技です。
ただし「国技」と呼ばれるのは
法律で決まっているからではなく
国技館という名前の影響や
長年の人気から自然にそう呼ばれるようになった
というのが本当のところです。
このような背景を知ると、
普段見ている相撲中継の印象も
少し変わるのではないでしょうか?
もしかしたら
「相撲の精神を少し日常に取り入れてみよう」
という気持ちになる人もいるかもしれません。
あなたなら
相撲のどんな部分を
自分の生活に取り入れてみたいですか?
さらに学びたい人へ
関連リンク・おすすめ書籍
公益財団法人 日本相撲協会公式サイト
『相撲の歴史をたどる』(日本相撲協会監修)
『大相撲40年史 ――私のテレビ桟敷』(小谷野敦/ちくま新書)
『物語日本相撲史』(筑摩書房)
特徴とおすすめ理由
📘公益財団法人 日本相撲協会 公式サイト
特徴:相撲の歴史から最新ニュース、番付、国技館情報、相撲博物館の展示まで、幅広く網羅された公式情報源です。
おすすめ理由:権威ある団体による情報なので、誤解や伝聞によらず正確。神事としての起源から現代の動きまで、多層的に理解するために必須です。公式サイト内の「相撲の歴史」ページでは、神話〜江戸〜現代までの流れが体系的にまとまっています。
📗『相撲の歴史をたどる』(日本相撲協会監修)
出版社:日本相撲協会
特徴:協会監修のガイド的な一冊で、年表・図版・写真が豊富。
おすすめ理由:教養と歴史をバランスよく学べる入門書として最適。神話から四股や礼の由来まで網羅されており、ビジュアルを通じて理解を深められます。日本相撲協会監修のため内容の信頼度も高いです。
📘『大相撲40年史 ――私のテレビ桟敷』
著者:小谷野 敦(文学博士・執筆家)
出版社:筑摩書房(ちくま新書)
特徴:1980年代から現代まで、テレビ放送に映った大相撲を世相と絡めながら解説。
おすすめ理由:相撲の歴史を「テレビ視聴者の記憶」という切り口で振り返るユニークな構成。角界の騒動、横綱相撲、外国人力士の登場などがエピソード豊かに描かれています。
📘 『物語日本相撲史』
著者:川端 要寿
出版社:筑摩書房
特徴:物語風の通史で、相撲の黎明期から国技化、現代までをドラマチックに描写。
おすすめ理由:読み物として面白く、歴史の流れをストーリーで追える点が素晴らしい。歴史好きや初心者にもおすすめです。
結びの言葉
相撲は、神事としての厳かな歴史と、
日本人の誇りとしての文化的な価値を
長い年月をかけて育んできた競技です。
法律で「国技」と決められているわけではないけれど、
多くの人に愛され、大切に守られてきたからこそ
自然に「日本の国技」として根付いたと言えるでしょう。
相撲の精神に触れることで、
礼儀やけじめの大切さ、
挑戦する心を学ぶことができます。
ぜひ、これから相撲を観るときには
ただのスポーツとしてだけでなく、
その背景に込められた深い意味を思い出してみてください。
これからも相撲を通じて、
日本文化の魅力を一緒に探求していけたらうれしいです。
補足注意
今回の記事は、
筆者個人が調べられる範囲で信頼できる情報源(日本相撲協会公式サイト・歴史資料など)をもとに
できる限り正確にまとめたものです。
しかし相撲の起源や国技の捉え方についてはさまざまな意見や研究があり、
今後の調査や学説の進展で変わる可能性もあります。
この答えがすべてではないことをご理解いただければ幸いです。
これからも相撲のように土俵を踏みしめ、一歩ずつ日本文化の奥深さを一緒に学んでいきましょう。
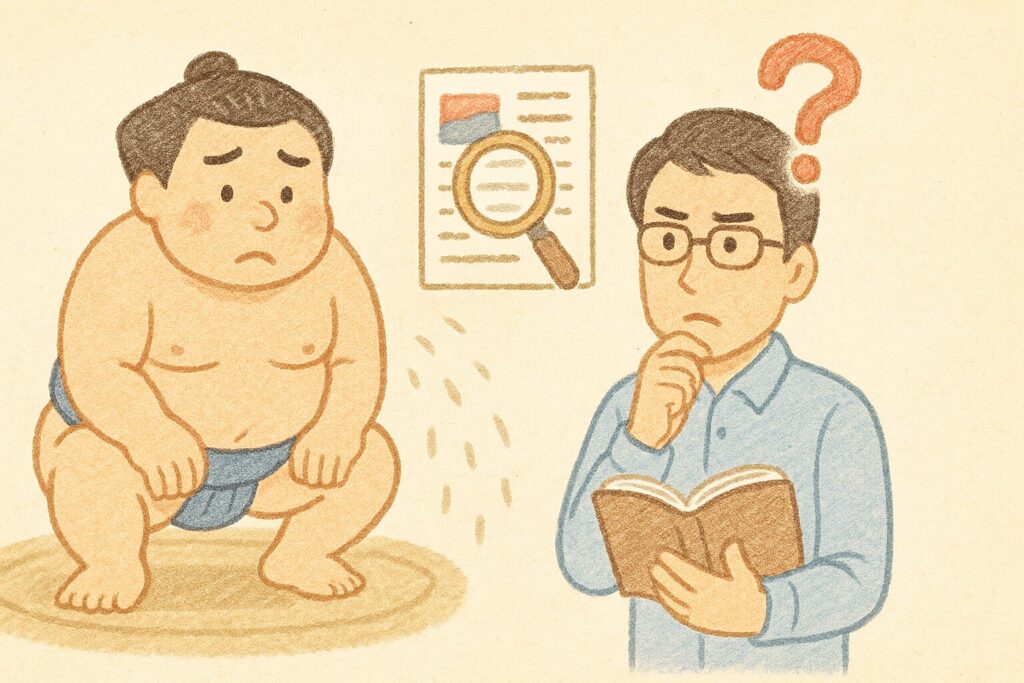
最後まで読んでいただき、
本当にありがとうございました。




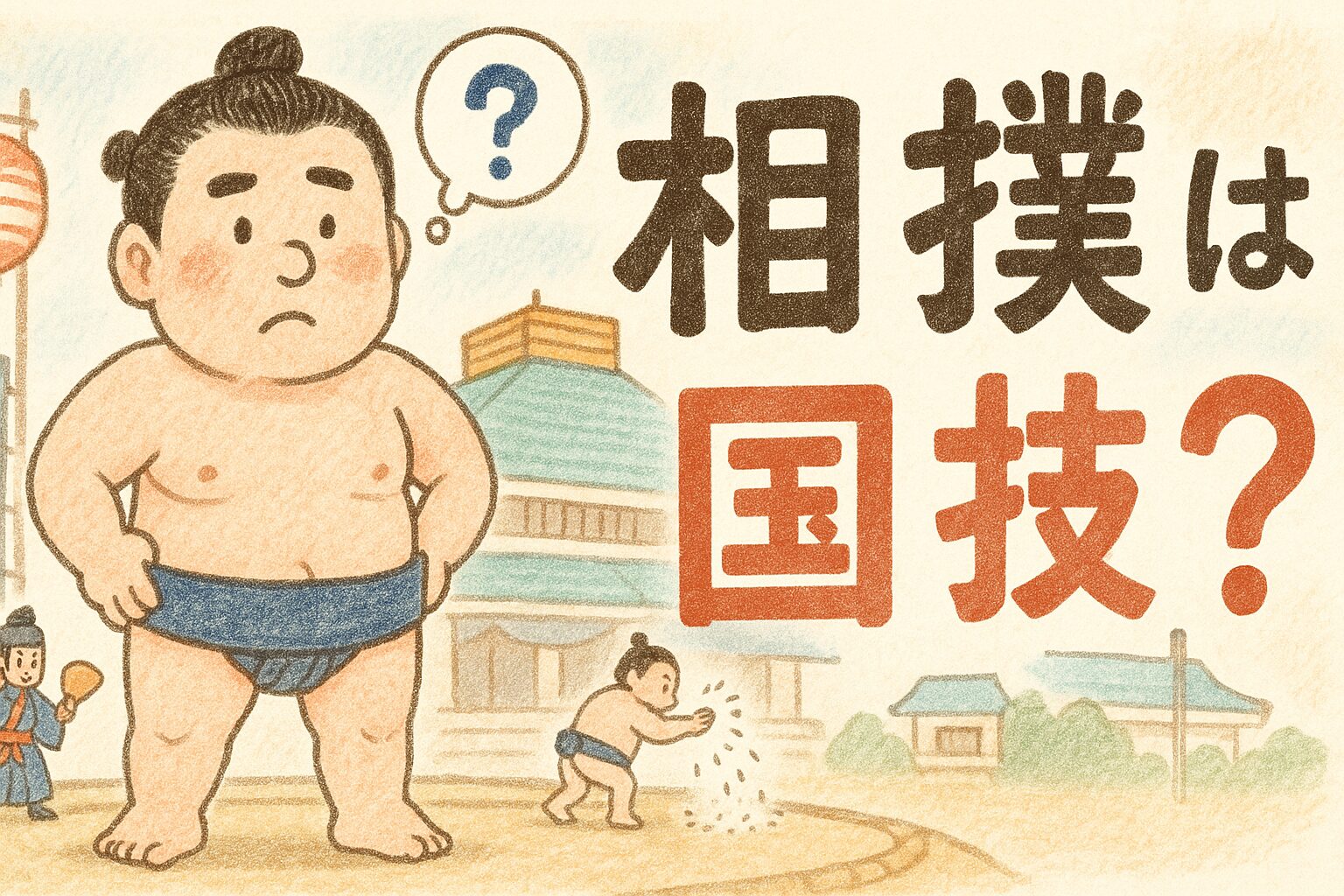


コメント